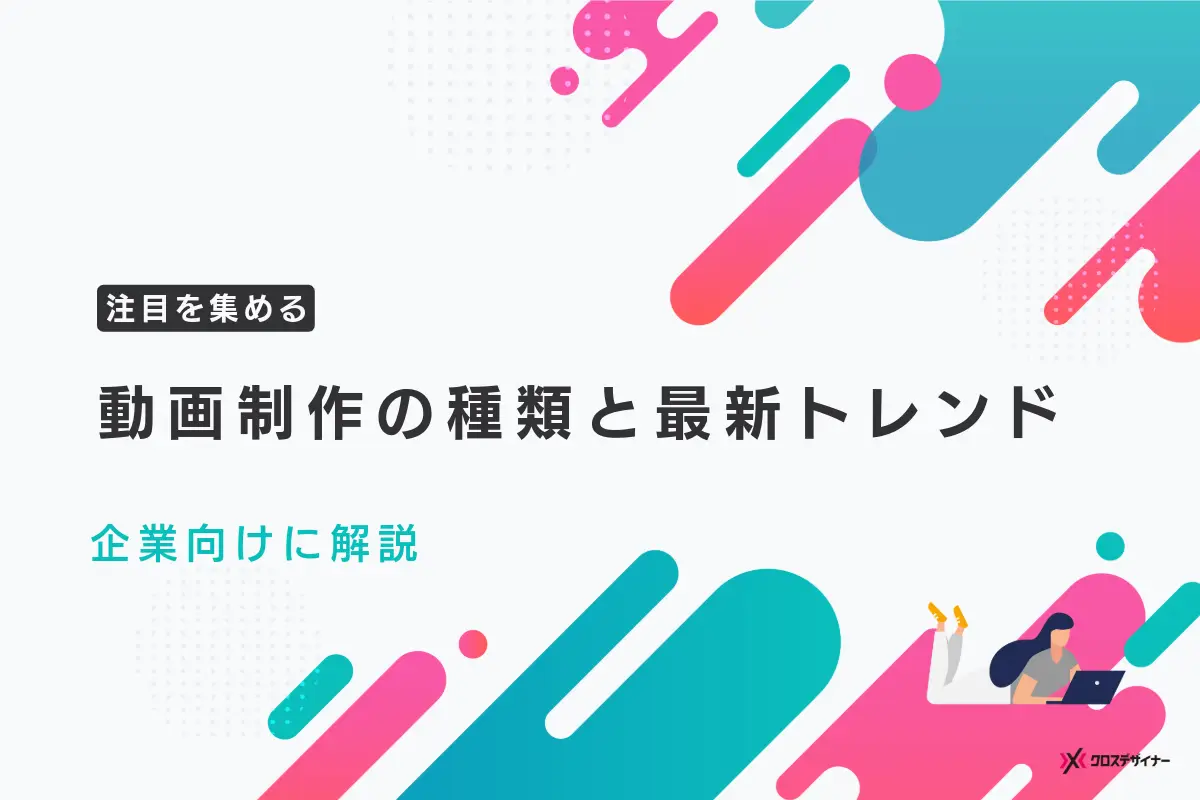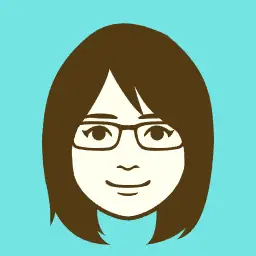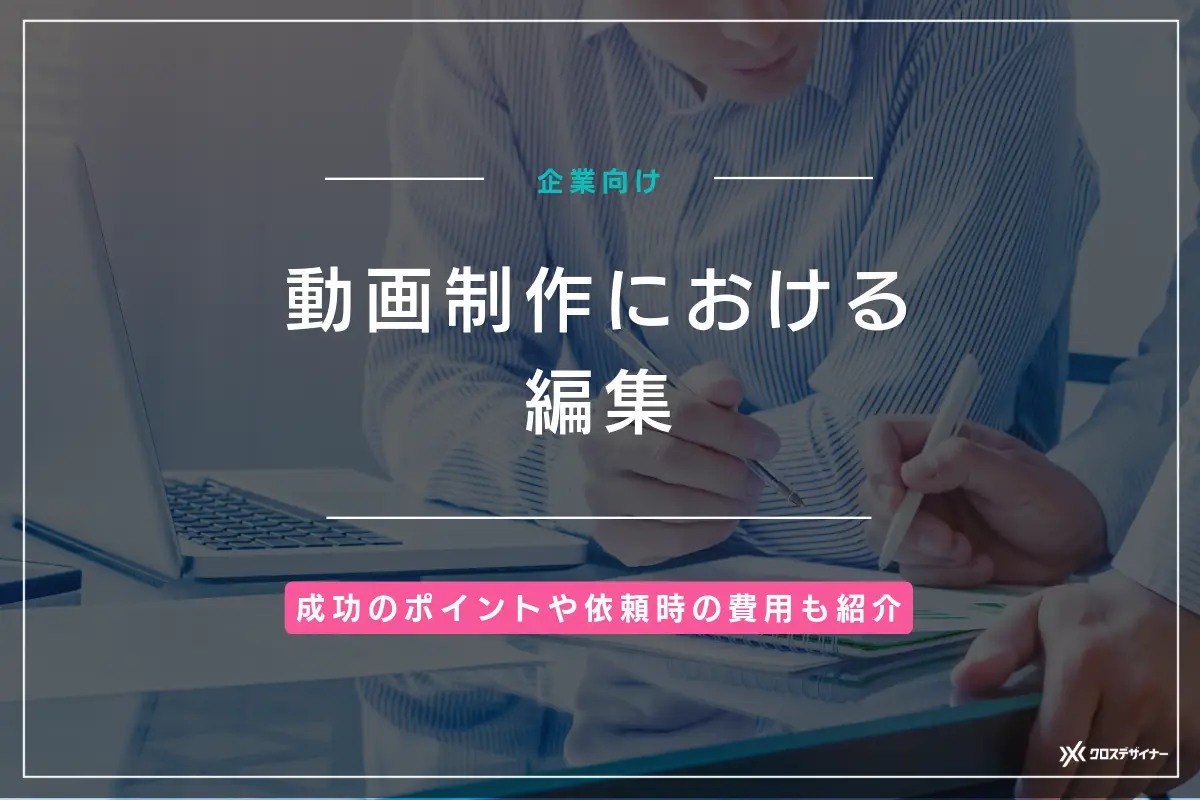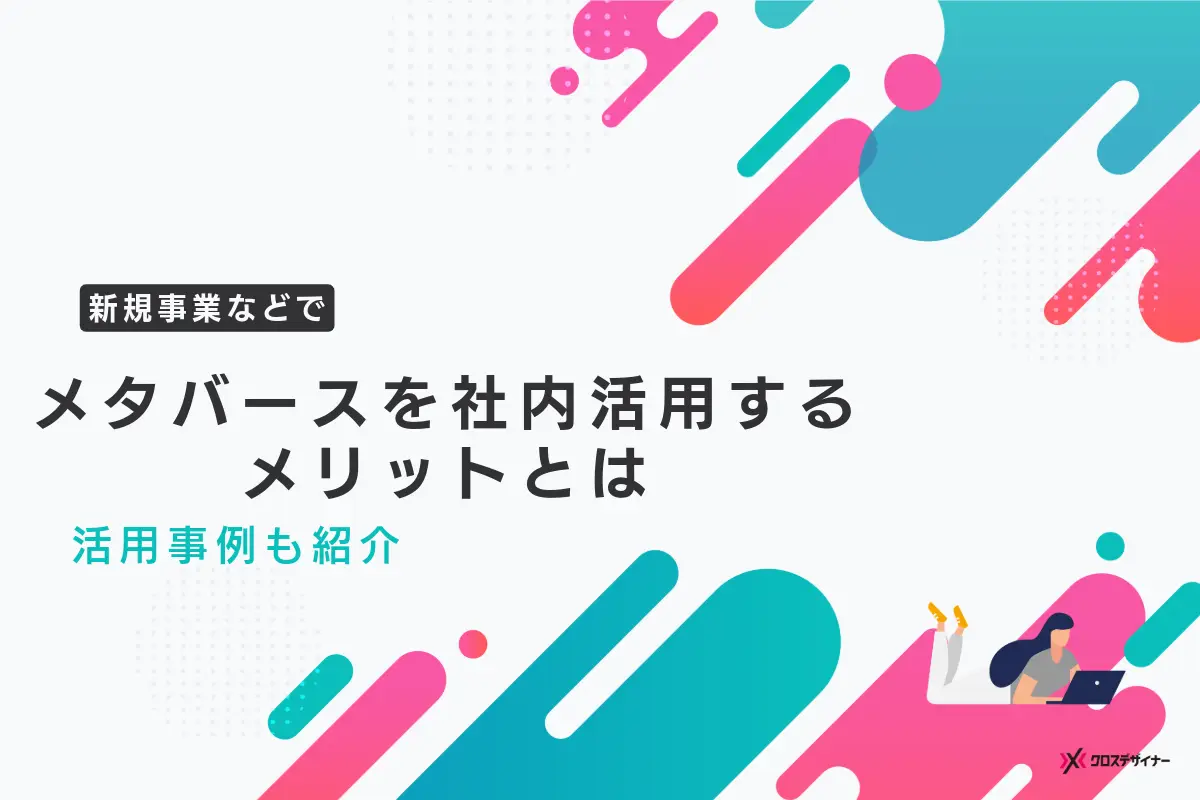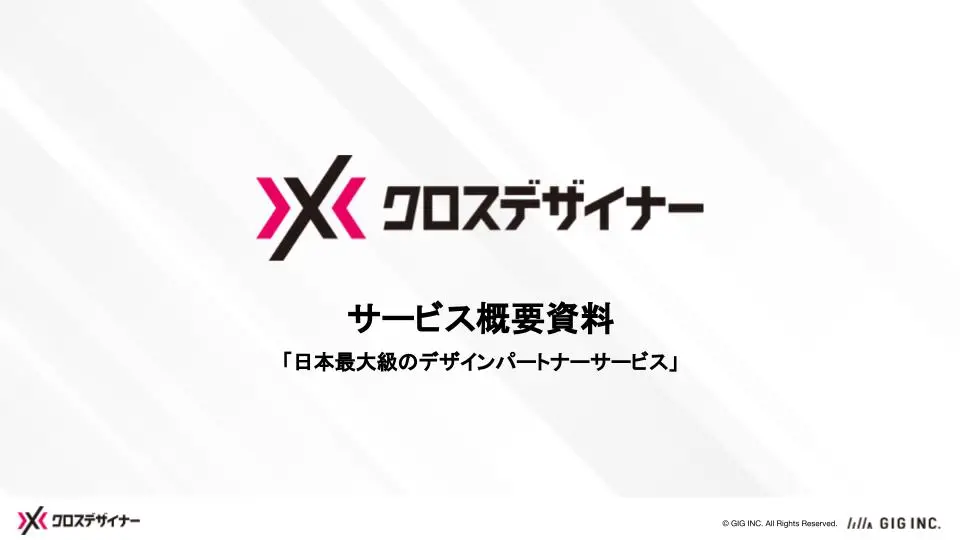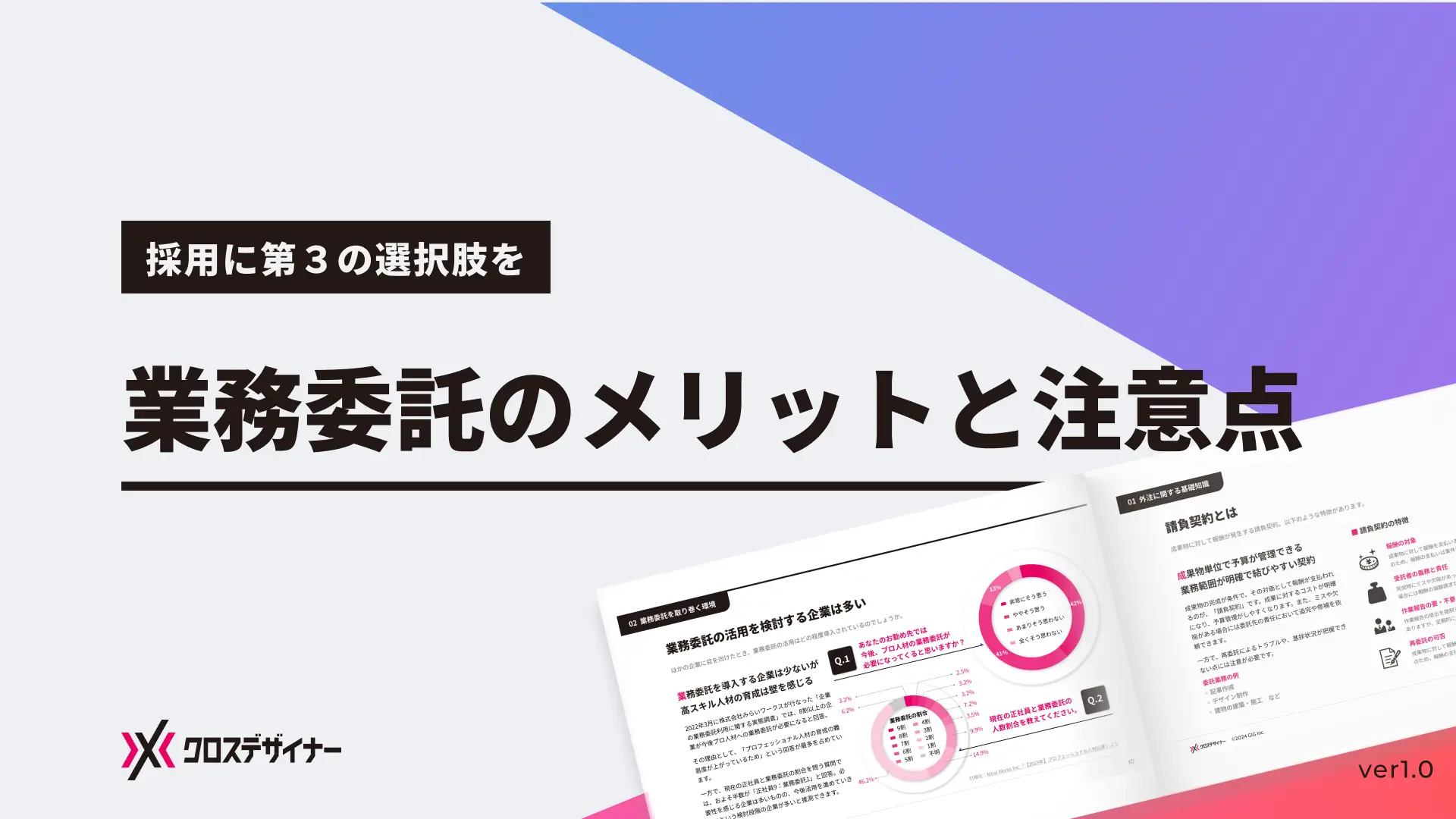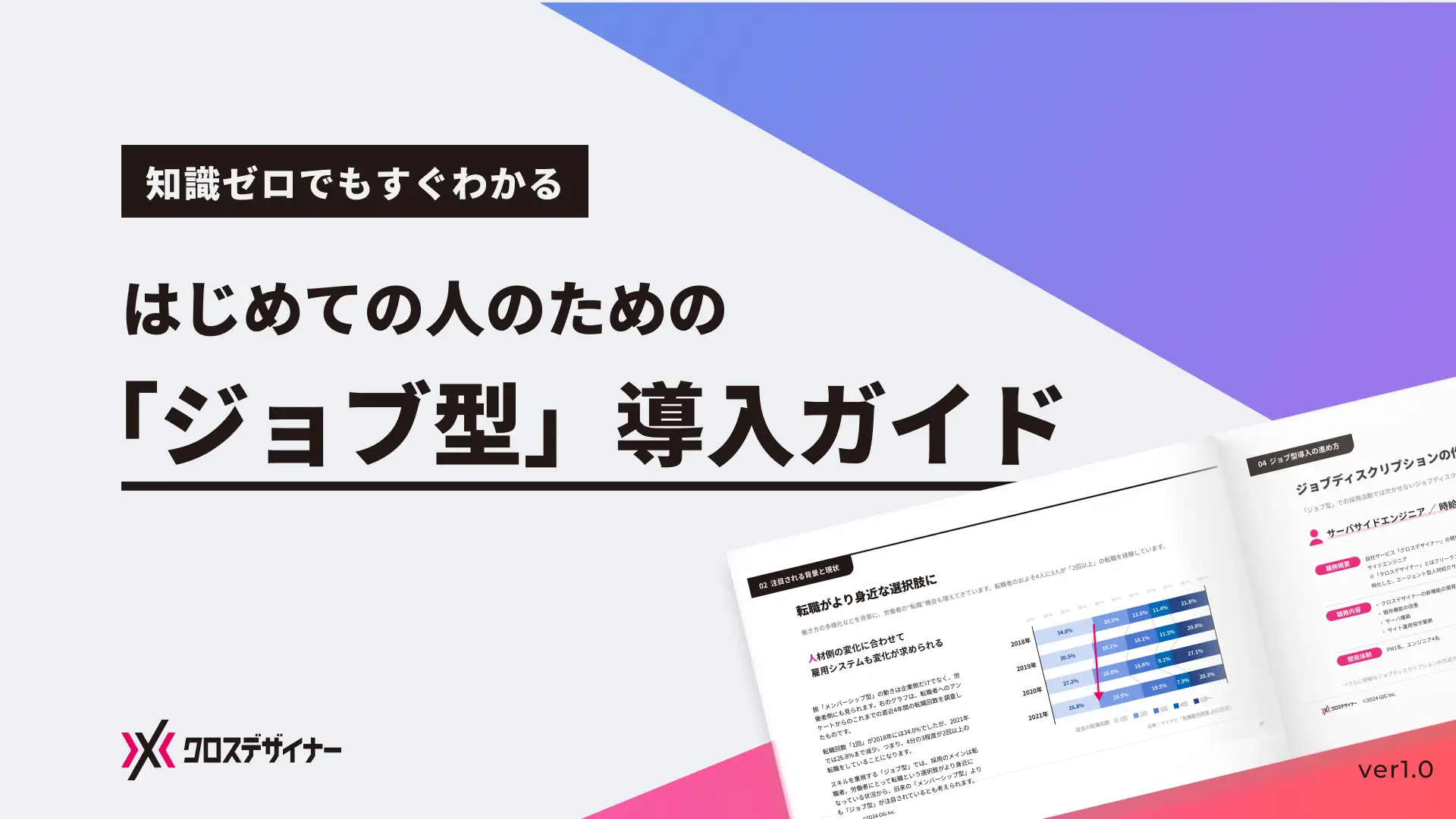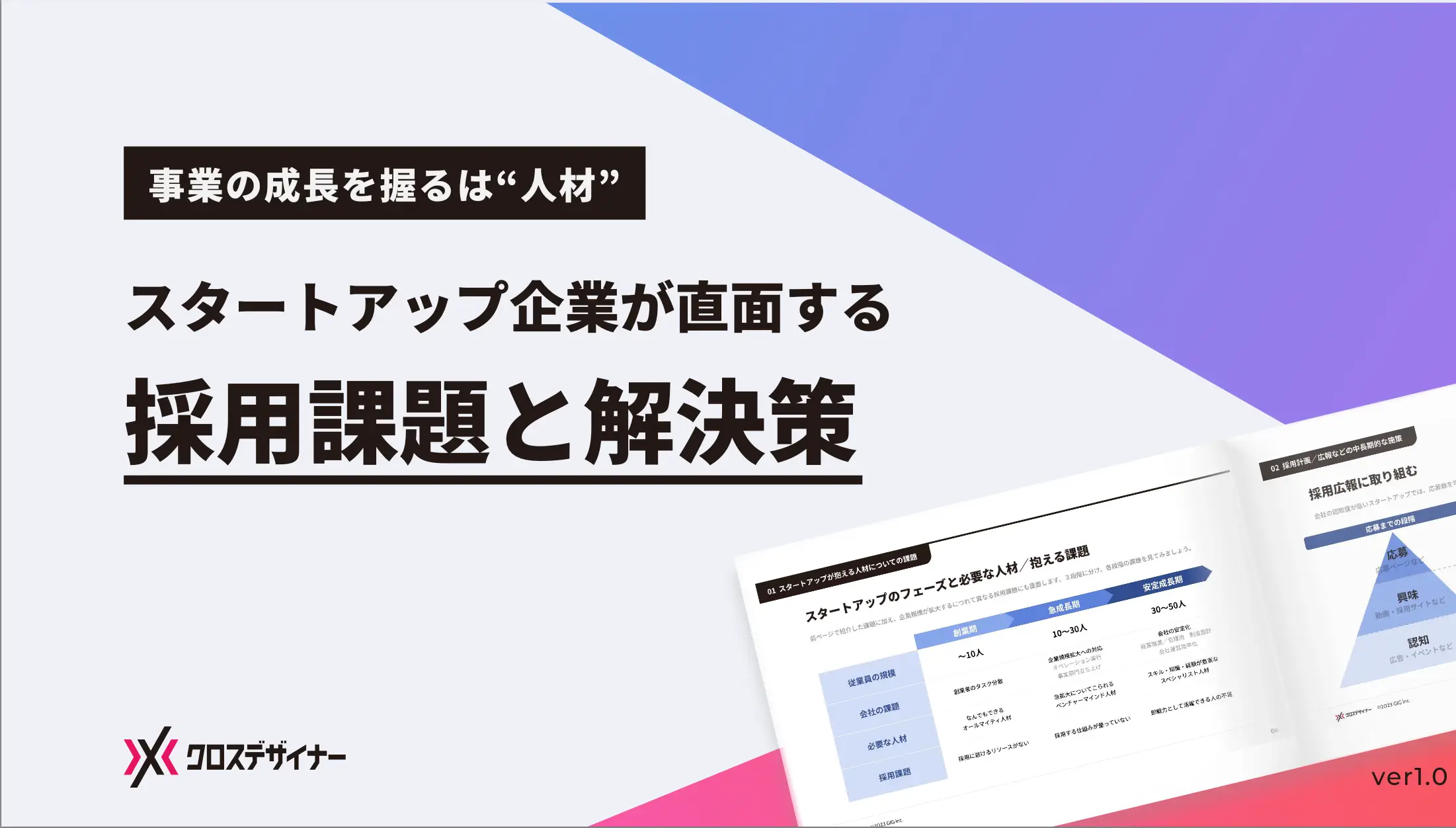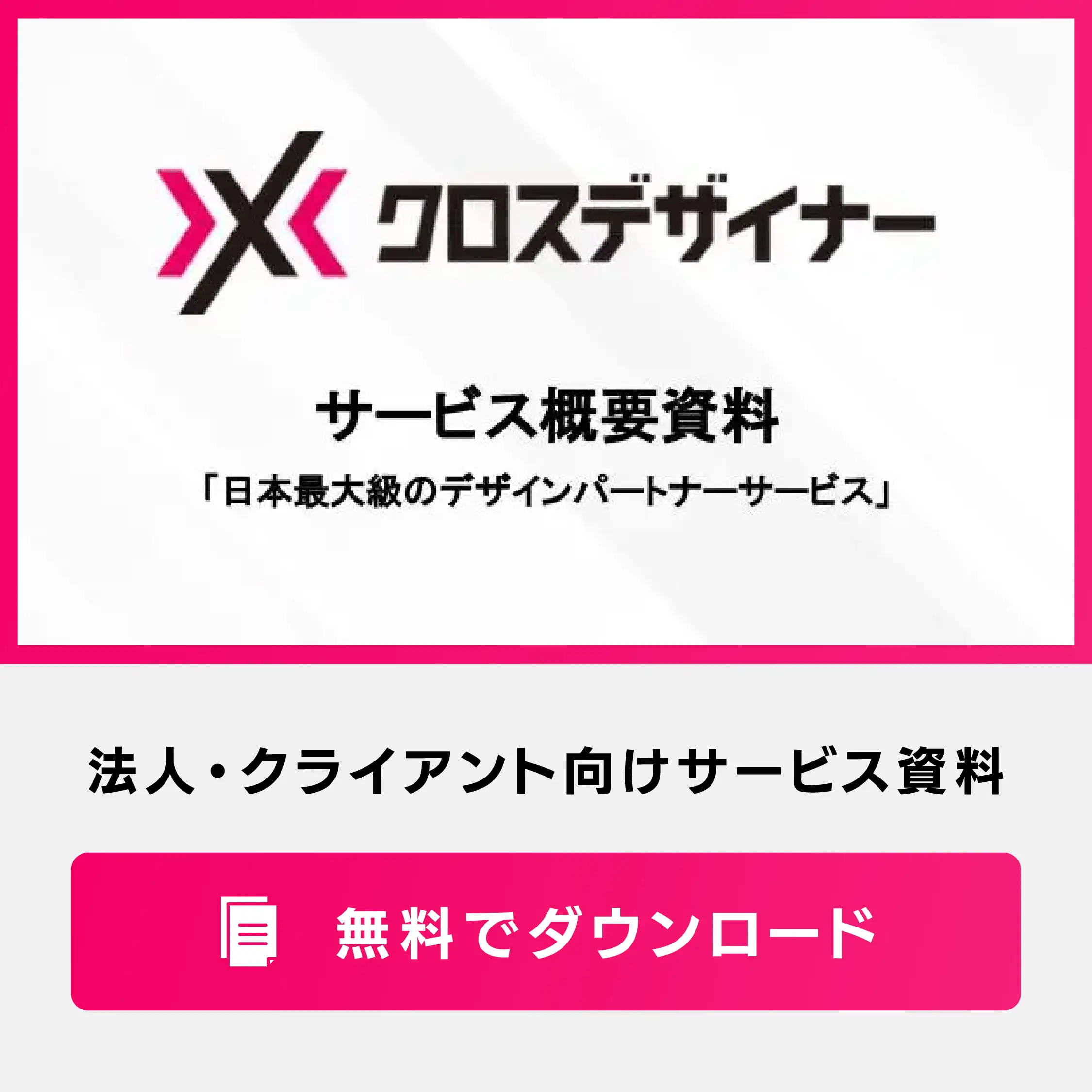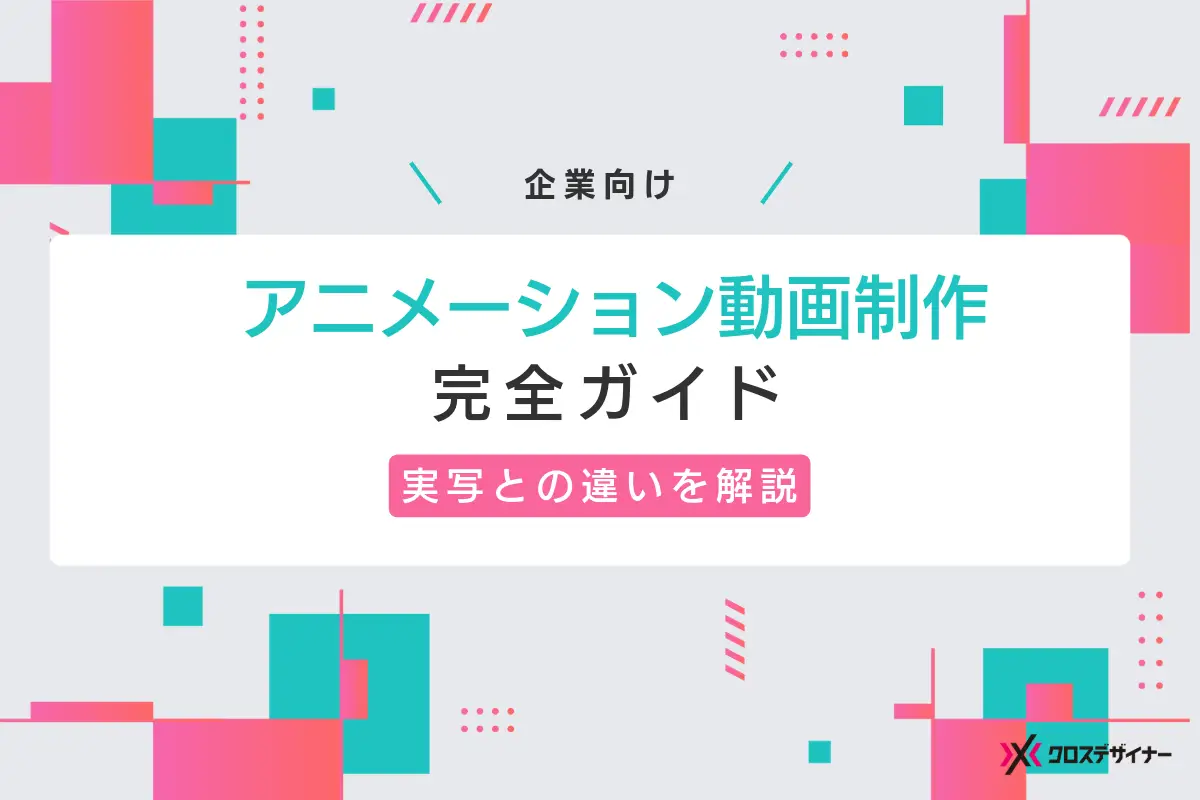
この記事では、企業向けに動画制作や動画コンテンツの種類について解説します。動画制作の最新トレンドや種類別の成功事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
動画制作の種類と特徴
動画制作の主な種類は以下の3つです。
- 実写
- アニメーション
- 3DCG
それぞれの制作方法の特徴やメリット・デメリットを以下の表にまとめました。
| 動画制作の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 実写 | ・実際の人物や風景を撮影して制作する。 | ・リアルなイメージや臨場感を伝えられる。 ・視聴者に安心感や信頼感を与える。 | ・撮影場所や出演者の手配、撮影コストが高くなる場合がある。 ・撮影対象を変更する際に撮り直しの費用が高額になる場合がある。 |
| アニメーション | ・イラストやキャラクターを使って制作する。 | ・実写より自由で幅広い表現が可能。 ・撮影場所や出演者の印象に左右されず意図した世界観を保てる。 ・視覚的な訴求力が高く、視聴者に伝わりやすい。 | ・制作に時間がかかることがある。 ・複雑な動きや詳細な表現にはコストがかかる。 |
| 3DCG | ・コンピュータグラフィックスを使って立体的な映像を制作する。 | ・立体的でリアルな表現が可能。 ・現実世界では撮影が難しい場所や、存在しない物体や空間も創造できる。 | ・高度な技術と専門知識が必要。 ・実写やアニメーションより制作コストが高くなる場合がある。 |
企業が動画を制作する際は、上記の特徴やメリット・デメリットを理解したうえで、自社のマーケティング戦略に合った制作方法を選ぶ必要があります。
動画コンテンツの主な種類
ビジネスで活用されている動画コンテンツの種類と特徴を把握しておくと、目的やターゲットに応じて適切な動画を制作するために役立ちます。
ここでは以下の7つについて解説していきます。
- プロモーション動画
- チュートリアル動画
- ブランディング動画
- 広報PR動画
- 採用動画
- トレーニング・教育動画
- イベント・ウェビナー動画
それぞれ詳しく説明します。
1.プロモーション動画
プロモーション動画は、製品やサービスの魅力を効果的に伝えるための動画です。短時間で多くの情報を伝えることができ、SNSやWebサイトでの拡散力も高いため、特に新製品の発売やキャンペーンの告知に効果的です。
視覚的なインパクトを持たせることで、ブランド認知度を向上させたり購買意欲を喚起させたりする効果が高まります。
Adobe Creative Cloudのプロモーション動画は、クリエイティブな表現と実際の使用シーンを組み合わせて、製品の魅力を効果的に伝えています。
Adobe Creative Cloudのここがイイ!Creative Cloud個人版のご紹介
2.チュートリアル動画
チュートリアル動画は、製品やサービスの使い方を分かりやすく説明するための動画です。動画を活用して手順を示すことで、ユーザーが理解しやすくなります。
特に複雑な操作や設定が必要な製品において、ユーザーのサポートツールとして有効です。顧客満足度の向上やサポートコストの削減にも効果があります。
ソニーはSPRESENSE™のチュートリアル動画で、SPRESENSE™とNeuralNetworkConsoleで始めるエッジAIプログラミングについて解説しています。
3.ブランディング動画
ブランディング動画は、企業の理念や価値観を伝えるための動画です。企業のストーリーやビジョンを動画で表現することで、視聴者に親近感や共感といった心理的なつながりを生み出します。
それにより顧客の信頼感を高めて、長期的なブランド価値の向上につながります。
トヨタシステムズのコンセプトムービーは、技術革新と未来のビジョンを表現し、視覚的な訴求力の強い映像になっています。
4.広報PR動画
広報PR動画は、企業の活動や最新情報を伝えるための動画です。新製品の発表やイベントの報告、社会貢献活動の紹介などを動画にして伝えることで、説得力や期待感を高めます。
一般消費者やメディア、投資家に向けて効果的に情報を発信でき、企業の透明性や信頼性を向上させます。
住友ゴム工業はCSR活動や最新技術を紹介する広報PR動画を多数公開しています。
5.採用動画
採用動画は、企業の魅力を求職者に紹介するための動画です。
職場の雰囲気や社員の声、企業文化を動画で表現することで、求職者にリアルなイメージを伝えます。
特に若年層に対して効果が高く、企業の魅力を具体的にアピールすることで、優秀な人材の獲得につながる可能性もあります。
デロイト トーマツ グループは、採用ブランドムービーで、個人の多様性を尊重し、すべての社員・職員に光を当て、潜在的な才能を輝かせる「People First」な組織を表現しています。
デロイト トーマツ【採用ブランドムービー】きのうのじぶんを超えていく、じぶんへ。
6.トレーニング・教育動画
トレーニング・教育動画は、社員のスキルアップや教育を目的とした動画です。
動画はテキストより教材として理解しやすく、繰り返し視聴することで学習効果を高めます。
特にリモートワークを実施していたり複数の拠点店舗を運営していたりする企業が教育ツールとして活用することで、教育コスト削減や研修の質の均一化などの効果が得られます。
東京労働局では、育児・介護と仕事の両立のための従業員研修の実施に活用できる動画などを公開しています。
7.イベント・ウェビナー動画
イベント・ウェビナー動画は、インターネット上で開催されたセミナーやイベントの内容を録画した映像を指し、オンラインで配信するために活用されます。
リアルタイムでの参加が難しい場合でも、動画を視聴することで情報を得ることが可能なため、参加者の拡大や情報の共有を促進します。
GMOインターネットグループは、日本最大級のセキュリティカンファレンス「GMOサイバーセキュリティ大会議&表彰式2025 」を開催し、アーカイブ動画を配信しています。
動画制作に関する注目のトレンド
動画制作に関するトレンドには注目すべきポイントがあり、取り入れることで、より効果的な動画制作が可能になります。
ここからは7つの主要なトレンドについて解説していきます。
- 動画ポッドキャスティング
- AIによる動画編集
- ショートビデオシリーズ
- UGC(ユーザー生成コンテンツ)とライブショッピング
- VTuberの活用
- 縦型動画
- Vlog
それぞれ詳しく説明します。
1.動画ポッドキャスティング
動画ポッドキャスティングは、音声ポッドキャストに動画要素を加えた形式です。
音声ポッドキャストの人気が高まる中で注目を集めるようになり、YouTubeやSpotifyなどのプラットフォームでの動画ポッドキャストが急増しています。
特にインタビューやディスカッション形式のコンテンツで効果を発揮し、視聴者のエンゲージメントを高める手法として活用されています。編集でハイライトを作成することで、SNSでのシェアも促進されます。
2.AIによる動画編集
AIの進化により動画編集の効率化が加速しています。AIを活用した動画編集ソフトを使用すれば、AIが映像の解析を行って自動でBロール(補足映像)を生成したり、最適なカット割やトランジションを追加したりすることが可能です。
これにより、編集者はクリエイティブに集中でき、制作時間が大幅に短縮されます。
関連記事:動画制作・編集の重要性や成功のポイントを企業向けに解説!おすすめソフトも紹介
3.ショートビデオシリーズ
ショートドラマとは、1話が30秒~3分程度の短時間で完結する物語形式の動画です。
TikTokやInstagramのリール、YouTubeショートなどのプラットフォームでは以前からショート動画が人気ですが、ショートドラマは2024年に急激に増加したジャンルで、TikTok上半期トレンド大賞2024のホットワード部門で「大賞」を受賞しました。
多くの企業がショートドラマを活用してプロモーションを行っており、広告感が抑えられスキップされにくい傾向があることから注目を集めています。
4.UGC(ユーザー生成コンテンツ)とライブショッピング
UGCは「User Generated Content」の略で、ユーザーが生成するコンテンツを指します。
具体的には、SNSの投稿、情報サイトに寄せられるクチコミやレビュー、レシピサイトに投稿されたレシピなどが挙げられます。フォロワーの多いユーザーが投稿すると影響力が大きく、ブランドの認知度向上が一気に高まる可能性もあります。
ライブショッピングとは、ライブ配信で商品やサービスを紹介し、視聴者がリアルタイムで買い物をする販売形態です。アパレルブランドや化粧品メーカーが、ショップ店員やインフルエンサーに依頼してライブ配信を行い、商品の使用方法や魅力を紹介するといった形で活用されています。
これらを組み合わせることで、視聴者の購買意欲を高めてエンゲージメントを向上させることが可能です。
5.VTuberの活用
VTuberとはバーチャルYouTuberの略で、2Dや3Dのキャラクターを使って動画配信やライブ配信を行うYouTuberのことです。
企業や自治体が、プロモーションや認知度向上にVTuberを活用するケースが増えています。
企業系VTuber初(※サントリー調べ)となる歌手デビューを果たしたサントリー公式VTuber「燦鳥ノム」や、自治体初の公認Vtuber茨城県の「茨ひより」などが代表的です。
6.縦型動画
縦型動画とは、スマホを縦向きにしたまま再生するためにサイズを合わせて作成された動画です。
動画を視聴する際のデバイスがスマホ中心になる中で、横型動画を縦で見るよりサイズが大幅にアップするため見やすいことから需要が高まっています。
TikTokやInstagramなどのSNSでは主流となっており、短時間で視聴できるため視聴完了率が高いことが特徴です。縦型動画を商品紹介やブランドストーリーなどのマーケティングに活用する企業が増えています。
7.Vlog
Vlog(ブイログ)とは、Video Blog(ビデオブログ)の略で動画形式のブログを指し、Vlogを作成・公開する人のことをVlogger(ブイロガー)といいます。
主に日常生活や食事、旅行など趣味に関する内容で、自然体で撮影し簡単に編集して投稿したものが多く、SNSでは以前から引き続き人気の映像ジャンルとなっています。特に若い世代を中心に多くの視聴を集めており、共感や憧れを抱かせるコンテンツが好まれています。
トヨタや無印良品など多くの企業がVloggerとコラボして製品の魅力を効果的に伝えています。
種類別にみる動画制作の成功事例
ここで、動画制作の成功事例について、種類別にマーケティング戦略の目的や効果について解説します。動画制作の成功事例も紹介するのでぜひ参考にしてください。
1.新商品ローンチ動画
新商品ローンチ動画とは、企業が新しい商品やサービスを市場に投入する際に、テキストや画像だけでは伝わりづらい魅力を動画でわかりやすく表現する目的で制作します。リアルな使用シーンやユーザーの声を盛り込み、SNSで公開することにより、消費者の興味を引き、購買意欲を喚起したり商品の認知度を高めたりする効果があります。
新商品ローンチ動画は効果的なマーケティング手法の一つとして、多くの企業で活用されています。
Appleは新しいiPhoneを発表する際、毎回大規模なイベントと共に高品質なプロモーション動画を公開します。これにより、製品の特徴や魅力を視覚的に伝え、消費者の期待を高めています。
2.採用動画
採用動画は、企業が求職者に対して自社の魅力や職場環境を効果的に伝えるために制作します。
動画を視聴した求職者は、企業の雰囲気や働き方を具体的にイメージすることができ、採用のミスマッチを減らす効果が期待できます。これにより、応募者の質が向上し、早期退職のリスクを抑えられる可能性もあります。
また、SNSやYouTubeなどで拡散されることで多くの人にリーチでき、企業やブランドの認知度の向上につながります。
LINEヤフーには、さまざまな領域で活躍する社員が数多く在籍しており、新卒入社から早くも重要な役割を担っている若手社員も多くいます。入社2年目の若手社員への密着動画で、オフィスでの働き方や仕事内容、その魅力について知ることができます。
【1日密着】LINEヤフー入社2年目 営業職女性社員の1日に密着
ヤマハは、採用動画として世界中のクライアントとともに感動を創る社員の挑戦や想いを紹介する映像を制作。製品や技術を紹介しつつ、社員のインタビューや職場の様子を交えて、ヤマハでの働き方や仕事のやりがいを伝えています。
【採用広報動画】Yamaha's Challenge ‐ Speaker Unit Development -
3.オンラインセミナー動画
オンラインセミナーは、見込み顧客を集めるための効果的な手段です。オフラインで行っていたセミナーをオンラインセミナーへ移行し、動画を活用することにより、地理的制約がなくなり、遠方の見込み客を取り込むことが可能です。
製品やサービスの詳細な説明やデモンストレーションを行うことで、顧客に価値を伝え、理解を深めてもらうことができます。企業の専門知識や業界での立ち位置をアピールし、ブランドの認知度と信頼性を高めることにもつながります。
また、セミナーで質疑応答の時間を設ければ、顧客との直接的なコミュニケーシを図ることが可能です。セミナー後の成約率や売上の上昇といった効果も期待できます。
村田製作所では、参加者のPCやスマホを使って好きな場所で参加できるウェビナーを実施しています。サイトでは、製品やアプリケーション、言語などの条件を指定してウェビナーを検索できます。また、過去のウェビナーの視聴や資料のダウンロード、次回のライブウェビナーへの登録を行うことも可能です。
4.ブランディング動画
ブランディング動画は、企業やブランドの歴史や理念、ビジョンを伝えるために制作し、動画視聴者に企業の信頼性や好感度を高める効果があります。
特に感動的なストーリーやユーモアを含む動画は、SNSでシェアされやすく、多くの人々にリーチすることも可能です。
また、ブランディング動画はBtoB(企業間取引)でも効果を発揮します。企業の専門知識や技術力を動画に盛り込むことで、取引先やパートナー企業の信頼感の醸成につながります。
ユニクロは生活に寄り添う服=「LifeWear」というコンセプトを伝えるために、ユニクロの製品がどのように日常を豊かにするかを描いたブランディング動画を制作しています。
2025 Spring&Summer LifeWear Collection "Sunny Moments"-15秒
スターバックスは世界中の店舗での顧客の交流を描いたドキュメンタリースタイルの動画で、スターバックスが単なるコーヒーショップではなく、人々が集まり交流する場所であることを伝えています。
5.CSR活動紹介動画
CSR活動紹介動画は、企業が環境保護活動や地域貢献プロジェクトを紹介するための動画です。
社会貢献活動や環境保護の取り組みを効果的に伝えて、企業の社会貢献意識をアピールし、ポジティブなブランドイメージを構築することができます。
また、社会貢献活動に積極的な企業は、求職者にとって魅力的に映ります。CSR動画を通じて企業の理念や活動を伝えることで、共感する優秀な人材の採用につながる可能性があります。
パナソニックは、環境保護活動をテーマにしたCSR動画を制作。「ACT-CAST」とは、パナソニックグループの企業市民活動を1分間でわかりやすく紹介するアニメーション動画シリーズです。生物多様性保全のための取り組みを紹介し、パナソニックの環境意識の高さを伝えています。
サントリーは、「水と生きる」という企業理念をテーマにしたCSR動画を制作。水資源の保護や環境保全活動に関する取り組みを紹介し、視聴者にサントリーの環境意識をアピールし、ブランドイメージを強化しています。
サントリー天然水の森 『水と生命(いのち)の未来を守る 』 ロングバージョン 13分30秒
動画制作の主な依頼先とメリット・デメリット
動画編集の主な依頼先は以下の3つです。
- 動画制作者を採用する
- 動画制作会社に依頼する
- フリーランスに依頼する
それぞれのメリット・デメリット、費用相場について詳しく説明します。
動画制作者を採用する
動画編集者を採用して社内で制作すると、外注費が掛からず、依頼後のコミュニケーションも取りやすい点がメリットです。特に自社で運営しているSNSの動画配信など、新鮮な情報発信やリアルタイムで対応が求められる動画については、内製したほうが良い場合があります。
内製するかどうかの判断ポイントは次の2点です。
- 定期的に作業が発生する
- できるだけ早い対応が必要
しかし、社員を雇用した場合は繁閑差や雇用ミスマッチが発生した場合でも一方的に解雇することは難しくなります。スキルやノウハウがない場合は対応できない点もデメリットで、人材育成にコストがかかります。
以下の資料では、デザインのリソースを確保する二つの手法として、外注と採用について比較しながらご紹介しています。無料でダウンロードできるので、ぜひご参照ください。
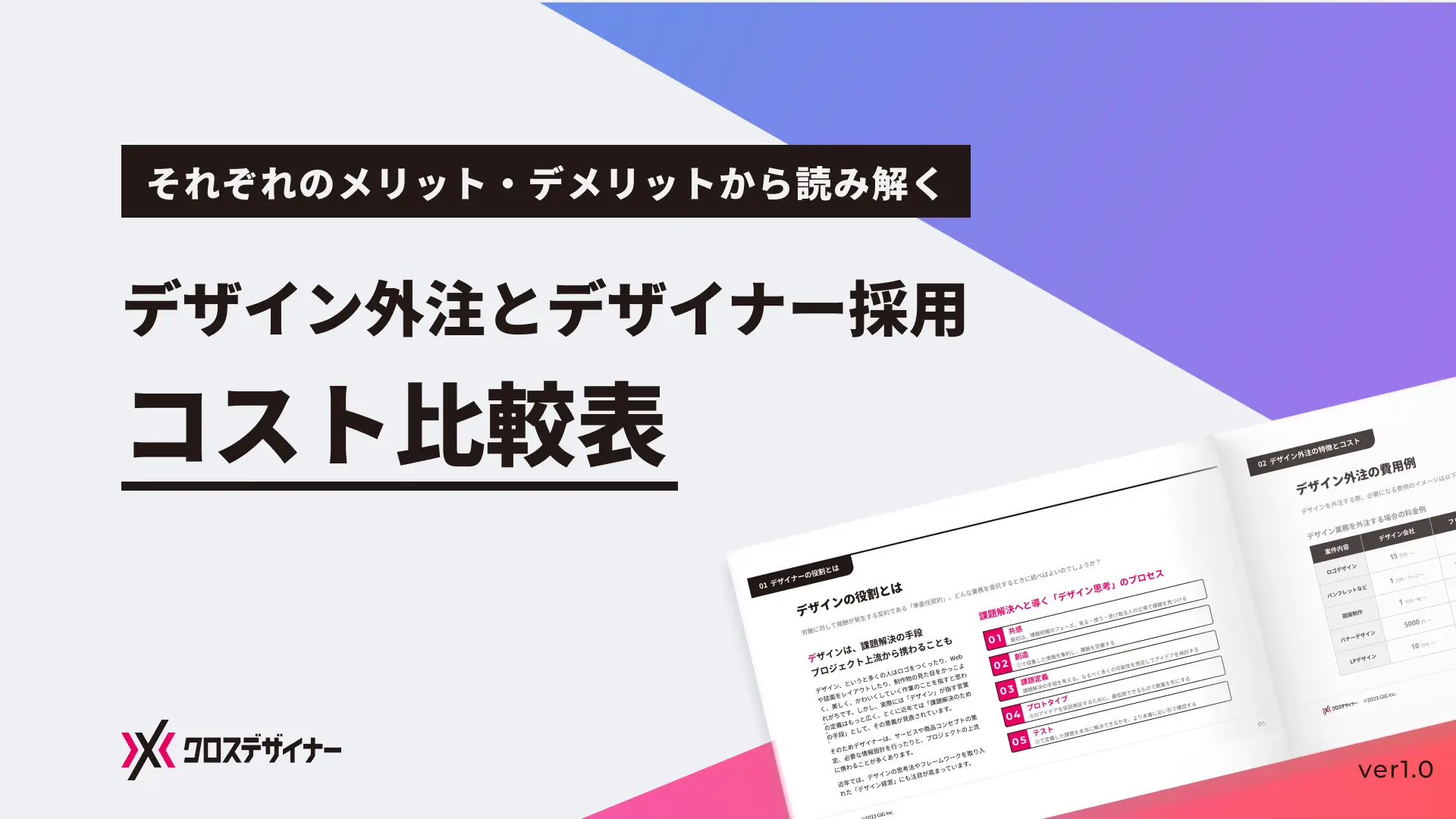
動画制作会社に依頼する
動画コンテンツのクオリティの高さや制作後の運用サポートを求めるなら、動画制作会社に依頼することをおすすめします。ただし、制作にコストや時間がかかる点がデメリットです。
動画制作会社に依頼すべきか判断する際のポイントは以下になります。
- 一定以上のクオリティを求める
- 予算・制作期間にある程度余裕がある
- 広告運用やマーケティング視点を踏まえた戦略設計も依頼したい
また、動画制作会社への依頼を検討しているものの、どこを選んだら良いかわからないといった方もいるでしょう。そのような場合は、依頼する動画の種類やジャンルでの実績があるか、人材が豊富かを基準に選ぶことをおすすめします。
関連記事:動画制作を外注する際の流れや費用相場、依頼先の選び方を徹底解説
関連記事:動画制作を依頼するには?その流れと依頼先の種類を紹介
フリーランスに依頼する
動画制作のスキルや実績があるフリーランスに依頼するという選択肢もあります。
最近では、クオリティの高い動画を配信しているクリエイターに動画制作を依頼する企業も増えています。
基本的に動画制作会社よりフリーランスに依頼するほうが費用を抑えられるため、スピードを重視して低コストで仕上げたい場合におすすめです。
クリエイターに直接依頼するためコミュニケーションがとりやすく、編集のみなど部分的な依頼も可能で、柔軟な対応が期待できる点もメリットでしょう。
次の場合、フリーランスのクリエイターに依頼することをおすすめします。
- 依頼したい外部クリエイターが決まっている
- 編集のみなど部分的な依頼をしたい
- 費用を抑えたい
一方、クリエイターによってスキルにバラつきがあるため、品質に差が出る点がデメリットです。また、フリーランスは遅延・廃業のリスクもあることを念頭に置き、信用できる人物かを見極めることも重要です。
関連記事:動画制作を個人のフリーランスへ依頼する際の費用相場や流れを解説
企業間の人材獲得競争が激化するなか、フリーランスなどの外部人材をいかに活用できるかが重要な要素となっています。
以下の資料では、外部人材を獲得するチャネルとしてよく挙げられる「業務委託」「派遣」「クラウドソーシング」に着目し、活用プロセスの違いやメリット・デメリットを解説しています。無料でダウンロードできるので、人材リソースの有効活用にお役立てください。
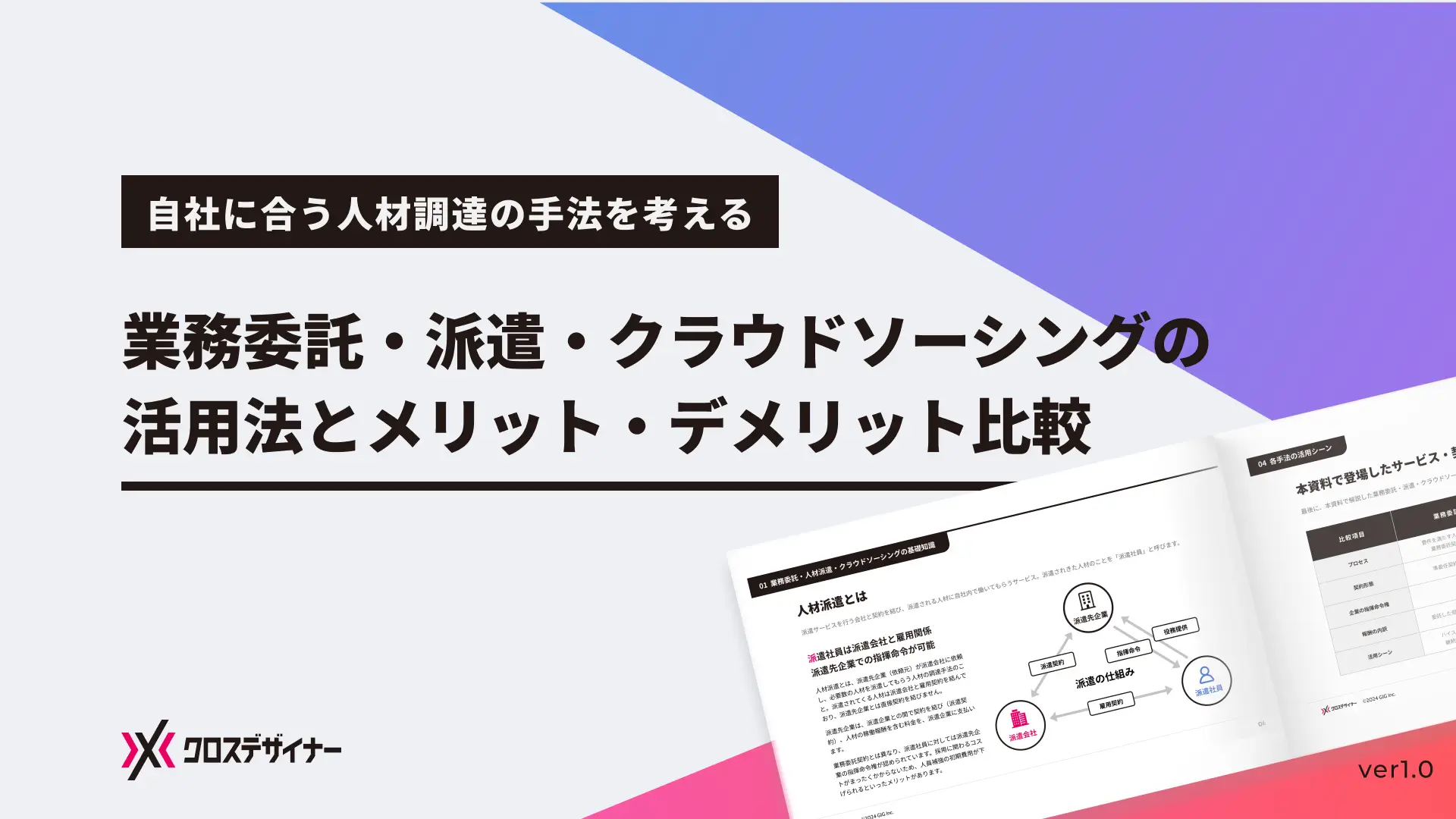
また、以下の資料では、「クロスデザイナー」に登録している注目デザイナーのリストの一部をご覧いただけます。こちらも無料でダウンロードできるので、ぜひご参照ください。
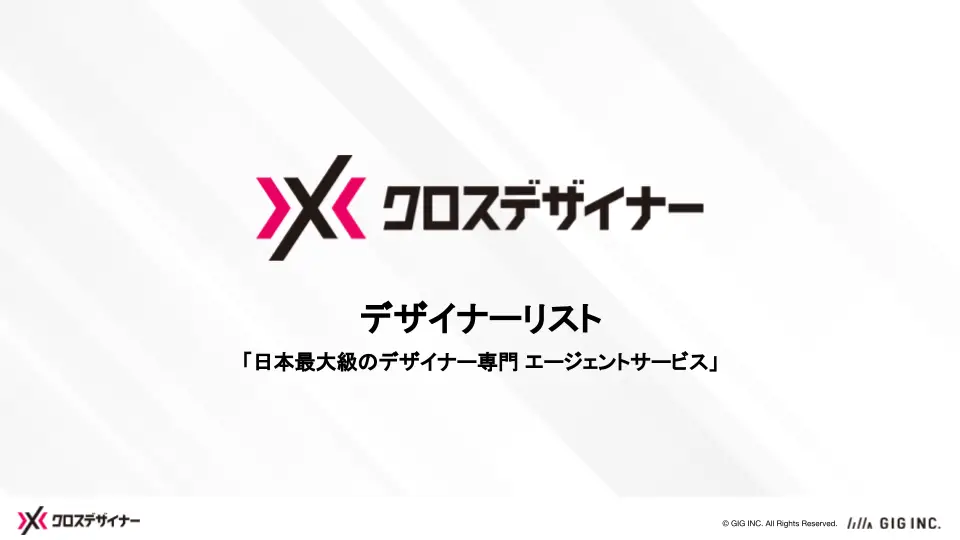
動画制作をフリーランスに依頼するならクロスデザイナーがおすすめ
本記事では、企業向けに動画制作や動画コンテンツの種類について詳細に解説しました。動画制作の最新トレンドや種類別の成功事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
動画制作を依頼する際に、「動画制作者を雇用する」「動画制作会社に依頼する」「フリーランスに依頼する」という3つの方法が考えられますが、依頼したい外部クリエイターが決まっている場合はもちろん、スピードを重視して低コストで仕上げたい場合もフリーランスへ依頼することをおすすめします。
クリエイターに直接依頼するためコミュニケーションがとりやすく、編集のみなど部分的な依頼も可能で、柔軟な対応が期待できる点もメリットです。
その際、フリーランスへ動画制作を依頼するなら、業界に詳しいクリエイター専門のマッチングサービスを利用するのがおすすめです。
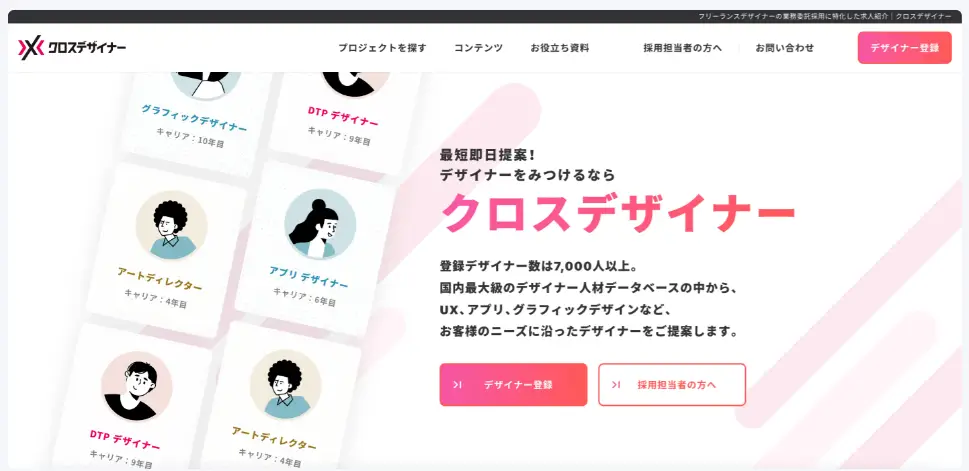
デザイナー専門の国内最大級エージェントサービス『クロスデザイナー』なら、厳正な審査を通過した即戦力のデザイナーや動画クリエイターが7,000人以上在籍。採用コンサルタントが、自社に必要なデザイナーのスキルや要件をヒアリングして最適な人材を紹介します。
以下では、『クロスデザイナー』のサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents