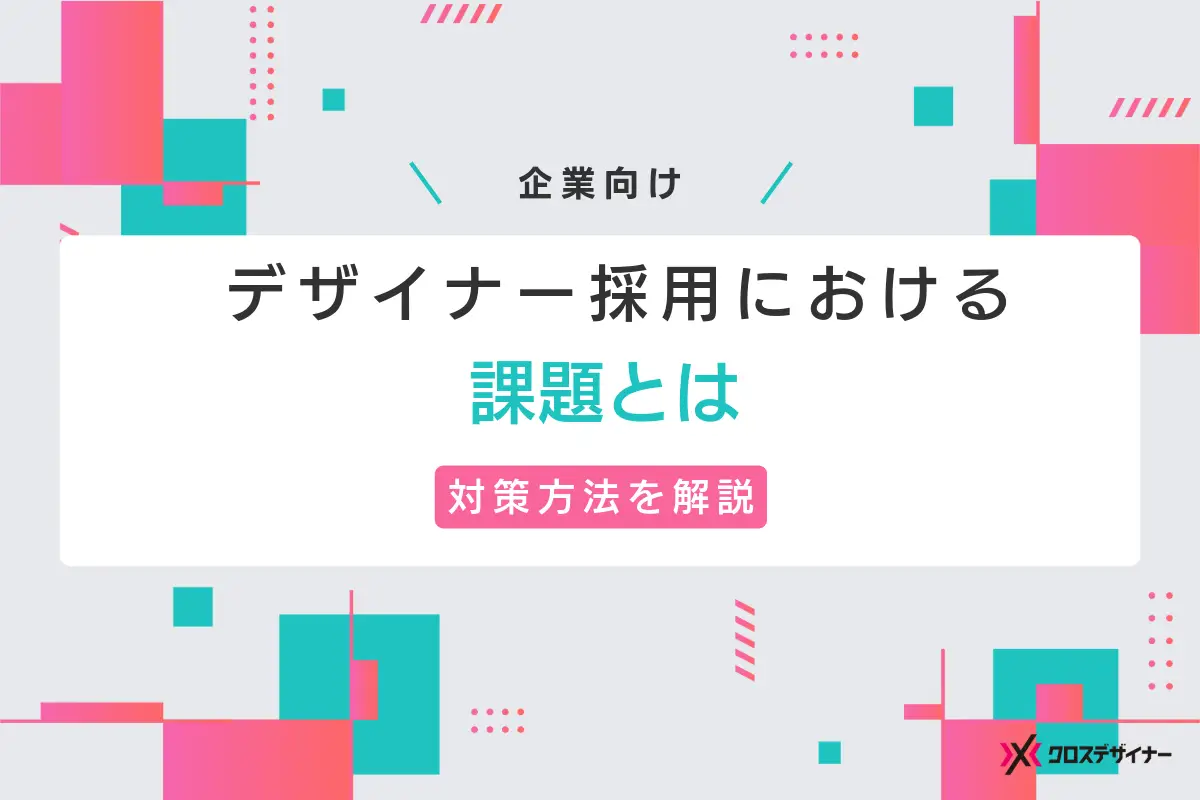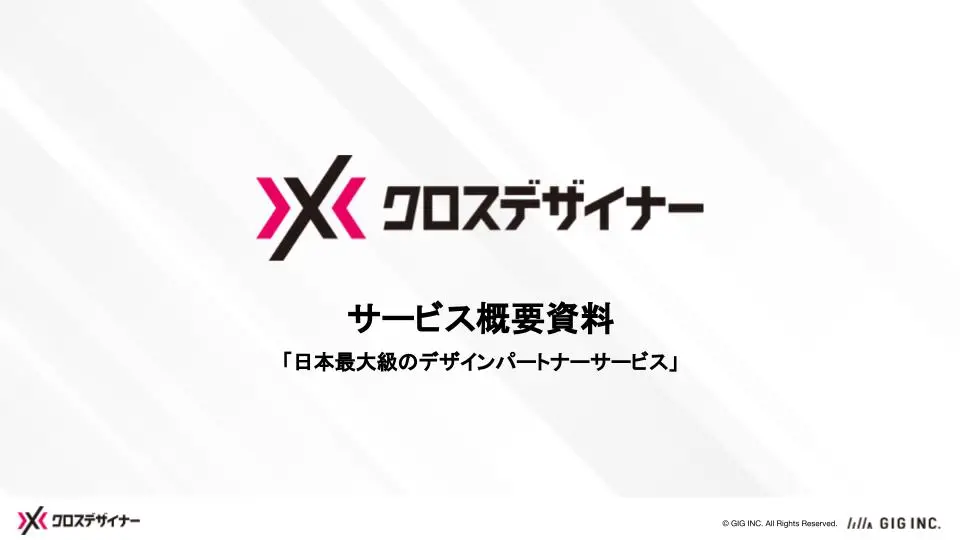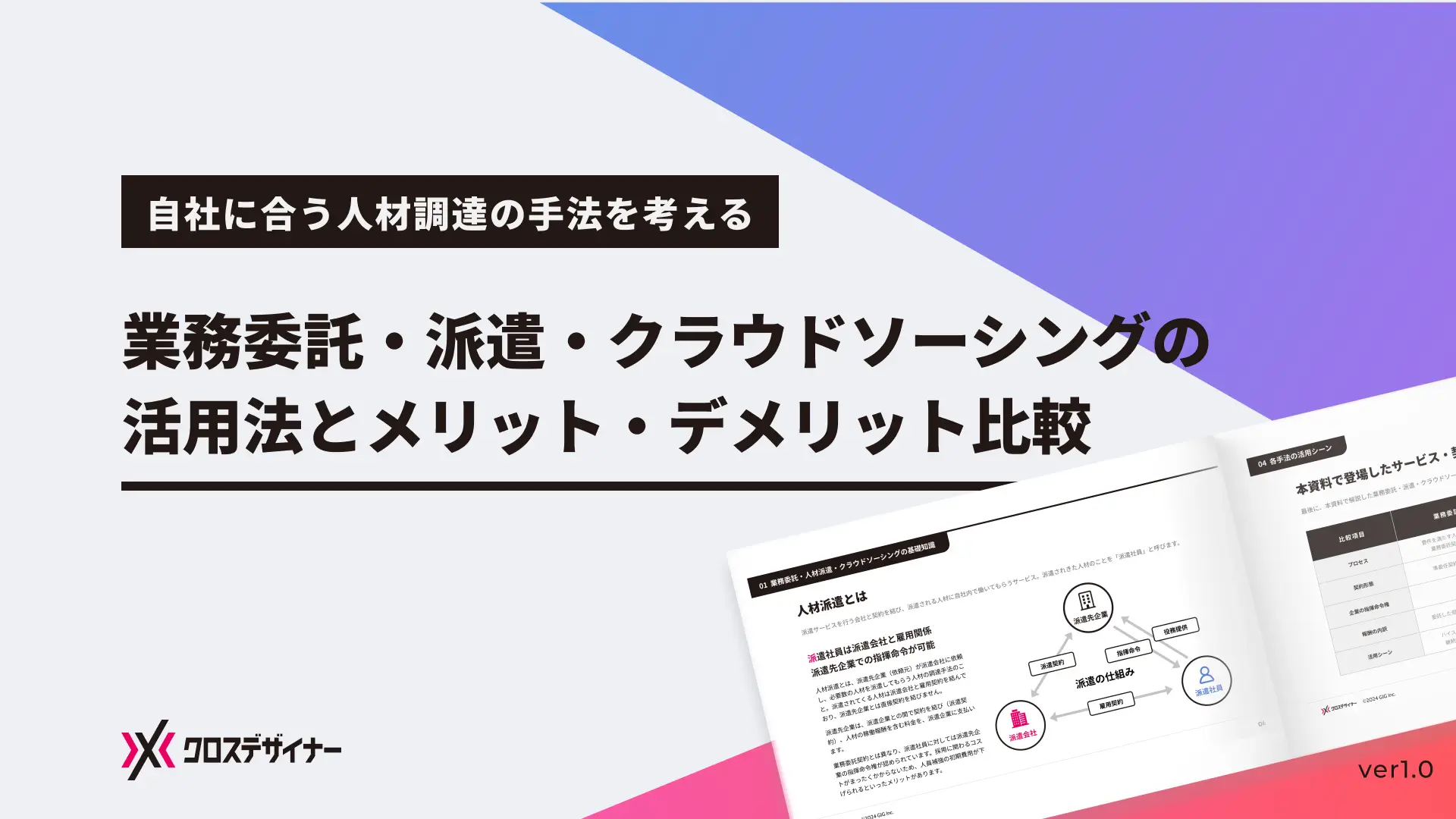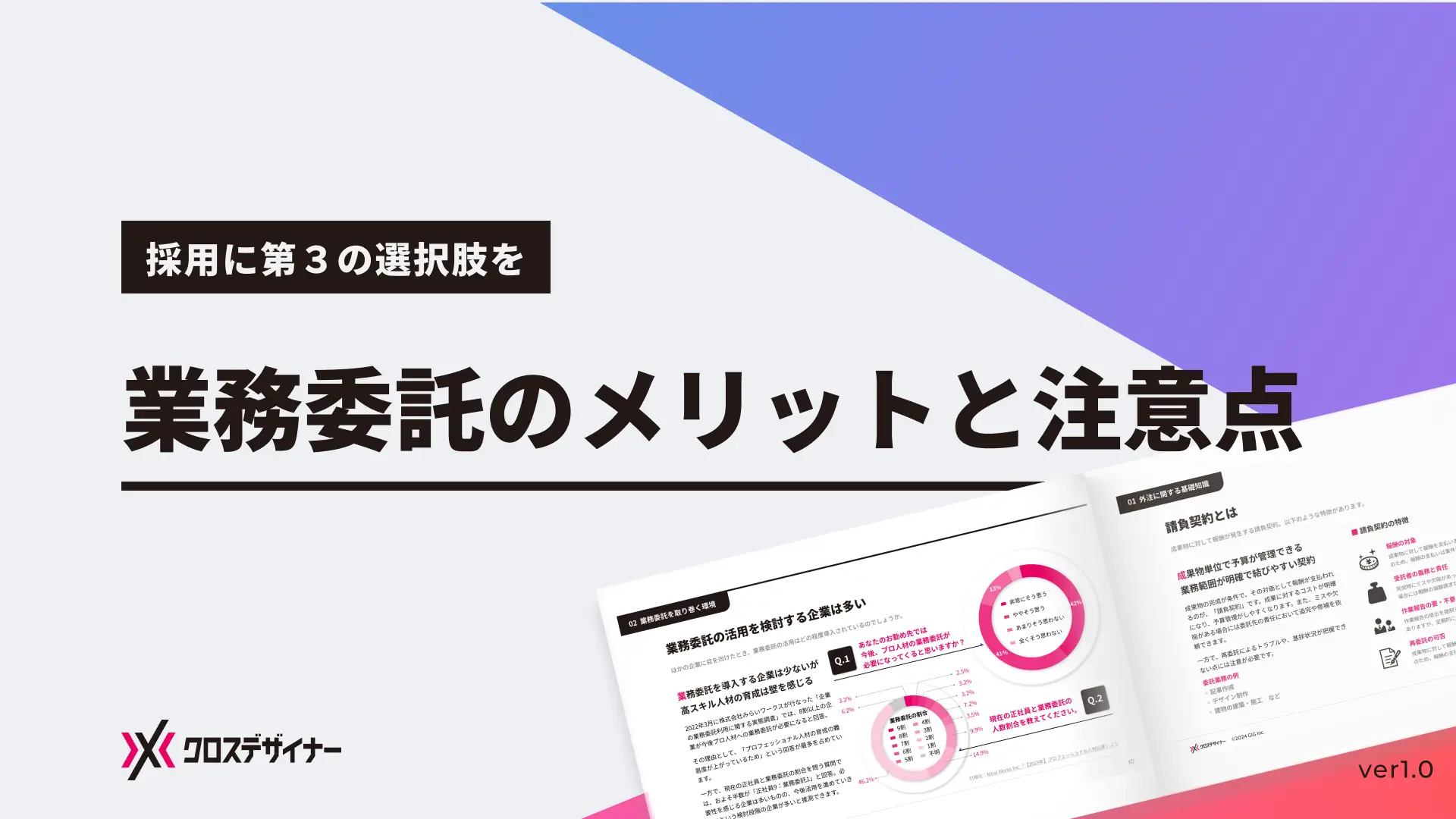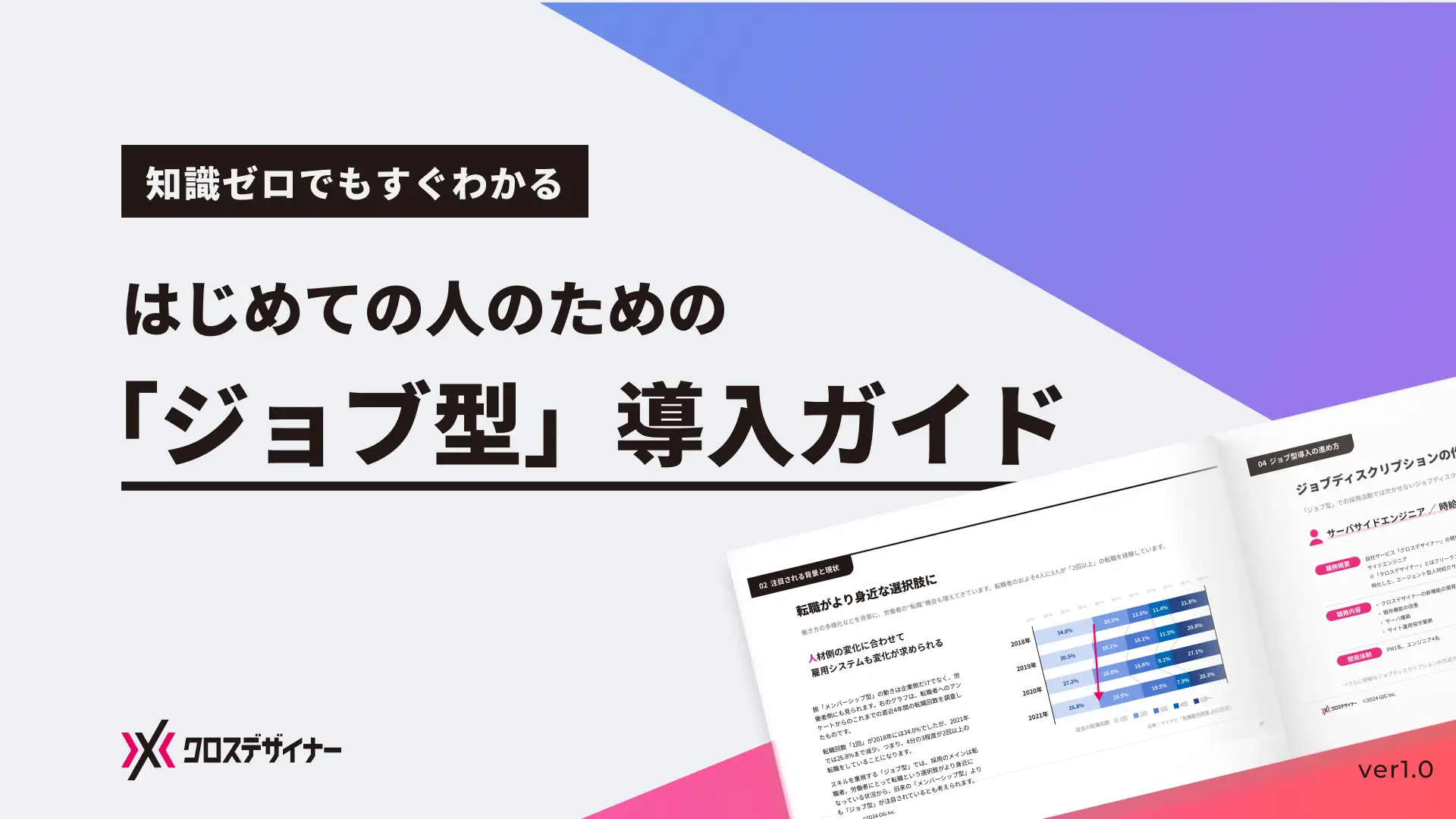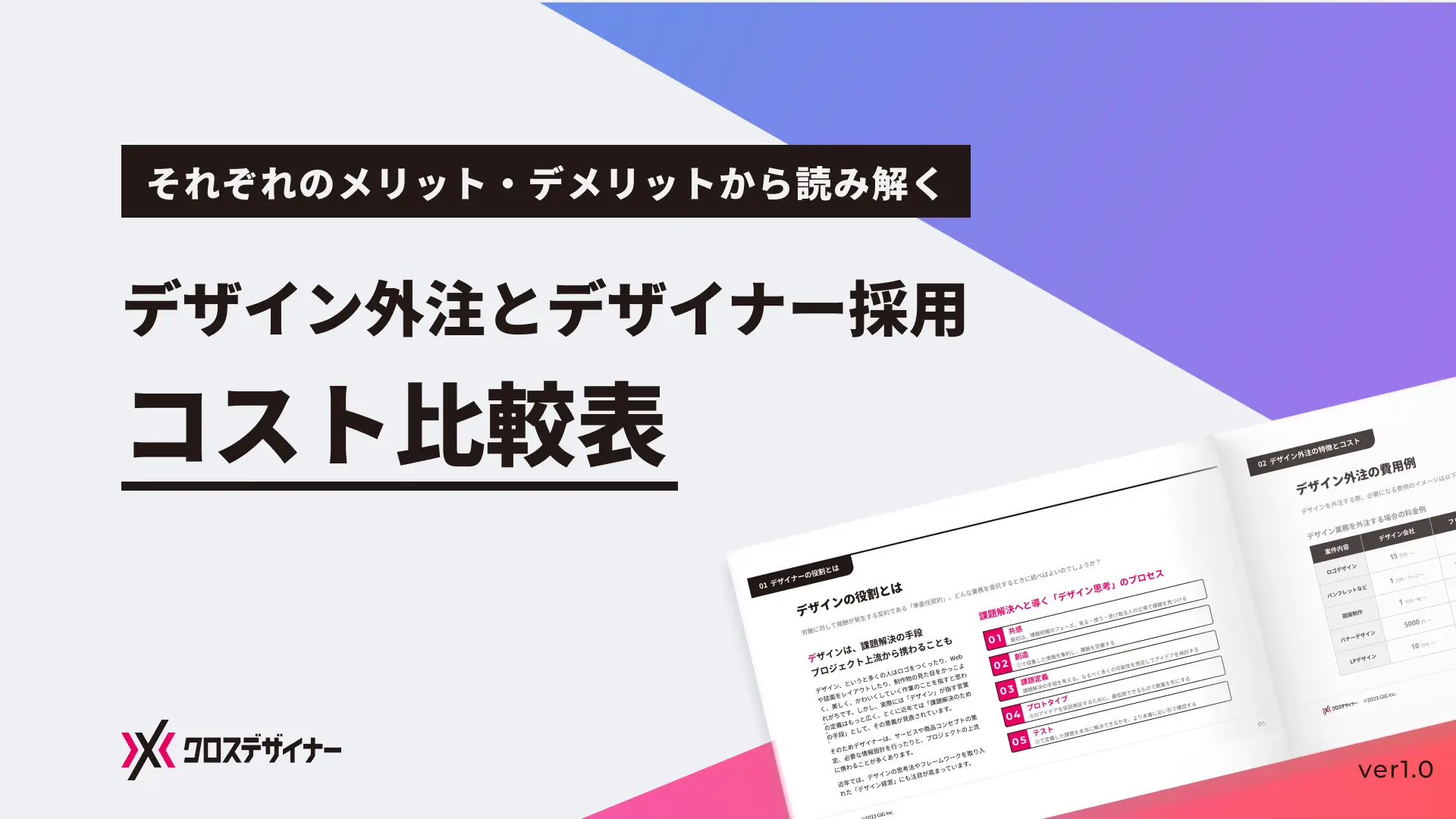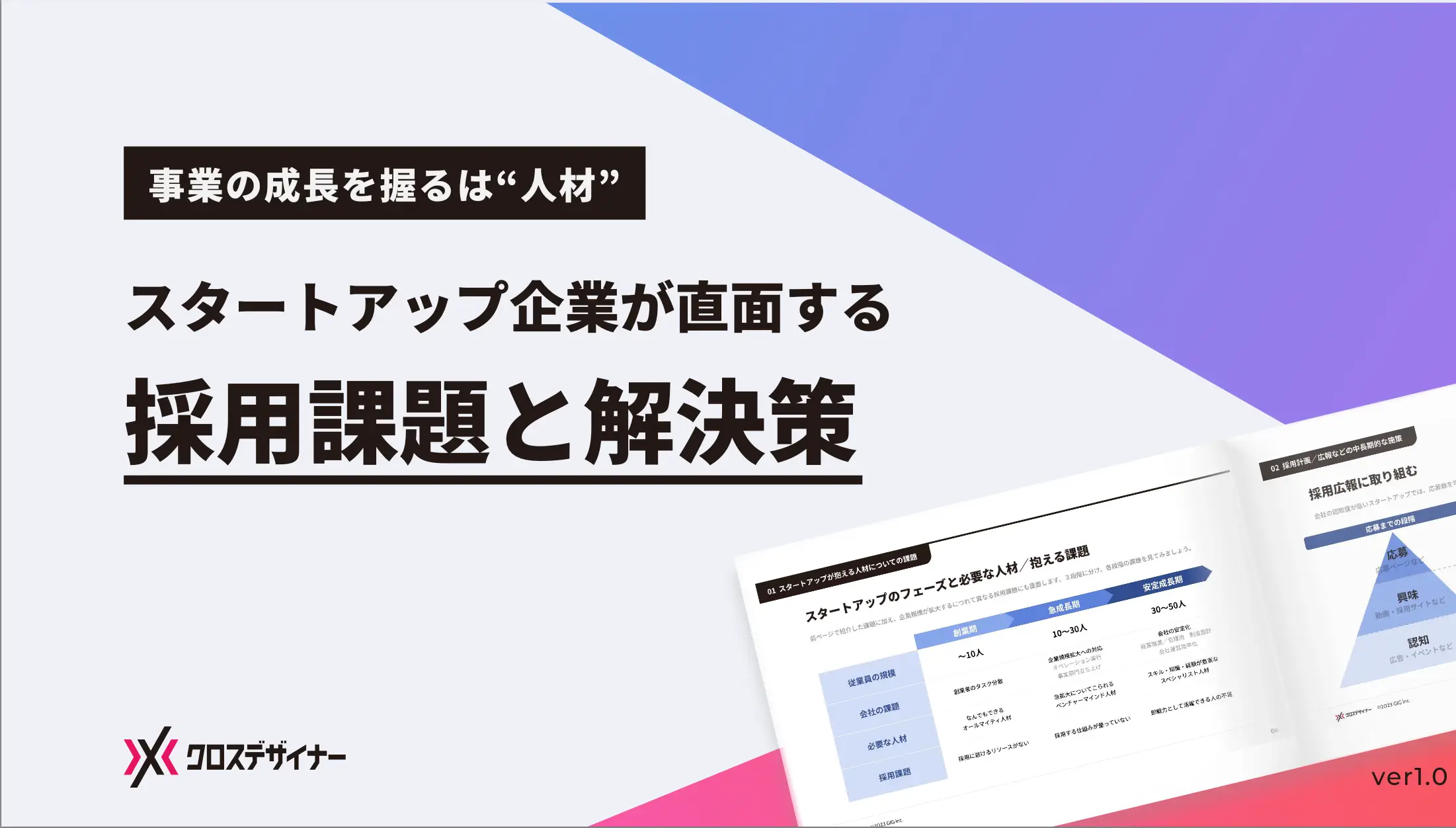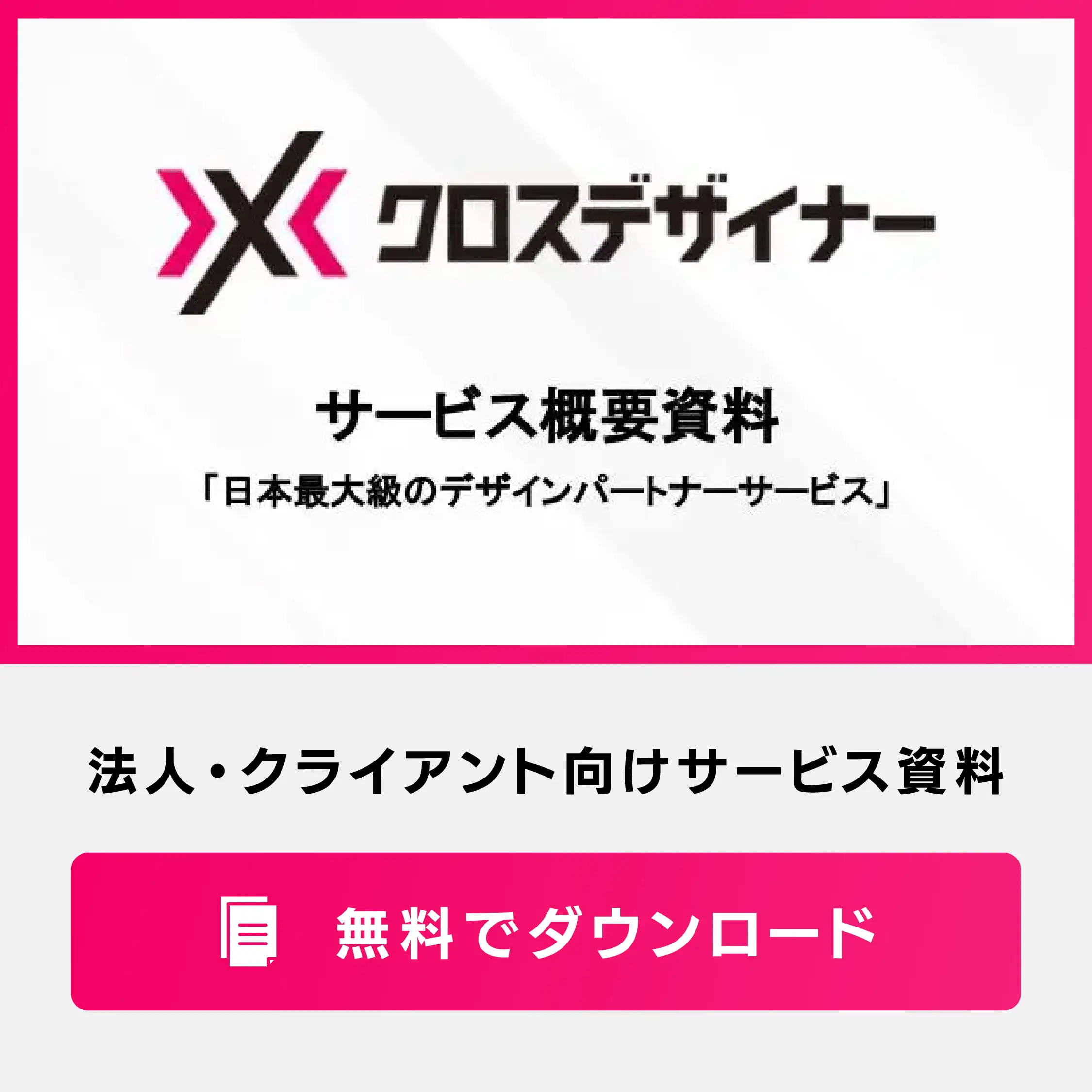業務委託とは、自社業務の一部、または全部を外注する方法で、請負契約・委任契約・準委任契約の3種類があります。
企業が業務委託をするときは、委託する業務の内容にあわせて適切な契約を結ぶことが大切です。とくに準委任契約は契約の性質上トラブルになりやすいため、各契約形態との違いや注意点を正しく理解しておかなければなりません。
そこで今回は、業務委託の準委任契約について、請負や委任契約との違い、メリットや注意点などを徹底解説します。これから準委任契約を締結しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
業務委託の準委任契約とは?基本的な概念を解説
業務委託契約とは、業務の一部を外部の企業やフリーランスなどに委託するときに結ぶ契約を指します。委託先とは主従関係や雇用関係はなく、同じ事業者として対等な関係で業務を進めます。
準委任契約とは、業務委託契約の一種で、特定の業務を第三者に委託する際に用いられる契約形態です。以下に基本的な概念を解説します。
準委任契約の特徴
準委任契約は、法律行為以外の業務を委託する契約で、成果物の完成を目的としない契約形態です。この契約形態は、業務の遂行自体に対価が支払われるため、柔軟な対応が可能であり、業務の進行状況に応じて報酬が発生するのが特徴です。
たとえば、ソフトウェアの保守やコンサルティング業務などが準委任契約に該当します。これらの業務では、特定の成果物の納品ではなく、継続的な業務遂行が求められます。
準委任契約は、業務の遂行に対して報酬が支払われるため、柔軟な対応が可能です。
関連記事:準委任契約とは?契約形態の違いと契約書の書き方について解説
下記の資料では、準委任契約と請負契約の比較や、実際に締結する際のポイントなどを網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご参照ください。

請負契約の特徴
請負契約とは、成果物を完成させることを目的とする契約です。たとえば、ロゴデザインやバナーデザインなど成果物が明確な業務が請負契約に該当します。
成果物が納品されたら、検収をしてから委託先に報酬を支払います。求める成果物を納品してもらうために、完成条件を事前に決めておくことが大切です。おもに、コンサルティング、システム保守などの業務に適しています。
関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説
委任契約の特徴
委任契約は、法律行為をおこなってもらうための契約です。おもに弁護士や税理士など、特定の資格をもつ専門家へ依頼する業務が対象のため、特定の成果物は求められません。
たとえば、裁判で弁護士を代理人として立てるときに、委任契約を結んで委託します。法律行為を遂行できるのは、士業など限られた職種のみなので、一般的な業務委託には適用されません。
法律行為以外の業務を委託するときは「準委任契約」を結びます。
関連記事:はじめての業務委託 成功のポイントと注意点を徹底解説
請負契約と委任契約、準委任契約はどう違う?
業務委託契約の3つの契約形態は、それぞれ目的や報酬の対象、指揮命令権の有無が異なります。それぞれの違いについて解説します。
準委任契約と委任契約の違いを比較
準委任契約と委任契約の主な違いは、委託される業務が「法律行為」か「事実行為」かにあります。
委任契約は、法律行為を委託する契約です。法律行為とは、法的な効果を生じる行為を指し、たとえば弁護士に訴訟代理を依頼したり、税理士に確定申告の手続きを依頼したりする場合などが該当します。
受託者には善管注意義務があり、依頼された業務を適切に遂行することが求められます。
一方、準委任契約は、法律行為以外の事実行為を委託する契約です。コンサルティング業務や調査業務、マーケティング調査などが事実行為に該当します。
準委任契約と請負契約の違いを比較
準委任契約と請負契約の主な違いは、請負契約が成果物の完成を目的とするのに対して、準委任契約は業務請負の業務の遂行を重視している点です。
請負契約では、特定の成果物の完成が目的のため、成果物が納品されてから報酬を支払います。準委任契約では完成させる責任はないため、未完成のまま納品されるケースがあるのです。
成果物の完成を求めるなら、一定の成果をおさめるために業務を遂行してもらう「成果完成型」がおすすめです。
下記の資料では、初めての方でも業務委託を安心して活用できるように、契約形態ごとの概要や特徴を、比較しやすい一覧表とともに解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

準委任契約が適しているケース
業務委託の準委任契約は、目的に応じた契約を選びやすいメリットがあります。ここでは、目的に合わせて適切な契約を選べるように、委託目的の事例を紹介します。
業務範囲が変動しやすい
業務内容が固定されず、進行に応じて変動するときは準委任契約が適しています。プロジェクトにあわせて業務範囲を調整しながら進められるため、仕様の変化にもスムーズに対応できるのです。
具体的には、以下のような業務が適しています。
- システムの運用・保守
- マーケティング戦略など支援業務
- 研究開発
これらの業務は遂行の段階で、追加業務が発生する可能性があります。そのため、準委任契約が適しているのです。
成果物なしで専門スキルを活用したい
業務遂行を重視し、成果物の完成が求められない場合、準委任契約が適しています。専門スキルを活かして、プロジェクトを進めてもらうのです。
- IT導入などのコンサルティング支援
- プロジェクトマネージャーとしての支援
- データ分析など専門家によるサポート
こうした特定のスキルや経験が求められる業務は、成果物が完成しなくても遂行のみで十分な価値があります。
外部の専門家にまかせたい
社内にリソースがなく、外部の専門家に業務を遂行してもらいたい場合にも準委任契約が適しています。プロのスキルをもって、最適な方法で業務を進めてもらうのです。
- ITサポート・ヘルプデスクの業務委託
- 外部人材による広告運用の最適化
- リスクマネジメント業務
ハイレベルのスキルが求められる業務や、こまかい指示を必要とせず、専門家の裁量で業務を進めることが求められるため、準委任契約が適しているのです。
長期的な支援を受けたい
単発案件や短期間のプロジェクトではなく、継続的な支援が必要な業務も準委任契約が適しています。たとえば以下のような業務があります。
- システム運用・保守サポート
- マーケティング戦略における長期支援
- 業務改善を目的としたサポート業務
IT関連の運用・保守業務の多くが業務内容の仕様変更に対応しやすい準委任契約です。
たとえば、Webサイト制作業務を委託する場合、Webデザインの要件定義や制作など業務の遂行そのものが重視される業務は準委任契約が適しています。しかし、Webデザインでもロゴやバナーのみデザインしてもらう場合、成果物が具体的なため請負契約が適しているわけです。
準委任契約と請負契約の活用事例を比較
以下では、準委任契約と請負契約の活用事例を比較します。
| 契約形態 | 主な活用事例 | 特徴 |
| 準委任契約 | ・ITシステムの運用・保守 ・サポートデスク業務 ・Webサイトの継続的な改良やコンテンツ更新 ・コンサルティング業務 ・バックオフィスの専門職(経理・労務等) ・顧問契約や技術指導、ヘルプデスク契約 | ・成果物の完成を必須とせず、業務遂行自体が契約履行となる ・工数や時間に応じて報酬が発生 ・仕様変更など柔軟な対応が可能 ・指揮監督権を委託者側が持つことが多い |
| 請負契約 | ・建設工事や製造業の製品開発 ・システムやプログラムの開発・納品 ・Webサイトやアプリの制作 ・コンテンツ制作(動画・デザイン等) ・業務委託による成果物納品 | ・成果物の完成・納品が報酬発生の条件 ・納期や仕様が明確 ・成果物に対する瑕疵担保責任が発生 ・仕様変更時は契約の再締結が必要 |
上記のように、準委任契約は、成果物の完成を求めず、業務の遂行自体に価値がある場合に適しています。たとえば、IT運用保守やコンサルティング、定期的なWebサイトの更新など、継続的・専門的な業務を外部に委託する際に多く用いられます。仕様変更や業務内容の調整が発生しやすい場合にも柔軟に対応できるのが特徴です。
一方、請負契約は、建設工事やシステム開発、Web制作など、成果物の完成が明確な業務に適しています。納品物の品質や納期が重視され、完成後に報酬が発生します。仕様変更時は契約内容の見直しが必要になるため、要件が明確なプロジェクトに向いています。
業務内容や目的に応じて、適切な契約形態を選択することが重要です。
準委任契約を結ぶ前の準備
業務委託で準委任契約の活用を決めたら、契約を結ぶ前にいくつか準備が必要です。事前にしっかりと準備をしておくことで、契約後のトラブルの発生を防ぐことができます。
受け入れ体制をつくる
まずは、委託側となる企業が業務を委託する体制を整えることが大切です。業務委託契約は雇用契約と異なる点が多いため、自社の従業員と同じように指揮命令はできません。以下のポイントを押さえて受け入れ体制をつくりましょう。
- 専任の担当者を決める
- 業務の進め方・連絡の取り方を決める
- 遂行に必要なツールを用意する
- 制作物の共有するための準備をする
委託先が誰と連絡を取ったらよいのか迷わないように窓口となる担当者を決めます。契約後は、定期的な進捗報告の機会を設けることも大切です。スムーズに業務を遂行できるように、ツールやアカウントの発行、共有フォルダを用意しておきましょう。
契約内容を明確にする
準委任契約は「業務の遂行」が目的ですが、どのような業務を遂行してもらうのか、具体的に契約内容を決めておく必要があります。
また、成果物の納品義務がない代わりに、納品目安の報告や進捗の報告など、最低限守ってほしいルールを決めておくことも大切です。納品をベースとした報酬設定ではないため、時間単価や月額固定など報酬の支払い条件も明確にしておくことが大切です。
正確な業務委託契約書を作成する
上記で決めた内容を契約書にまとめておくことも大切です。準委任契約の運用には、正確な業務委託契約書が欠かせません。もし、口頭で契約を交わした場合、トラブル発生時に適切な対応がむずかしくなります。
下記の資料では、業務委託に必要な契約書を作成する際のポイントについて網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約書の書き方と注意点【テンプレート付き】
業務委託で準委任契約を適切に運用するには、正確な契約書を作成しなければなりません。ここでは、業務委託契約書に記載すべき項目と注意してほしいポイントについて解説します。
業務内容・範囲の明確化
準委任契約では、委託する業務内容・作業範囲を明確にすることが大切です。たとえばWebサイト制作を委託する場合、デザインのみなのか、コーディングも含めるのか、修正は何回まで対応するのかを決めておく必要があります。
作業範囲があいまいなままだと「聞いていない」「ここまではできない」といったトラブルが起こる可能性があるため、注意が必要です。契約前に双方で共通の認識をもつために業務範囲を決めて合意しておくことが大切です。
求めるスキルを明確にしておくことで、業務遂行スキルを持つ人材の確保が可能です。ジョブディスクリプションを作成して理想の委託先を見つけましょう。以下より作成ガイドを無料でダウンロードいただけます。

報酬・委託料の決め方
準委任契約の場合、報酬の算出方法や支払い条件を明確に決めておくことが大切です。ただし、業務遂行が目的のため、業務内容によって報酬の決め方は異なります。
たとえばWebデザイン業務の場合、Webページ1枚あたりの単価や作業時間に応じた時間単価、プロジェクト単位といった決め方があります。
どのように報酬が決まり、どのタイミングで支払われるのかも記載しておくと、委託先も安心して受けることができるでしょう。
関連記事:業務委託に最低賃金は適用される?報酬相場やコスト削減のコツを解説
契約期間・更新条件
業務委託契約では、いつまでの契約なのか期間を明示しておくことが大切です。継続の可能性がある場合は、更新条件を設けておくとトラブルを防ぐことができます。
たとえばWebデザインの業務委託をする場合、「1か月ごとに更新」や「1年契約」など決めておきましょう。契約期間を決めない場合、プロジェクトの進行状況によってはトラブルになる可能性もあります。自動更新の有無や契約終了のタイミングなども記載しておくことが大切です。
成果物の権利・知的財産権
業務委託契約では、成果物によって権利問題がトラブルになることがあります。デザイン業務の場合、成果物の権利が誰に帰属するのかを明記しておくことが大切です。
業務の遂行中に生じた成果物やアイデアの知的財産権が誰に帰属するかを明確にすることで、後々の権利関係のトラブルを防げます。契約書に知的財産権の帰属や使用条件を詳細に記載し、双方の合意を得ることが重要です。
とくに商標登録が絡むデザインや、二次利用をしたい場合、権利の範囲を具体的に決めておく必要があります。
関連記事:デザイナーとの業務委託契約書で注意すべき点とは? 必須の記載事項も解説
契約解除・中途解約の条件
業務委託契約では、プロジェクトの途中で契約が終了するケースもあります。たとえばWebサイト制作の場合、デザイン制作まで完了しているものの、コーディングに入るまでに何かしらの事情があり、契約を終了したいときです。
こうした場合、どこまでの作業を報酬の対象とするのかを契約書で決めておく必要があります。契約解除のタイミングは、どちらかが不利になる可能性もあるため、双方で確認をして合意を取ることが大切です。
関連記事:準委任契約の中途解約とは?トラブルを予防・解決する方法を解説
禁止事項・競業避止義務
業務委託契約で機密情報を扱う業務を委託するケースもあるでしょう。委託先が機密情報を第三者に開示する可能性を想定して、契約書に禁止事項として盛り込むことが大切です。
また、競業避止義務を設定する場合、委託先の業務に支障をきたす場合もあります。「契約終了後は〇年間は同業他社とは契約できない」といった期間を設けることを検討してください。
再委託の可否
準委任契約の場合、委託先のスキルをもって業務を遂行してもらうため、基本的に再委託は認められていません。しかし、規模が大きめのWebサイト制作や、委託先ではリソース不足の場合、再委託によりスキルを確保し、プロジェクトを進めることが可能です。
再委託を認めるときは、成果物の品質や情報漏洩のリスクを踏まえて、再委託の条件をこまかく決めておくことが大切です。
損害賠償責任
準委任契約の場合、請負契約のような契約不適合責任は適用されません。その代わり善管注意義務があり、義務を怠った場合に債務不履行を追及することができます。
債務不履行が発生した場合、企業は損害賠償請求が可能です。しかし、可能なかぎりこうした事態は避けたいものです。プロジェクトをスムーズに進めるためにも契約前に適切な人選をおこなうことで、トラブルを防ぐことができます。
関連記事:業務委託契約を締結する際に起こりがちなトラブル事例6つと対処法を解説
その他
業務委託契約書に記載する内容は、法律で義務付けられていません。そのため、委託する業務にあわせてさまざまな事項を定めることができます。
トラブルが起きたときの解決手段なども記載しておくことで、法的な効力をもたせることが可能です。また、長期にわたるプロジェクトの場合、認識がずれてしまうこともあります。契約書を作成しておくことで、共通の認識をもつことが可能です。
下記の資料では、業務委託に必要な4種類の契約書について、すぐに使えるテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

業務委託でエージェントを活用するメリット
業務委託を活用するときは、契約形態の性質の理解や準備、労務管理、関係法令の理解などさまざまな課題があります。
通常の業務を進めながら、業務委託の受け入れ体制をつくるにはエージェントの活用がおすすめです。ここでは、業務委託契約にエージェントを活用するメリットについて解説します。
契約の準備からサポートを受けられる
業務委託契約では、業務範囲や報酬の設定など契約書を作成するためにさまざまな項目を決めておく必要があります。
エージェントを活用することで、契約準備の段階から締結までスムーズに進めることが可能です。企業と求職者の双方の要望を聞いて、納得のいく条件で適切な契約書を作成してくれます。
法的なリスクを抑えることができるため、担当者にとっても大きな負担軽減となるでしょう。
関連記事:人材紹介エージェントから受けられるフォローとは?稼働前後の内容をそれぞれ紹介
三者間契約で偽装請負のリスクを回避
業務委託では、企業が委託先に直接指示を出しすぎると「偽装請負」とみなされる可能性があります。とくに制作工程が複雑なデザイン業務の場合、こまかい指示を出したり、スケジュールを厳しく管理したりするとリスクが高まります。
しかし、プロジェクトを進めるにあたり、指示を出したいときもあるはずです。エージェントを介した三者間契約を結ぶことで、企業が指揮命令をしなくても、適正に業務を進めてもらうことが可能です。
関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説
労務管理を依頼できる
業務委託契約では、企業と委託先は雇用関係にありません。基本的に労務管理の責任は発生しませんが、稼働状況の把握や報酬の支払いスケジュールなどの管理は必要です。
エージェントを活用することで、進行状況や報酬の支払いを適正に管理できるため、負担軽減につながります。自社である程度把握したい場合には、以下の資料が役立ちます。無料でダウンロードが可能です。

デザイン業務の外注は『クロスデザイナー』におまかせください
クロスデザイナー(XDesigner)は、フリーランスデザイナーを専門に取り扱うエージェントサービスです。クロスデザイナーが優秀なフリーランスへの業務委託に適している理由には、以下のようなものが挙げられます。
- 豊富なデザイナー登録者数
- 業界最速級の提案スピード
- 柔軟なアサインが可能
- 専門的なサポートが受けられる
- 質の高いデザイナーのみが登録されている
それぞれ解説します。
1.豊富なデザイナー登録者数
クロスデザイナーには、経験豊富で優秀なデザイナーが7,000人以上登録されています。企業は自社のニーズに合ったデザイナーを迅速に見つけることができ、幅広いプロジェクトに対応可能です。
2.業界最速級の提案スピード
クロスデザイナーは、業界最速級の提案スピードを誇ります。依頼を受けてから迅速に適切なデザイナーを提案するため、プロジェクトの開始がスムーズに行えます。
3.柔軟なアサインが可能
クロスデザイナーでは、プロジェクトの進行状況やニーズに応じて、柔軟にデザイナーをアサインすることができます。急な変更や追加のリクエストにも対応できるため、プロジェクトの成功率が高まります。
4.専門的なサポートが受けられる
クロスデザイナーは、デザイナーだけでなく、プロジェクトマネージャーやコンサルタントなどの専門家によるサポートも提供しています。これにより、プロジェクト全体の品質を高め、円滑な進行を支援します。
5.質の高いデザイナーのみが登録されている
クロスデザイナーには、通過率約5%という厳しい選考をクリアした、質の高いデザイナーのみが登録されています。これにより、企業は安心して業務を委託でき、高品質な成果物を期待できます。デザイナーのスキルや経験が保証されているため、信頼性が高いです。
下記の資料からは、実際に登録しているデザイナーのスキルや得意分野などをご確認いただけます。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
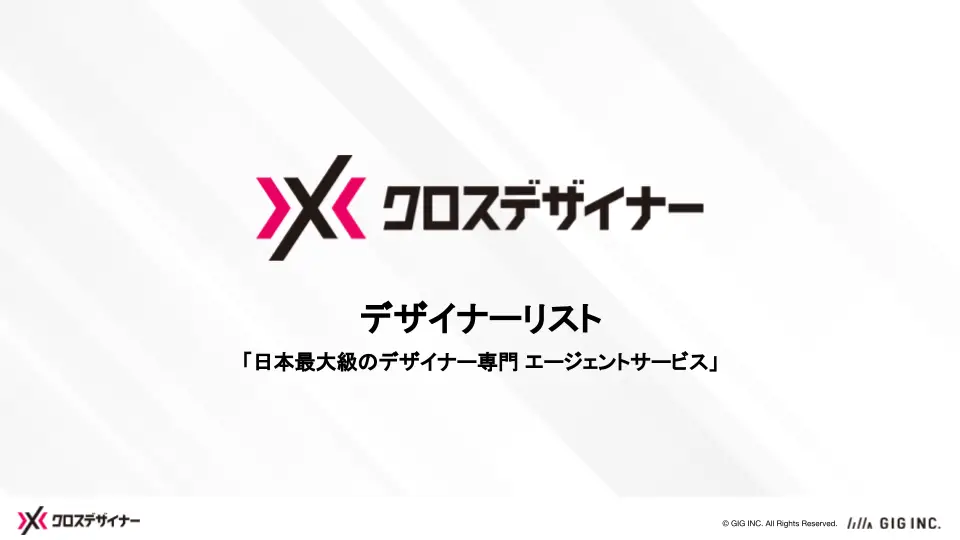
国内最大級のデザイナー専門のエージェントサービスである、クロスデザイナーには、厳正な審査を通過したハイスキルなデザイナー7000人以上が在籍しており、自社に合うデザイナーを見つけることができます。また、制作開始後も担当のコンサルタントがさまざまなトラブルや困りごとにも間に入って対応してくれるため、安心です。
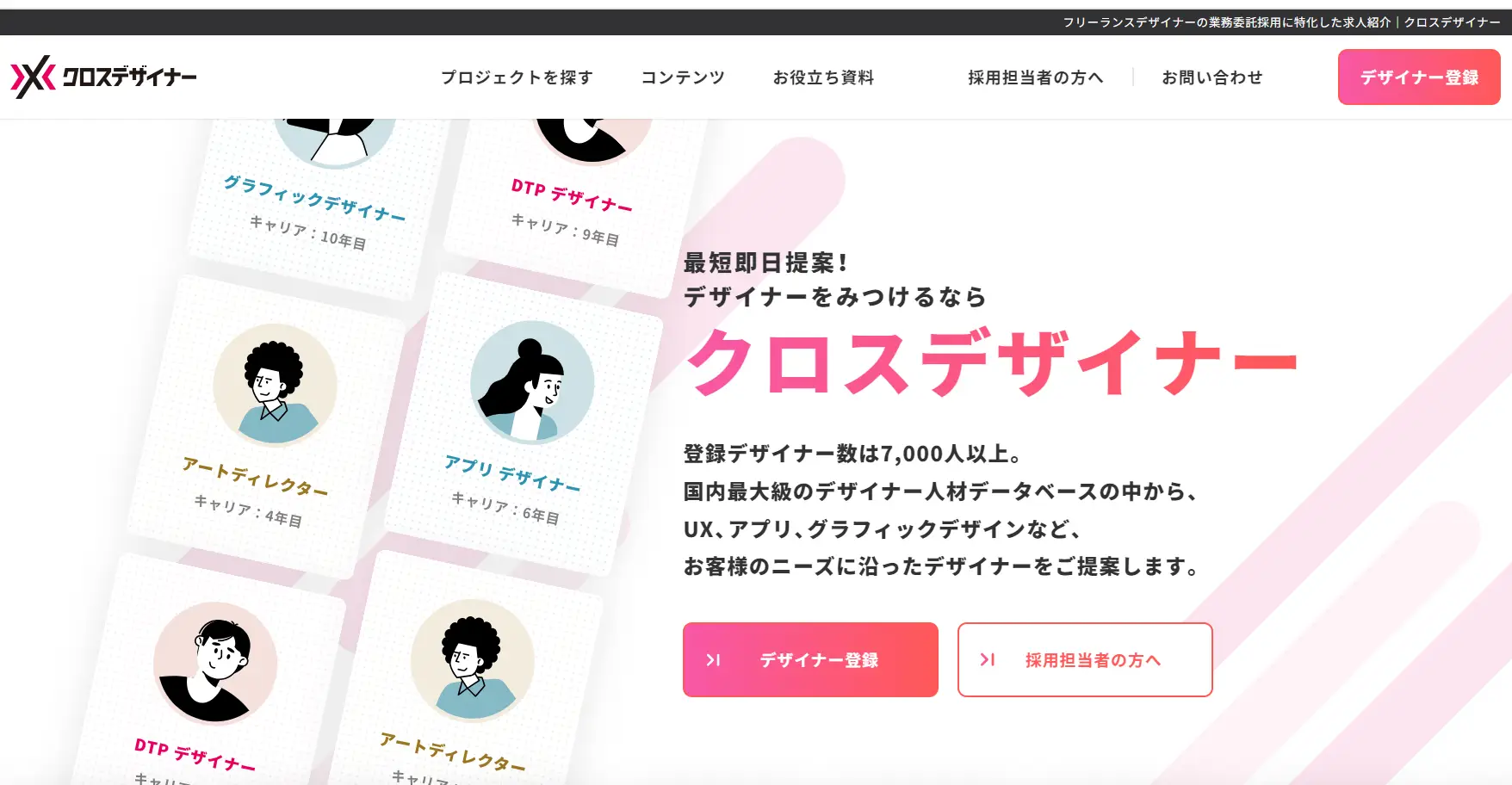
さらに、登録しているデザイナーと合意があれば正社員採用もできます。スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い、即戦力デザイナーの採用機会を最大限サポートしています。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の柔軟な依頼も可能なので、自社の作業量に応じて効率的に外注することが可能です。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

Workship MAGAZINE編集部。フリーランス、マーケティング、会計経理、経営分野が専門。個人事業主としてスポーツインストラクター、飲食店経営、飲食コンサルを経て、現在はコンテンツ制作会社を経営中。
Documents