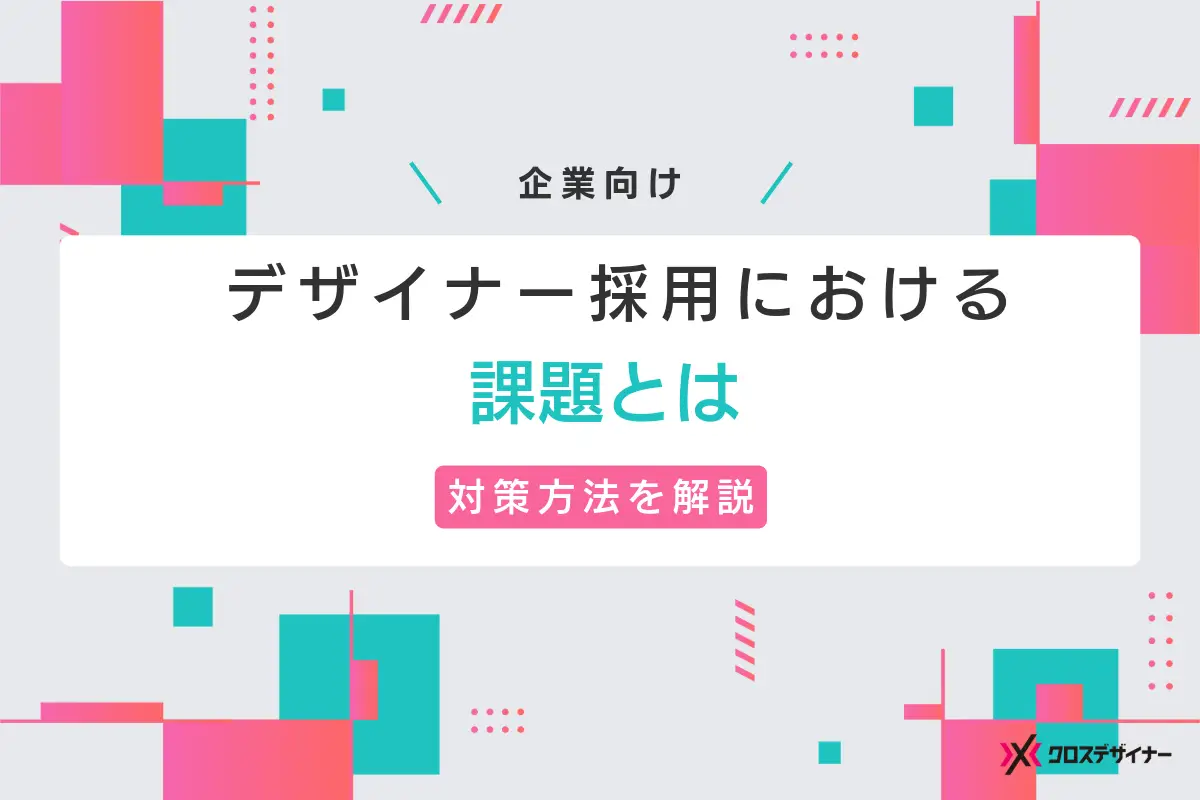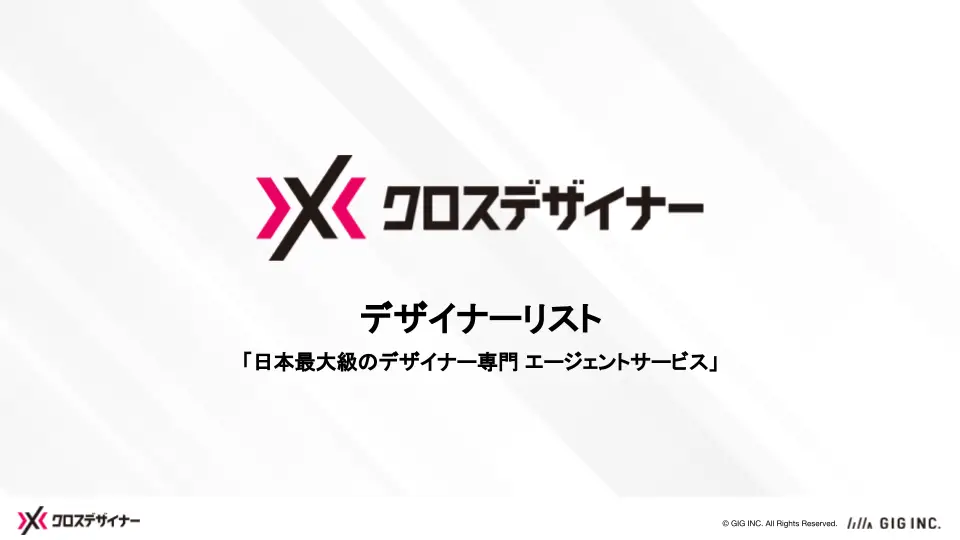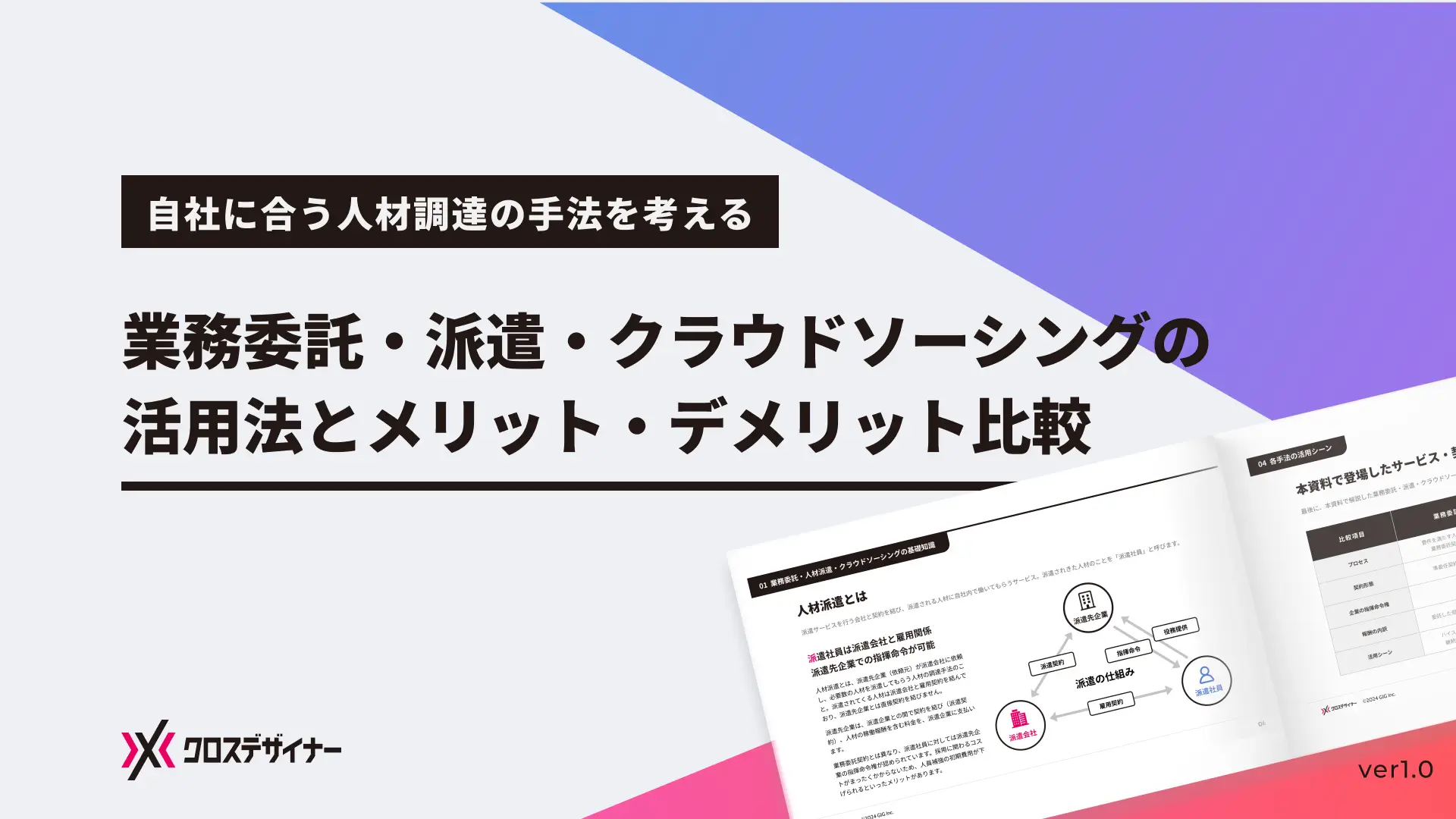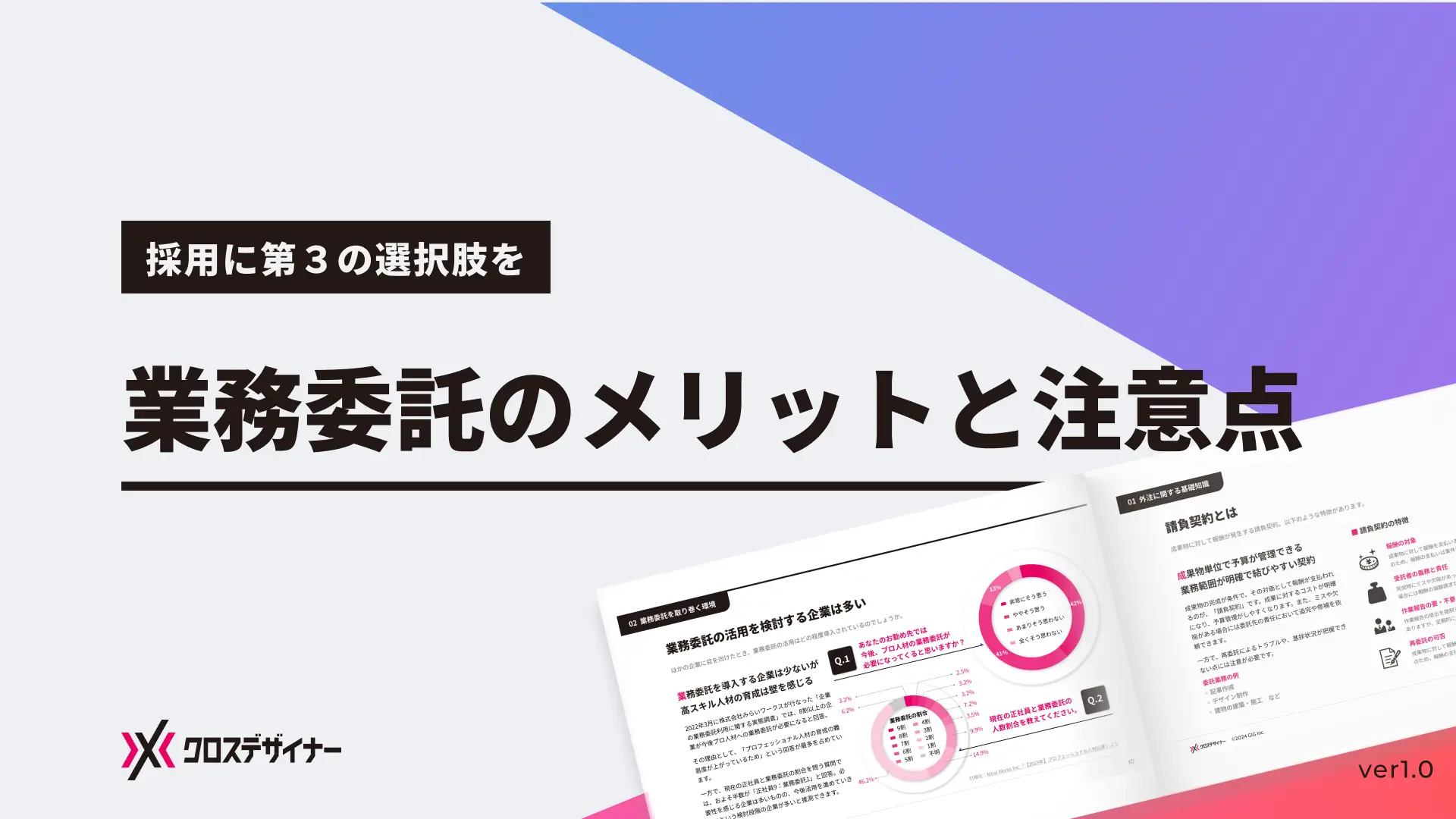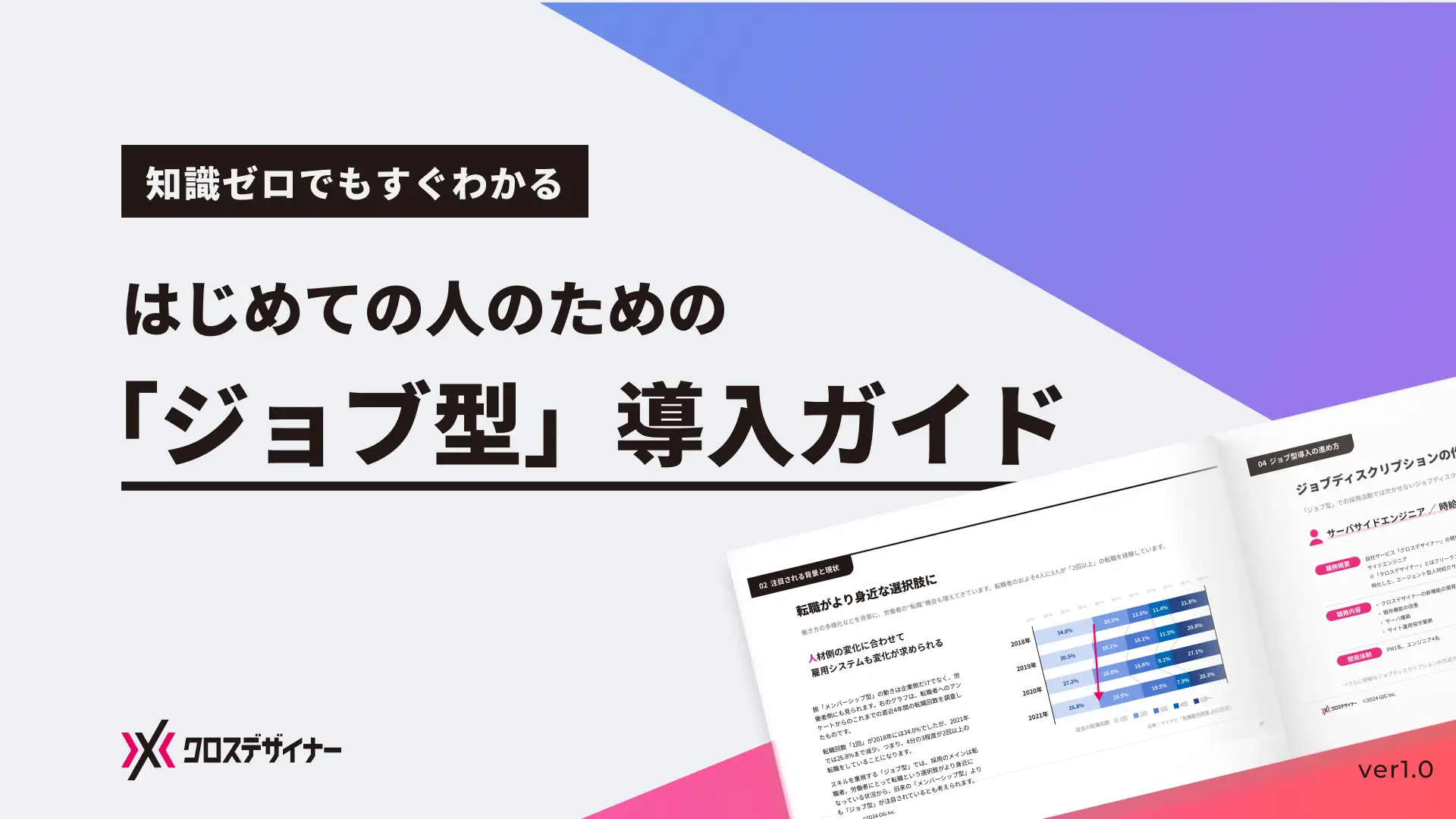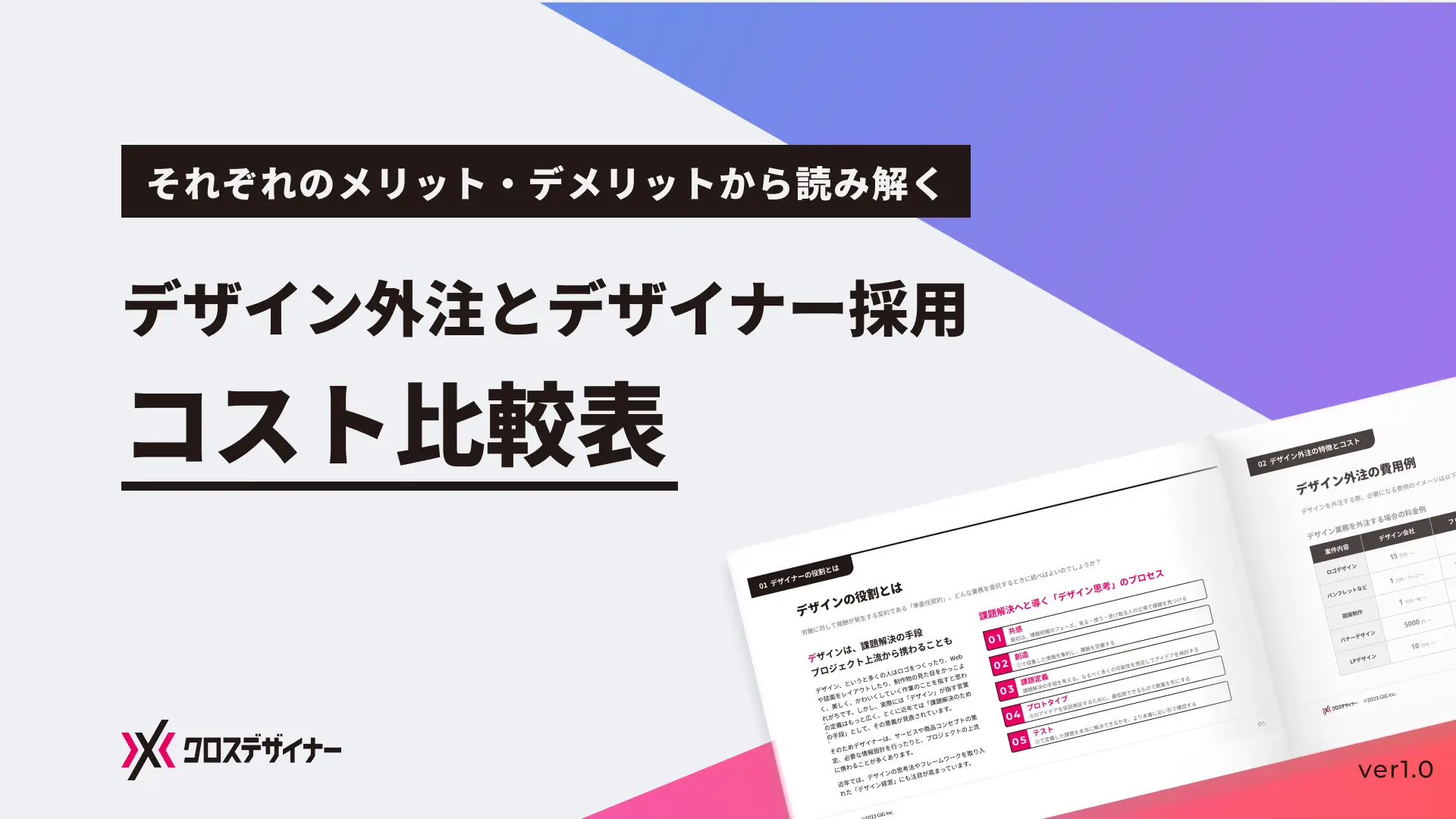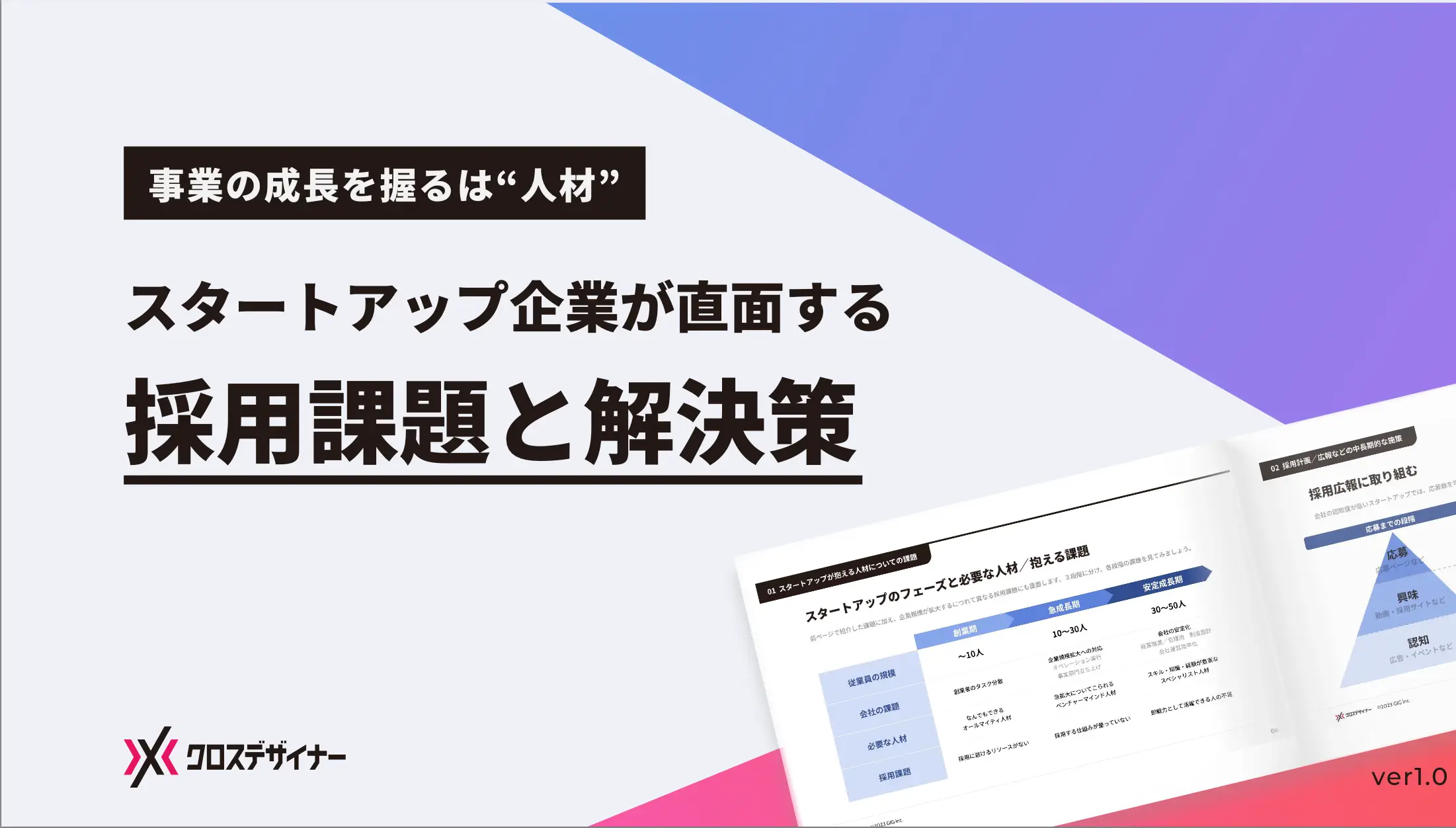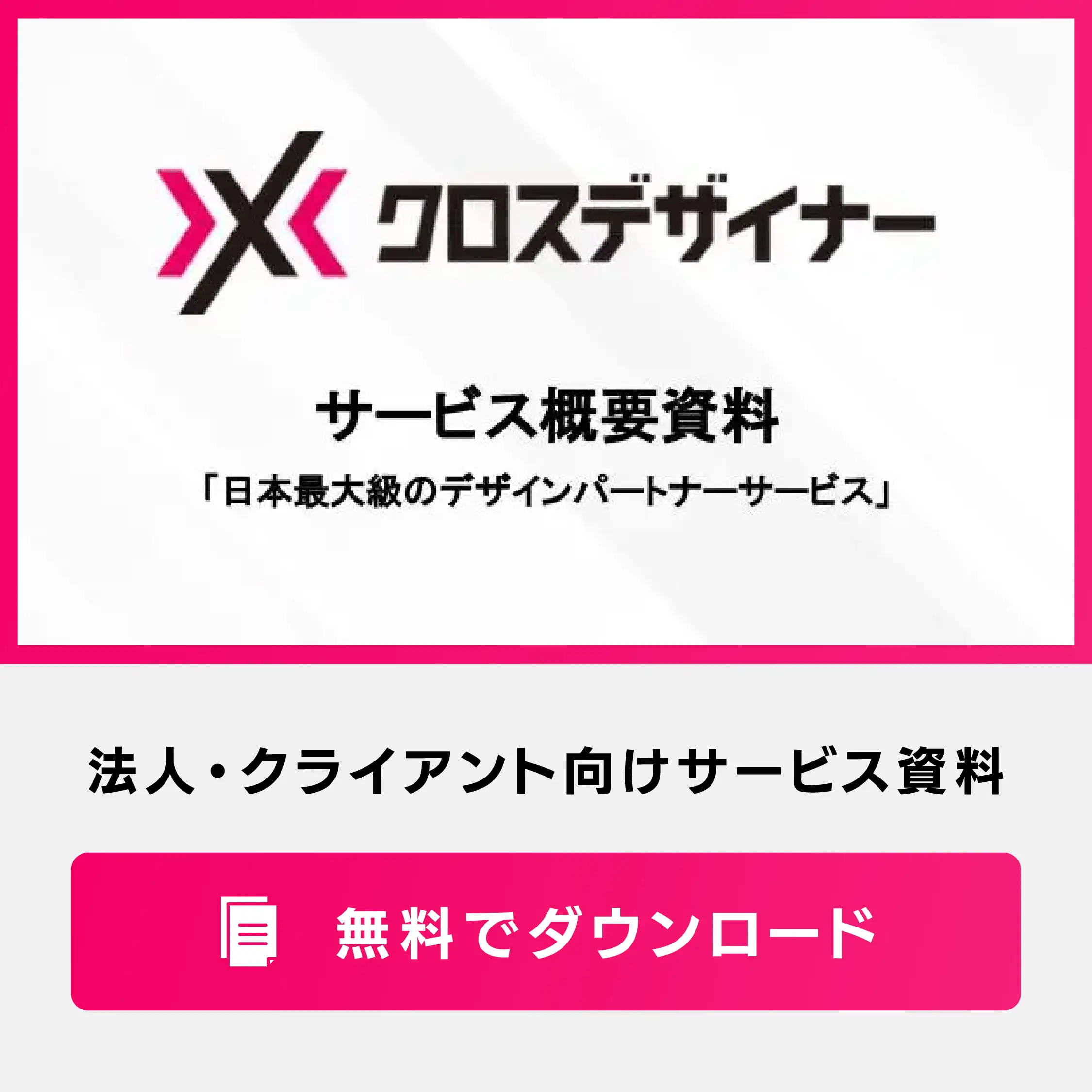業務委託契約における源泉徴収は、報酬の支払い時に企業が税額を天引きし納付する重要な手続きです。
企業においては、源泉徴収の対象となるケースや税額計算のルールを理解していないと、税務上のトラブルにつながる可能性があります。
正確な計算方法と適切な対応を知ることで、安心して業務委託を活用できるでしょう。
そこで今回は、業務委託に源泉徴収が必要となるケースや税額の計算方法を企業向けに解説しますので、ぜひ参考にしてください。
業務委託に源泉徴収は必要か
業務委託とは業務の一部を社外の人材へ委託するものです。契約を結ぶ相手や委託する業務によっては源泉徴収を行わなければなりません。
業務委託契約とは
そもそも業務委託契約とは、個人事業主やフリーランスと契約を結んで業務の一部を委託する方法です。請負契約・準委任契約・委任契約があり、それぞれ以下のように報酬が発生する対象などが異なります。
業務委託契約の種類 | 報酬の対象 | おもな職種 |
請負契約 | 成果物の納品 | デザイナー、ライターなど |
準委任契約 | 業務を遂行した業務 | ITエンジニア、コンサルタントなど |
委任契約 | 法律行為 | 弁護士、司法書士など |
関連記事:外注費の勘定科目は?源泉徴収や消費税などの仕訳例も解説
業務委託契約については無料配布資料「はじめての業務委託採用」で解説しています。下記より無料でダウンロードいただけますのでお役立てください。

源泉徴収制度とは
源泉徴収制度は、給与や報酬を支払うときに支払者が所得税として一定額を徴収して、自治体へ納付する納税制度です。納付額の調整は給与所得者は年末調整、給与所得者以外は確定申告で正しい所得額を申告します。
給与や報酬の支払者は「源泉徴収義務者」と呼ばれ、法人以外に学校や官公庁、個人でも該当します。
源泉徴収税と所得税の違い
所得税は年間所得に応じて課せられる税金です。源泉徴収税は報酬・給与額をもとに計算した所得税を徴収し納税します。それぞれ計算の対象となる金額が異なるため、納税額に差が生じます。
給与所得者が11月末ごろから行う年末調整は、この誤差を調整するための手続きです。業務委託の場合、確定申告で正しい所得額を申告します。
所得が年間48万円以下なら所得税はかかりません。年間所得が48万以下の場合、源泉徴収された金額は納税者に還付されます。
源泉徴収をしないとどうなる?
もし源泉徴収を差し引き忘れたときは、次回の報酬から源泉徴収税分を差し引く形で対応が必要です。
源泉徴収義務があるのにやらない場合、所得税法第240条・第242条の規定にもとづいて「10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」が科せられます。
「請求書に記載がなかったのに?」と思われるかもしれませんが、源泉徴収義務があるのは報酬の支払者です。請求書に源泉徴収税額の記載がなくても、個人と業務委託契約を結んでいるなら源泉徴収の義務があります。対象業務を委託しているなら、必ず源泉徴収を行わなければなりません。
関連記事:業務委託に確定申告や源泉徴収は必要なし?委託と受託、双方の視点から解説
源泉徴収の対象範囲と不要なケース
業務委託の源泉徴収は取引先が個人なら必須です。ただし、委託する業務内容でも対応は異なるため、何を委託するのか明確にしておくことが大切です。
個人との業務委託契約
業務委託契約を個人と結ぶときは、所得税法204条で定められた業務や取引が源泉徴収の対象です。
- 原稿料や講演料等
- 弁護士や公認会計士・司法書士等の特定の資格をもつ人などに支払う報酬等
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、モデルや外交員等に支払う報酬等
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬等
- ホステス等に支払う報酬等
- プロ野球選手の契約金等、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(参考:国税庁 第5 報酬・料金等の源泉徴収事務)
「原稿料や講演料」にはWebデザインやコンテンツライティング、翻訳、通訳などの業務が含まれています。取引内容だけではなく、こまかい業務内容も確認が必要です。
業務委託契約で宿泊費や交通費がかかる業務を請け負う場合、企業側が旅館やホテル側に直接支払っていれば源泉徴収は不要です。ただし受注者に支払うときは源泉徴収の対象になります。誰に支払うのかを基準に考えるとわかりやすいでしょう。
法人との業務委託契約
法人との業務委託契約では、原則として源泉徴収は不要です。ただし、国内法人との取引で馬主(法人)に競馬の賞金を支払うときだけ源泉徴収しなければなりません。
業務委託を検討しているところが、法人か個人かわからないときは取引先に確認をしてください。わからなかったからといって源泉徴収をしないと罰則を科せられてしまいます。
関連記事:デザイナーに支払う報酬に源泉徴収が必要となるケースや計算方法を解説
源泉徴収税額の計算方法
源泉徴収税額は、会計ソフトなどを使用していると自動で算出してくれますが、計算方法を覚えておくとミスにも気が付きやすくなります。
業務委託契約は原則消費税込みで計算
業務委託の報酬に対する源泉徴収税額は原則、消費税込みの金額で計算します。しかし、必ずしも税込処理と決まってはいません。請求書で報酬額と消費税額が区別されていれば、消費税を含めずに報酬額のみで計算をします。
「納税額が異なるのでは?」と不安に思うかもしれませんが、税込・税抜の処理方法で異なるのは入金額です。業務委託先は確定申告をすることで正しい所得税を納税しています。結果的に手元に残る金額に差はないため、問題はありません。
支払金額別の源泉所得税の計算例
源泉徴収税額の計算方法は、支払金額が100万円以下と100万円超で計算方法が異なります。
支払金額(A) | 税額 |
100万円以下 | (A)×10.21% |
100万円超 | (Aー100万円)×20.42%+102,000円 |
委託業務がデザイン制作だったときに、報酬50万円と120万円のそれぞれの源泉徴収税を計算してみました。
<50万円の報酬を支払う場合>
50万円 × 10.21% =源泉徴収税額51,050円
<120万円の報酬を支払う場合>
(120万円 - 100万円)× 20.42% + 102,000円 =源泉徴収税額142,840円
復興特別所得税とは
復興特別所得税は、東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための税金です。2013年1月1日から2037年12月31日までの間、源泉徴収義務者は納税者の基準所得額より2.1%相当額を徴収しなければなりません。
源泉徴収税率 10.21% | |
所得税率 10% | 復興特別所得税率 0.21% |
基準所得額が100万円未満で所得税率が10%の場合、復興特別所得税率は「10%×2.1%=0.21%」となるため、あわせて10.21%を使用して納付額を求めます。
消費税は請求書の記載方法で異なる
業務委託先には源泉徴収義務がないため、源泉徴収税額が記載されていない請求書が発行されるケースも少なくありません。そもそも請求書の源泉徴収税額欄は義務ではないため、ないときは企業側で計算をして納付してください。
業務委託の源泉徴収税の納付方法
業務委託契約の源泉徴収税を納めるときは「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使用します。おもに請負契約や準委任契約時に使用するもので、法律行為を依頼する委任契約の報酬について源泉徴収するときは「給与所得・退職所得等の納付書」を使用します。
支払う報酬には区分コードが設けられているため、国税庁のホームページで確認してください。
国税庁 納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収計算書)
源泉徴収税の納付期限・納付先
厳選徴収税は報酬支払月の翌月10日の納付期限までに、納税地の所轄税務署に納付します。
納付方法は金融機関や税務署窓口のほか、e-Taxやインターネットバンキングなどキャッシュレスで納付が可能です。インターネット環境があれば税務署閉庁後も納税できます。
手続方法 | 概要 |
ダイレクト納付 | e-Taxで預貯金口座より振替納付 |
インターネットバンキング(登録方式) | インターネットバンキングから納付 |
インターネットバンキング(入力方式) | ATMで電子納税 |
クレジットカード納付 | 「国税クレジットカードお支払サイト」から納付 |
スマホアプリ納付 | |
コンビニ納付(QRコード) | QRコードをコンビニエンスストアに持参して納付 |
(参考:国税電子申告・納税しステム e-Tax 電子納税)
ただし、電子納税の場合、領収証書は発行されないため、必要な方はスクリーンショットをとっておいてください。
常時雇用10名以下で納期の特例が適用
源泉徴収税は通常、報酬を支払った翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、常時雇用者が10名以下の場合、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、以下のように年2回に分けて納付が可能です。
- 1月~6月分:7月10日までに納付
- 7月~12月分:1月20日までに納付
年度途中でも申請できますが、原則として給与を支払う人数が常時10人未満であることが条件です。
業務委託人材や一時的な雇用者は含まれないので注意してください。
業務委託の源泉徴収でよく聞かれるトラブルQ&A5選
以下では、業務委託の源泉徴収でよくある企業側のトラブルについて解説します。
Q1.源泉徴収の対象かどうか判断できない
A1:業務委託契約では、報酬の種類によって源泉徴収の対象かどうかが異なります。例えば、デザインや執筆業務の報酬は源泉徴収の対象ですが、単なる事務作業は対象外となることが多いです。判断に迷った場合は、国税庁のガイドラインを確認し、税理士に相談するのが確実です。
Q2.源泉徴収額の計算ミスが発生した
A2:源泉徴収額は報酬額に応じて異なり、計算ミスがあると税務調査で指摘される可能性があります。報酬額の10.21%(100万円以下の場合)や20.42%(100万円超の場合)など、正しい税率を適用することが重要です。計算ミスを防ぐために、税務ソフトを活用するか、専門家に確認すると安心です。
詳しくは、「デザイナーに支払う報酬に源泉徴収が必要となるケースや計算方法を解説」の記事をご参照ください。
Q3.フリーランス側から源泉徴収の還付を求められた
A3:フリーランスは確定申告を行うことで、源泉徴収された税額の還付を受けることができます。しかし、企業側が誤って過剰に源泉徴収してしまうと、フリーランスから還付請求を受けることがあります。契約時に源泉徴収の有無を明確にし、適正な税額を計算することでトラブルを防げます。
源泉徴収に関する詳しい内容は、国税庁のホームページをご参照ください。
Q4.源泉徴収の納付期限を過ぎてしまった
A4:源泉徴収税は翌月10日までに納付する必要があります。期限を過ぎると延滞税が発生し、税務署から指摘を受ける可能性があります。納付期限を管理するために、スケジュールを設定し、税務担当者と連携して確実に納付することが重要です。
Q5.源泉徴収の対象外だと思っていたが、後で対象と判明した
A5:一部の業務委託契約では、企業側が源泉徴収の対象外と判断していたものの、後で税務署から指摘を受けるケースがあります。特に、報酬の性質が曖昧な場合は、事前に税理士に相談し、契約書に源泉徴収の有無を明記することでリスクを回避できます。
なお、源泉徴収が必要な報酬や料金は、国税庁のホームページでご確認いただけますので、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度施行後の源泉徴収は?
インボイス制度が2023年10月1日より始まりました。源泉徴収税の計算方法は従来と変わりませんが、委託する業務内容によっては消費税の適用税率が変わるため、トラブルが起こる可能性も考えられます。
源泉徴収税に関して大きな影響はありませんが、ある程度知識をもってるフリーランスへ委託したほうがトラブルは起こりにくいかもしれません。
インボイス制度に関する企業側の対応については、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:インボイス制度はなぜ必要? 専門家に“中立的な視点”から教えてもらった
源泉徴収をふまえた業務委託の導入方法
業務委託人材を活用するときは、源泉徴収以外にも用意しておくことがあります。
業務委託契約書とNDAも用意する
源泉徴収には納税者の氏名や住所などの個人情報が必要ですが、個人情報を提供するにあたって抵抗を示す個人事業主やフリーランスも少なくありません。NDA(秘密保持契約書)は預かった個人情報を適切に扱うことを約束する契約書です。
クラウドソーシングを利用する場合もNDAの締結は可能です。匿名で活動しているフリーランスや個人事業主が多いため、安心して受注してもらうためにもNDAの締結をお考えください。
なお、無料配布資料「フリーランス・副業人材との業務委託契約書作成ガイド」では業務委託契約を締結する際に必要な契約書の作成方法をまとめております。下記より無料でダウンロードいただけますのでぜひご活用ください。

源泉徴収税について説明する体制をつくる
トラブルが起きたときのために、源泉徴収税について説明できる体制を整えておくことが大切です。
- 源泉徴収は所得税の前払い
- 給与所得者と同じように行うもの
- 業務委託先は確定申告で還付を受けることが可能
こうした内容を説明できるようにしておくと、もしものときに安心です。もし、委託先が源泉徴収や確定申告に関する知識がなく、所得申告をしていないようであれば企業側からもある程度サポートしたほうがよいでしょう。
もし委託先が無申告でペナルティを受けて業務を続けられなくなると、企業側にとっても大きなデメリットとなります。業務委託契約を結ぶときに、内容について双方で確認しておくことが大切です。
業務委託人材を採用するならクロスデザイナーにおまかせください
業務委託は源泉徴収の対象です。委託先が正しい知識をもっているとは限りません。トラブルに備えて社内で体制を整えておくことが大切です。もし、ペナルティなど不安があるときは、業務委託契約をサポートするエージェントを活用する方法もあります。

クロスデザイナーは国内最大級のデザイナー専門のプロ人材エージェントサービスです。『Workship』に登録する約7,000人のデザイナーより、自社の要望に応じた人材を紹介いたします。
不明点も多く聞かれる業務委託契約をサポートしているため、スムーズに即戦力人材を確保することが可能です。双方の合意があれば正社員への転換もできます。詳細は無料でダウンロードいただけるサービス資料にまとめております。貴社のデザイナー採用にお役立てください。
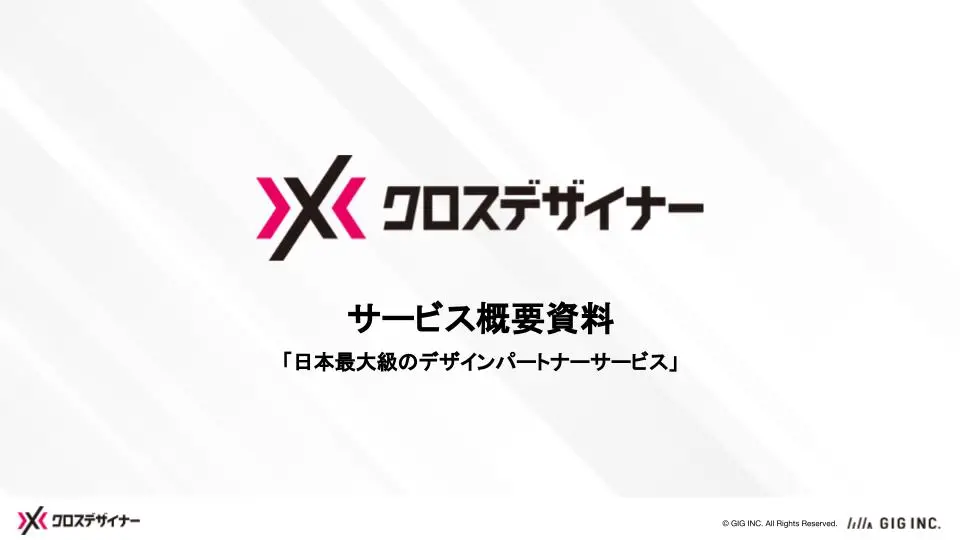
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents