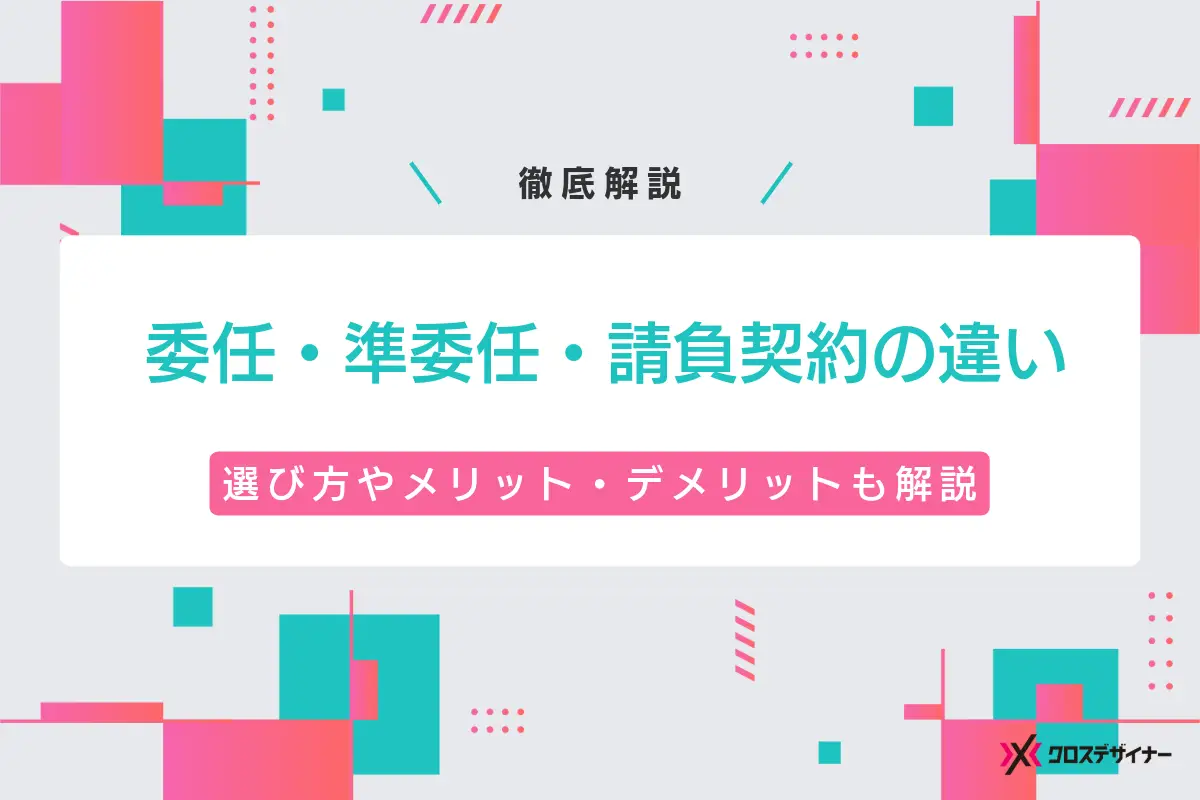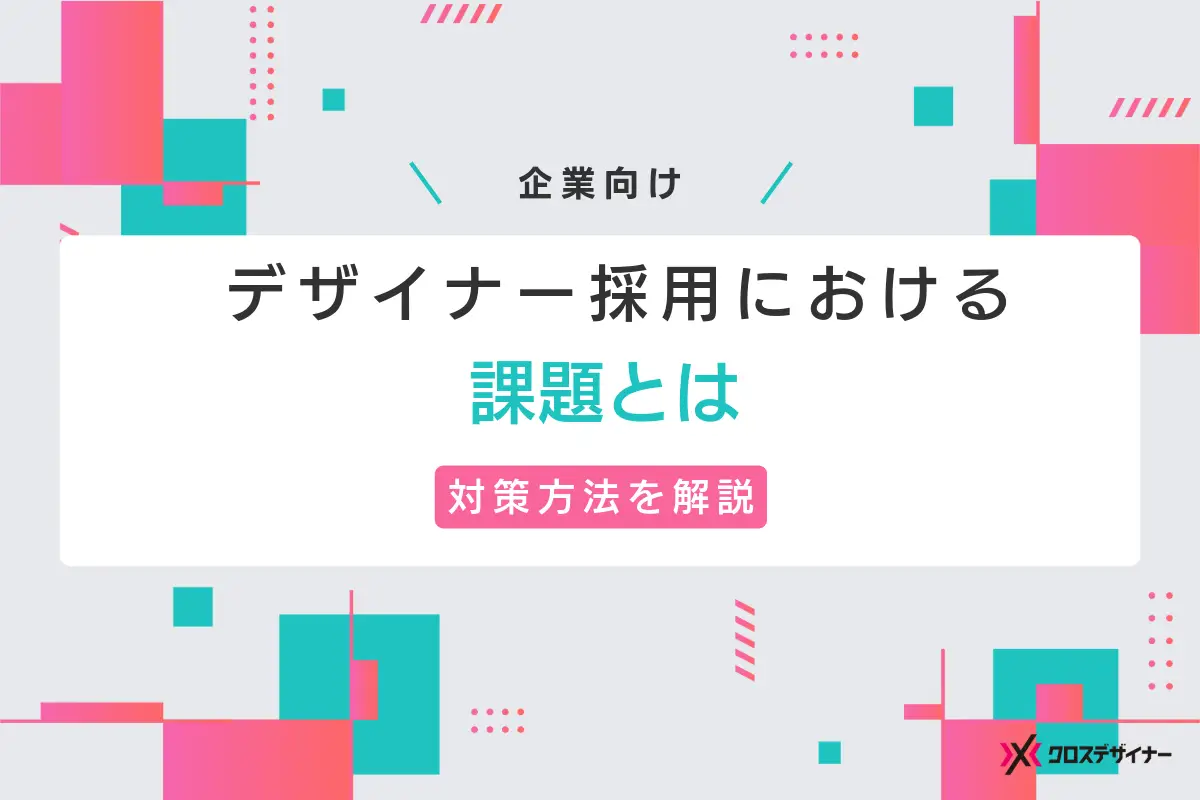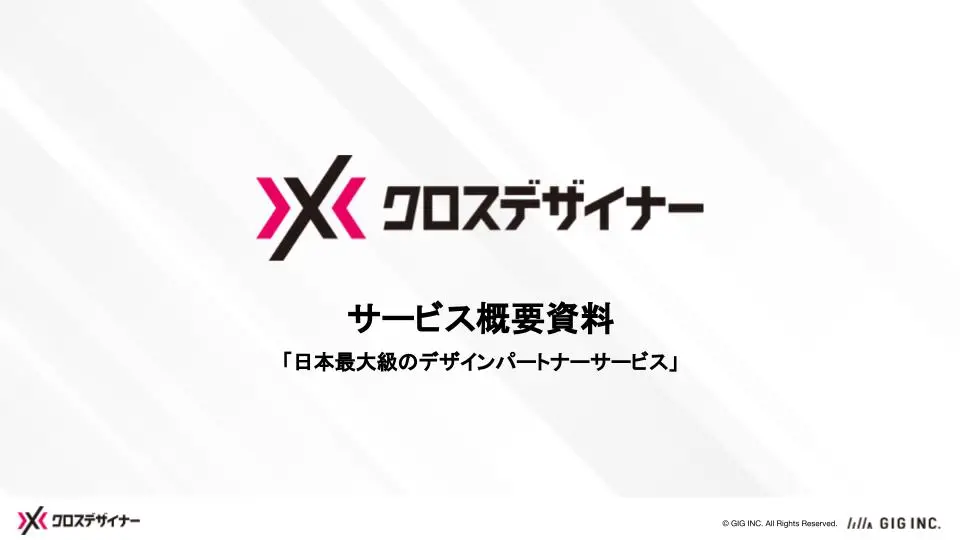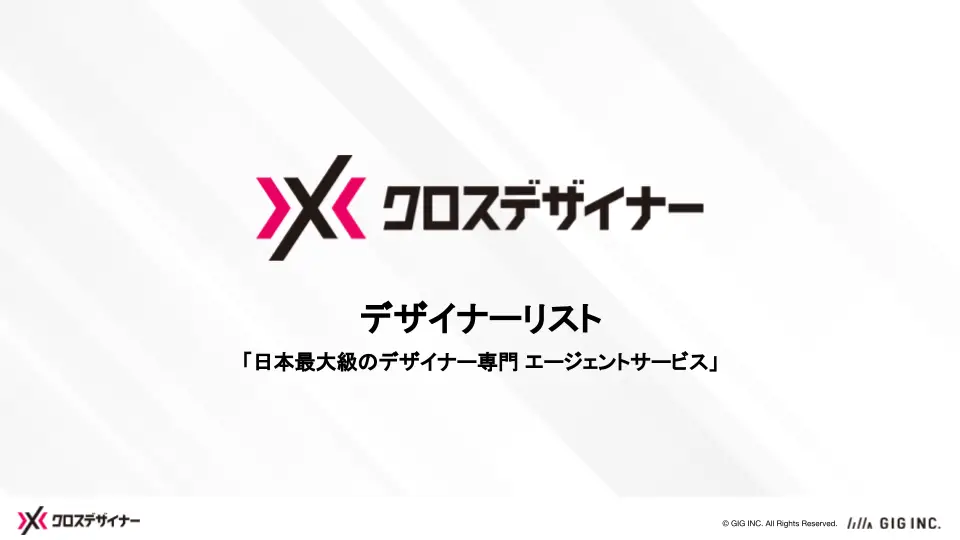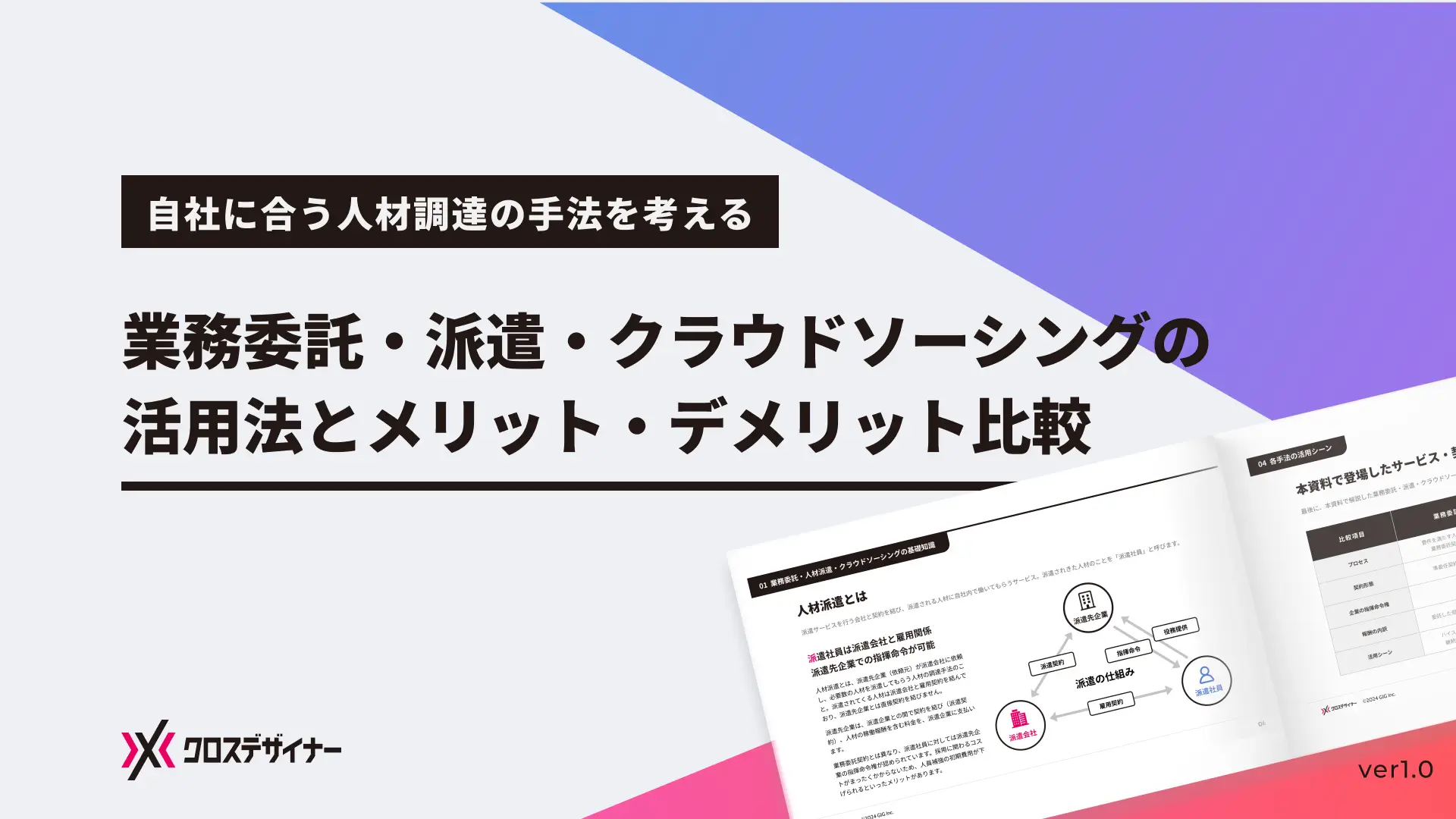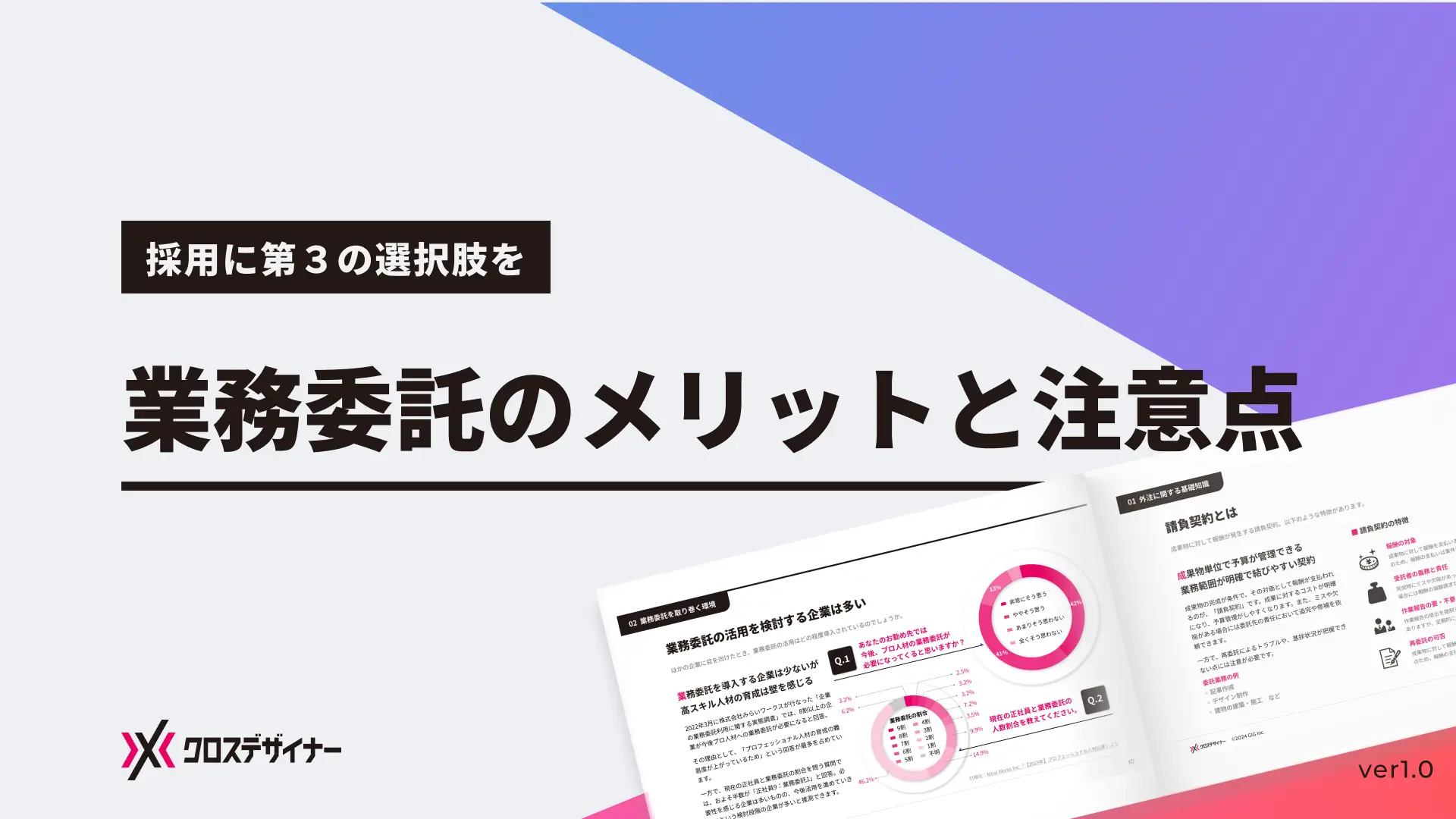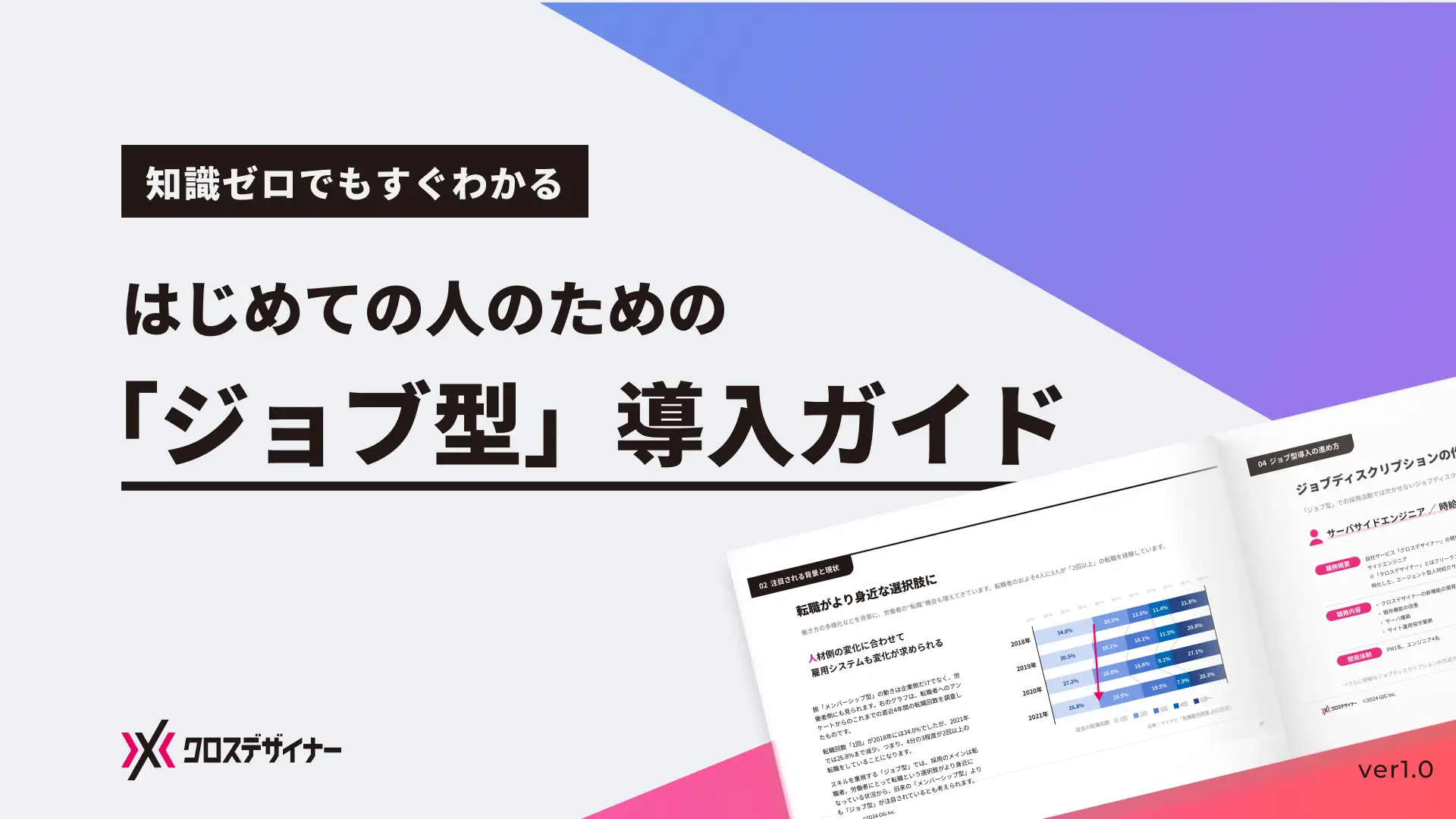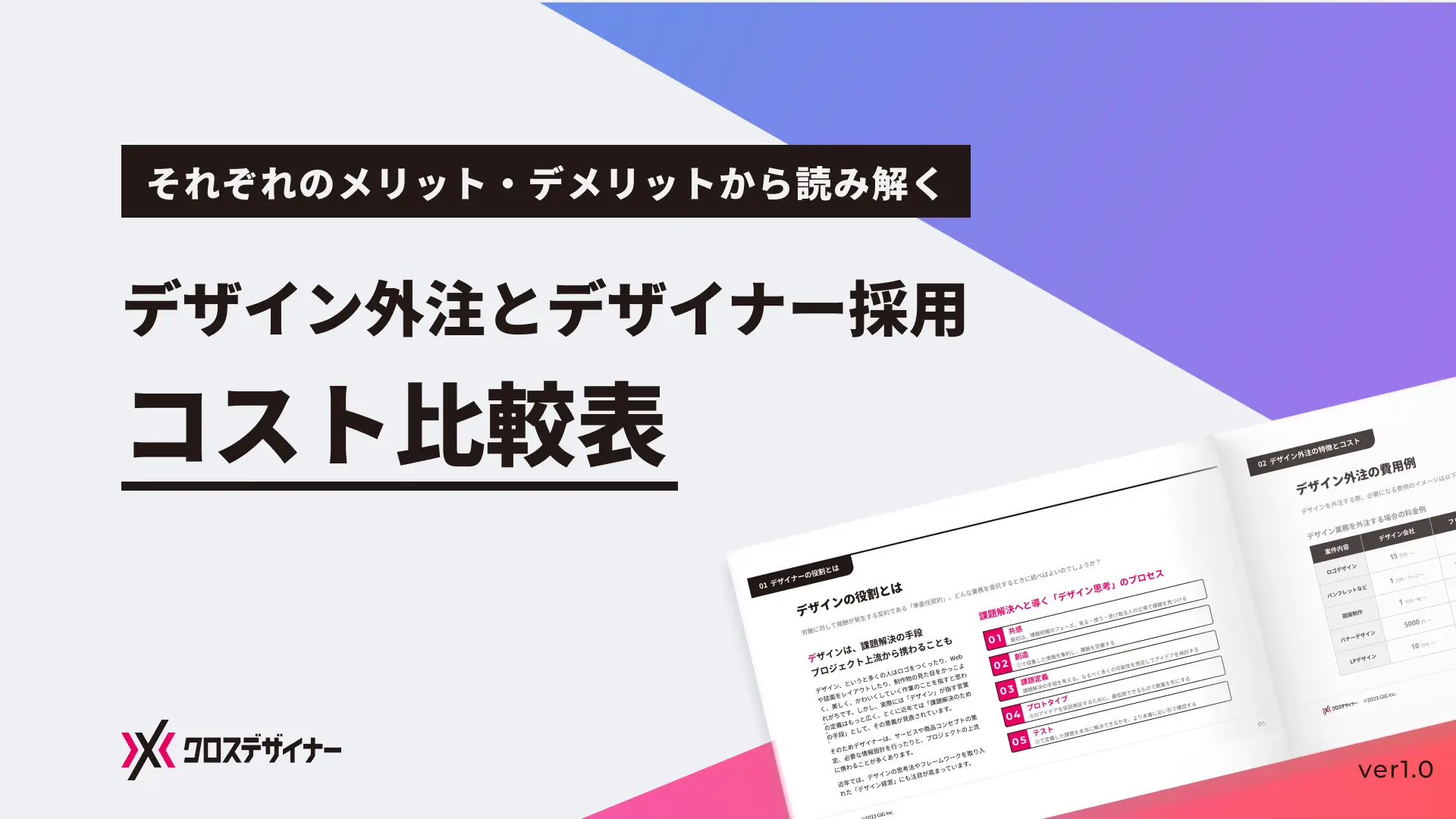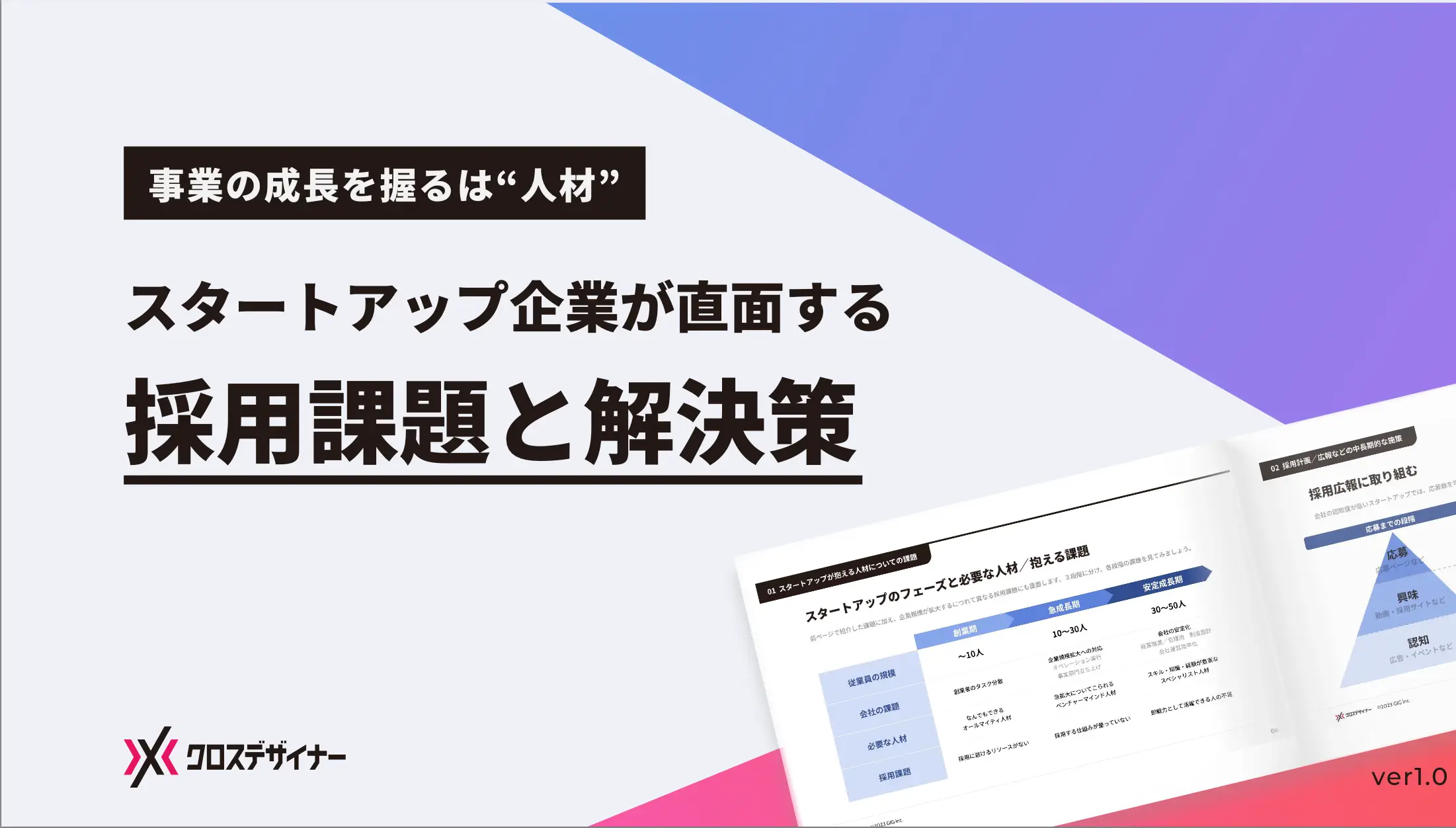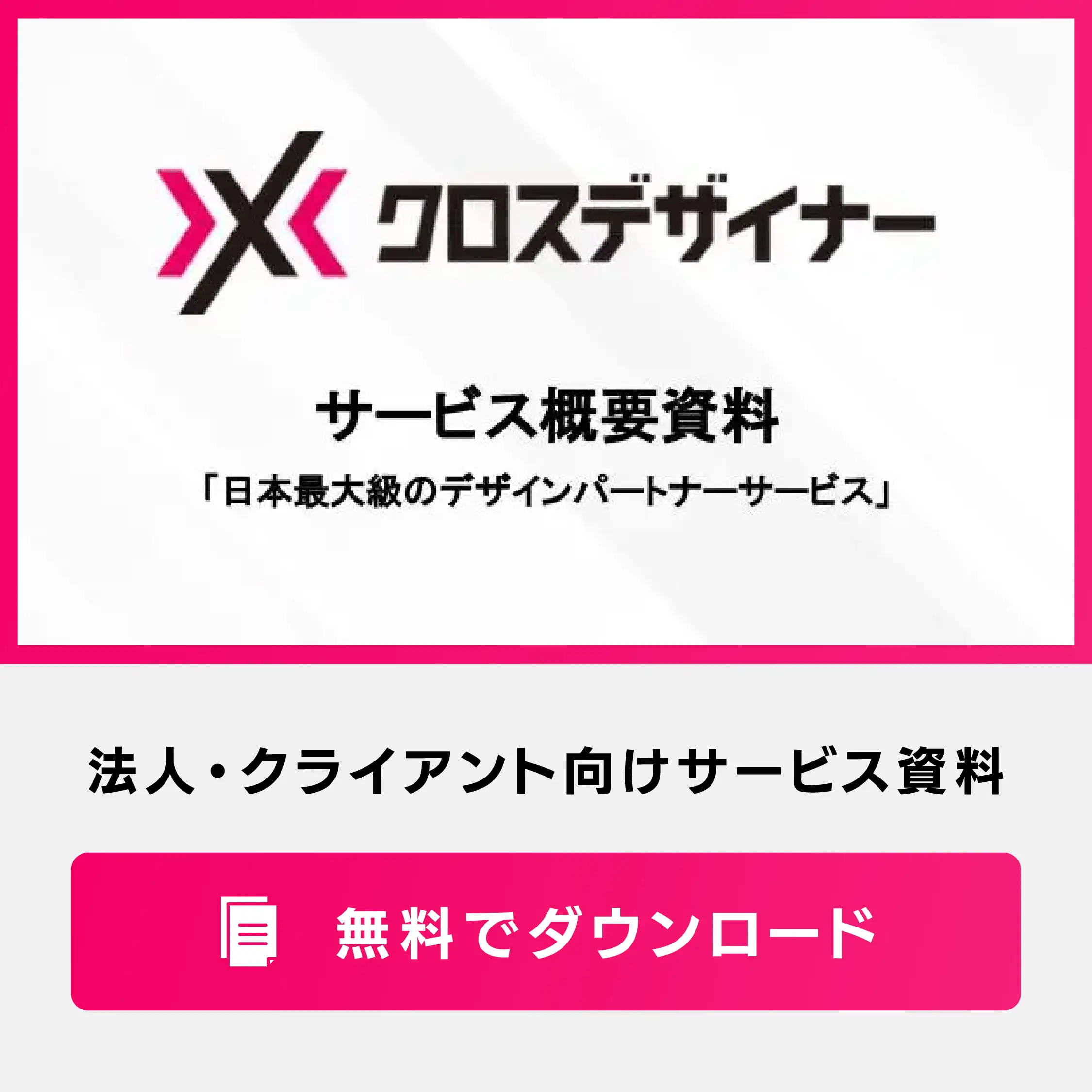ビジネスやプロジェクトを進める上で、契約の種類は非常に重要です。特に、委任契約、準委任契約、請負契約の違いを理解することは、適切な契約を選び、トラブルを避けるために欠かせません。
委任契約は、法的な業務を他者に任せる際に用いられる契約で、信頼関係が重視されます。一方、準委任契約は、法律以外の専門的な知識や技術が求められる業務に適した契約です。そして請負契約は、成果物の完成を目的とする契約で、結果に対する責任が明確なのが特徴です。
これらの各契約形態の違いを理解し、適切に選ぶことで、ビジネスの成功に繋がります。
そこで今回は、委任契約・準委任契約・請負契約の違いを比較し、各契約形態の選び方やメリット・デメリット、注意点も徹底解説します。詳しい内容については、一般的に用いられる準委任契約と請負契約を中心に紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
委任契約・準委任契約・請負契約とは?概念や選び方、適する業務事例も解説
以下ではまず、委任契約・準委任契約・請負契約の基本的な概念や選び方、適する業務事例を解説します。
委任契約
委任契約は、法律行為を依頼する場合に選ぶ契約形態です。例えば、弁護士に訴訟代理を依頼する場合などです。また、税理士が企業と顧問契約を結び、税務相談や申告書作成などの業務を継続的に行う契約も委任契約となります。
なお、委任契約は業務の遂行が目的であり、成果物の完成は必須ではありません。
考慮すべきポイントとしては、委託する業務内容を具体的に定めること、報酬について明確に取り決めること、そして契約解除の条件を確認することが挙げられます。
委任契約に適した主な業務
- 弁護士に訴訟代理を依頼する
- 税理士に確定申告の手続きを依頼する など
準委任契約
準委任契約は、法律行為以外の業務を依頼する場合に選ぶ契約形態です。例えば、ITシステムの運用・保守業務を依頼する場合などです。
準委任契約も、委任契約と同様に業務の遂行が目的であり、成果物の完成は必須ではありません。
考慮すべきポイントとしては、業務内容を具体的に定めること、報酬の発生タイミングを明確にすること、そして再委任の可否を契約書に明記することが重要です。
報酬については、成果完成型と履行割合型のどちらかを選択する必要があります。
準委任契約に適した主な業務
- コンサルタントに経営アドバイスを依頼する
- ITサポート会社にシステムメンテナンスを依頼する
- マーケティング会社に広告キャンペーンの企画を依頼する など
関連記事:準委任契約とは?契約形態の違いと契約書の書き方について解説
下記の資料では、準委任契約と請負契約の比較や、実際に締結する際のポイントなどを網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご参照ください。

請負契約
請負契約は、成果物の完成を依頼する場合に選ぶ契約形態です。例えば、デザイナーにWebデザインを外注する際や、ITエンジニアにソフトウェア開発を委託する場合などです。
請負契約では、完成した成果物に対して報酬が支払われます。
考慮すべきポイントとしては、完成させるべき仕事の内容を具体的に定めること、納期を明確に定めること、そして契約不適合責任を明確にすることが挙げられます。
特に、納期遅延時の対応や、完成物に不具合があった場合の修補義務などを取り決めておくことが重要です。
請負契約に適した主な業務
- コンテンツ制作(Webサイトやデザインの制作)
- ソフトウェア開発(アプリやシステムの開発)
- 建設工事の請負(建物や工作物の建設) など
関連記事:【企業向け】請負契約とは? 準委任との違いやメリット・デメリットを解説
自社業務をはじめて外注する際は不安を感じる方も多いはず。そこで下記の資料では、外注の流れとポイントをステップ別に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

委任契約・準委任契約・請負契約の違いを比較
委任契約・準委任契約・請負契約は一般的に「業務委託」と呼ばれていますが、この3つが民法上の正式名称です。
以下では、委任契約・準委任契約・請負契約それぞれの違いを、委託する企業の視点から比較します。
委任契約 | 準委任契約 | 請負契約 | |
契約内容 | 法律行為の委託 | 法律行為以外の委託 | 仕事の完成を目的とする |
適用業務 | 訴訟代理、契約締結など | Webサイトの運用・保守、コンサルティングなど | Webデザイン、ソフトウェア開発など |
成果物の有無 | 必須ではない | 必須ではない | 必須 |
報酬の対象 | 業務の遂行 | 業務の遂行または成果物 | 成果物の完成 |
リスク管理 | 善管注意義務 | 善管注意義務 | 完成物に対する契約不適合責任 |
契約の柔軟性 | 高い | 高い | 低い |
解除条件 | 双方の合意のもとで可能(損害賠償あり) | 双方の合意のもとで可能(損害賠償あり) | 原則不可 |
再委託の可否 | 原則不可(承諾があれば可) | 原則不可(承諾があれば可) | 可能(ただし事前の同意や契約書への記載が必要) |
メリット | 法律行為の専門家に依頼できる | 専門知識を持つプロに依頼できる | 完成物の品質が保証される |
デメリット | 成果が保証されない | 成果が保証されない | 柔軟性が低い |
上記のように、各契約にはそれぞれの特徴と適用範囲があります。具体的な業務内容や目的に応じて、最適な契約形態を選択することが重要です。
下記の資料では、初めての方でも業務委託を安心して活用できるように、契約形態ごとの概要や特徴を比較しやすい一覧表とともに解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

委任・準委任契約と請負契約のメリットとデメリット
以下では、準委任契約と請負契約のメリットとデメリットをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
委任・準委任契約のメリットとデメリット
委任・準委任契約は、特定の技術や知識を持つ専門家に業務を委託でき、効率的に業務を遂行できる利点があります。委任・準委任契約は業務の遂行が目的であり、契約期間や内容を柔軟に変更できるため、プロジェクトの進行に合わせて調整可能な点もメリットです。
一方、業務の遂行方法については具体的な指示を出すことができないため、業務の進行管理が難しい場合があります。また、業務の結果に対して完成の義務がないため、期待通りの成果が得られなくても費用が発生する可能性がある点がデメリットと言えるでしょう。
関連記事:業務委託の準委任契約とは?請負や委任契約との違い、メリットや注意点を解説
請負契約のメリットとデメリット
請負契約は、仕事の完成が契約の目的であるため、指定した成果物が納品されることが保証されます。また、成果物に対して報酬が支払われるため、無駄なコストを抑えることができるメリットがあります。
一方で、外部に業務を委託するため、社内にノウハウが蓄積されにくいことや、業務の進め方や方法について具体的な指示を出すことができないために業務の進捗管理が難しい点などがデメリットです。
上記のように、それぞれの契約形態には特有のメリットとデメリットがあるため、業務内容や目的に応じて適切な契約形態を選択することが重要です。
関連記事:企業が業務委託を活用するメリットとデメリット、注意点を徹底解説
委任・準委任契約と請負契約の注意点を解説
次に、委任・準委任契約と請負契約の注意点を、委託側の視点でそれぞれ解説します。
委任・準委任契約の注意点
委任・準委任契約における注意点は、主に次の3つが挙げられます
1.業務範囲を明確にすること
委任・準委任契約は業務の遂行が目的であり、成果物の完成義務はありません。そのため、契約書に業務範囲を明確に記載することが重要です。具体的な業務内容や範囲を明示することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、業務範囲が曖昧だと、期待する成果が得られない可能性があるため、詳細な業務内容を記載することが重要です。
2.偽装請負に注意すること
委任・準委任契約では、委託者が受託者に対して指揮命令を行うことはできません。もし、委託者が業務の進め方や労働時間などに関して指示を行うと、偽装請負とみなされる可能性があります。
偽装請負と判断されると、労働者派遣法や労働基準法に違反することになり、罰則が課せられる可能性があります。したがって、委託者は受託者に対して具体的な指示を出さず、業務の進行状況を確認する程度にとどめることが重要です。
関連記事:偽装請負とは?禁止事項や判断基準、問題点や罰則などを事例とともに解説
3.再委託を管理すること
委任・準委任契約では、基本的に受託者が業務を第三者に再委託することができません。そのため、契約書に再委託不可に関する条項を明確に記載することが大切です。
再委託を禁止することで、自社の機密事項が漏洩するリスクを回避できます。
請負契約の注意点
請負契約における注意点は、主に次の4つが挙げられます
1.成果物を定義すること
請負契約では、契約の成果物を明確に定義することが重要です。具体的な仕様、品質、納期などを詳細に記載することで、双方の期待を一致させ、後々のトラブルを防ぐことができます。
2.契約不適合責任の範囲を設定すること
契約不適合責任とは、納品された成果物が契約内容に適合しない場合の責任を指します。この範囲を明確に設定することで、どのような場合に修正や再納品が必要かを明確にし、責任の所在を明確にできます。
3.契約解除の条件を設定すること
契約解除の条件を明確にすることも重要です。納期遅延や品質不良が続く場合、契約を解除できる条件を設定しておくことで、リスク管理がしやすくなります。また、解除の際の手続きや違約金についても明記しておくと良いでしょう。
4.再委託の条件を設定すること
再委託とは、請負業者(受託者)が第三者に業務の一部または全部を委託することを指します。再委託の条件を設定することで、品質管理や責任の所在を明確にできます。
関連記事:はじめての業務委託 成功のポイントと注意点を徹底解説
各契約に共通する注意点
業務委託契約においては、契約書の作成が非常に重要です。
適切な契約書を作成することで、委託者と受託者の権利と義務を明確にし、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。また、業務内容や報酬、支払い条件、納期などを具体的に記載することで、双方が安心して業務を進めることができます。さらに、契約違反が発生した場合の対応策や解決方法を明記することで、迅速かつ公平な解決が可能です。
業務委託契約書を作成する重要性
前述したように、業務委託契約書の作成は、委託者と受託者双方にとって非常に重要です。
契約書を作成する目的は、委託者と受託者双方の権利と義務を明確化することです。
業務内容や報酬、納期などを具体的に定め、契約書に明記することで、誤解やトラブルを防ぎます。これは、スムーズな業務遂行や、信頼関係の構築にもつながる重要な要素です。
また、著作権や秘密保持に関する取り決めを明文化することで、将来に起こりうる成果物の権利に関する法的リスクを軽減できます。
業務委託契約書は、下請法によって書面(電子書面も可)での契約が求められており、作成しないことは違法行為となる可能性があるため注意が必要です。
上記のように、業務委託契約書の作成は、法的保護や効率的な業務遂行、健全なビジネス関係の構築に不可欠なプロセスなのです。
業務委託契約書に記載すべき基本項目
業務委託契約書に記載すべき基本項目は、委託する業務によってさまざまです。、そこで以下では、特に重要な項目をピックアップして一覧表でわかりやすく解説します。
以下の項目を適切に記載することで、委託者と受託者の権利義務を明確にし、将来的なトラブルを防ぐことが可能です。
記載項目 | 説明 |
業務内容 | 委託する業務の具体的な内容と範囲を明確に記載します。 |
契約期間 | 契約の開始日と終了日、自動更新の有無や条件を明記します。 |
報酬と支払条件 | 報酬額、算定方法、支払時期、支払方法などを明記します。 |
再委託 | 業務の第三者への再委託の可否と条件を明記します。 |
成果物の納品と検収 | 成果物の具体的な内容、納品方法、検収基準を明記します。 |
知的財産権の帰属 | 納品された成果物の著作権や知的財産権の帰属を明確に記載します。 |
秘密保持 | 業務上知り得た情報の取り扱いと守秘義務を取り決めて明記します。 |
契約解除条件 | 契約違反や不履行時の解除条件と手続きを取り決めて明記します。 |
損害賠償責任 | 契約不履行や秘密漏洩などによる損害の賠償責任についての取り決めを明記します。 |
管轄裁判所 | 万が一の紛争発生時に備えて、訴訟を提起する裁判所を指定して明記します。 |
上記のような項目を網羅しつつ、契約の変更事項や紛争の解決方法なども契約書に明記しておくことで、不要なトラブルを回避できるでしょう。なお、各項目の詳しい内容や契約書の作成方法については、以下の記事をご参照ください。
関連記事:業務委託契約書の重要性と作成方法、記載すべき項目や注意点を解説【テンプレ付き】
下記の資料では業務委託に必要な4種類の契約書について、すぐに使えるテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

デザイン案件の業務委託は、クロスデザイナーにおまかせ!
クロスデザイナーはフリーランスデザイナー専門のエージェントで、即戦力となるデザイナーを紹介し、クライアントのニーズに適した人材を迅速に提案いたします。
クロスデザイナーを活用することで、専門性の高い優秀なデザイナーを迅速に確保できるため、企業のブランドイメージやユーザー体験の向上にも寄与するでしょう。
国内最大級のデザイナー専門のエージェントサービスである、クロスデザイナーには、厳正な審査を通過したハイスキルなデザイナー7000人以上が在籍しており、自社に合うデザイナーを見つけることができます。また、制作開始後も担当のコンサルタントがさまざまなトラブルや困りごとにも親身になって対応するため安心です。
さらに、登録しているデザイナーと合意があれば正社員採用も可能です。スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い、即戦力デザイナーの採用機会を最大限サポートしています。
エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の柔軟な依頼も可能なので、自社の作業量に応じて効率的に外注することが可能です。
こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声

Workship MAGAZINE編集部。フリーランス、マーケティング、会計経理、経営分野が専門。個人事業主としてスポーツインストラクター、飲食店経営、飲食コンサルを経て、現在はコンテンツ制作会社を経営中。
Documents