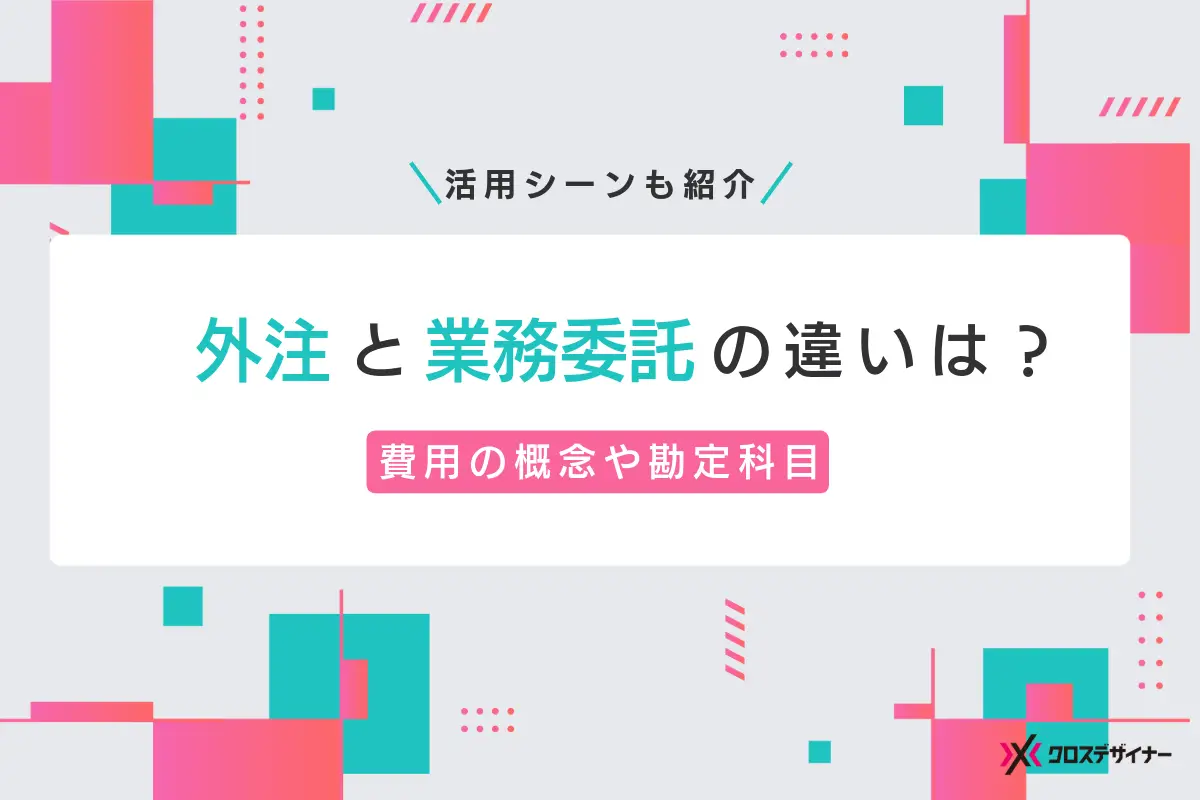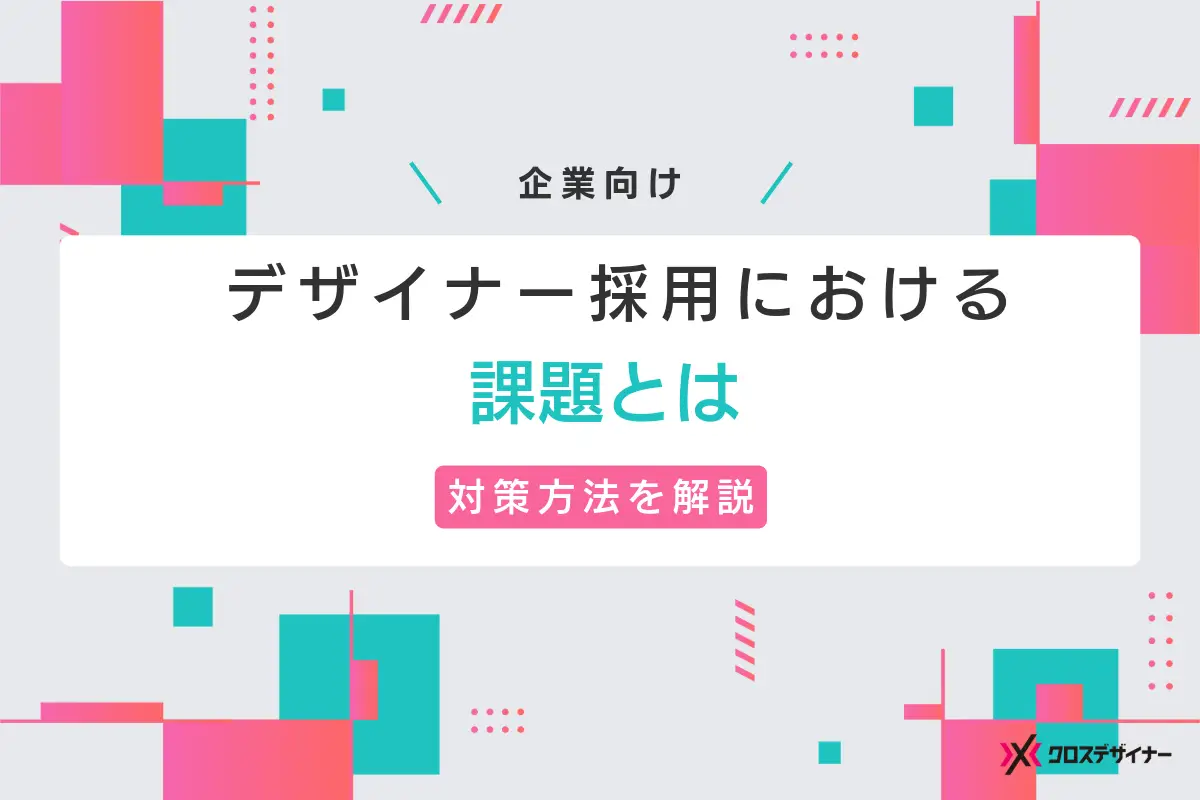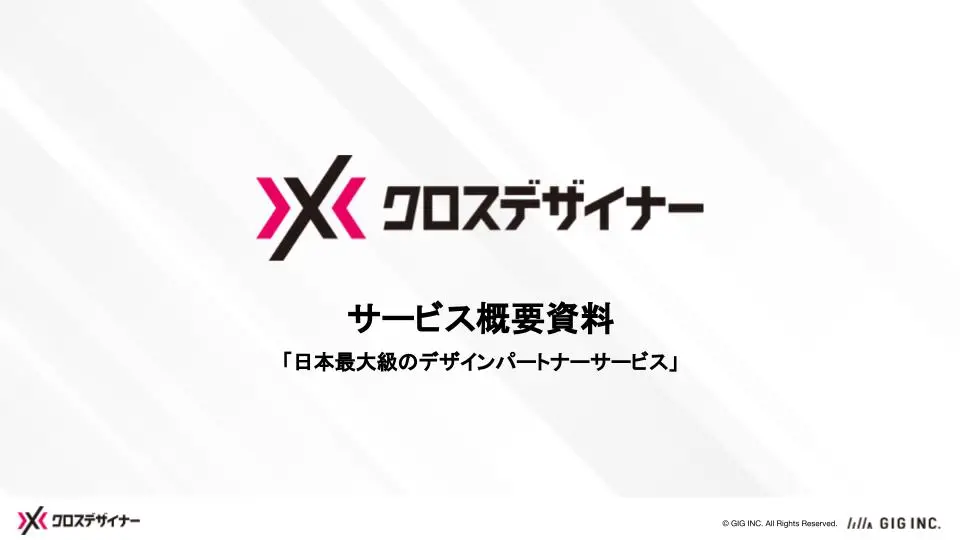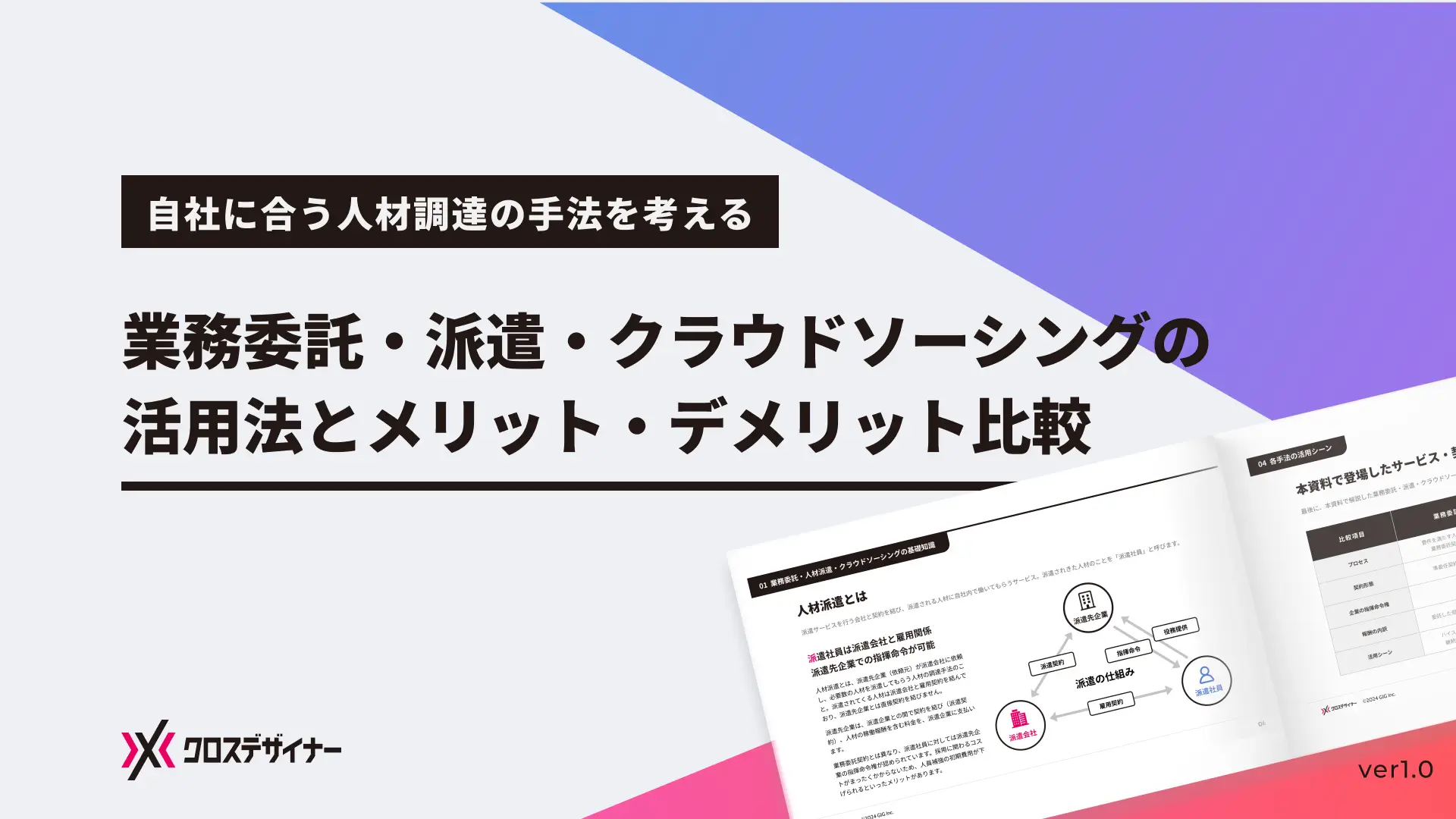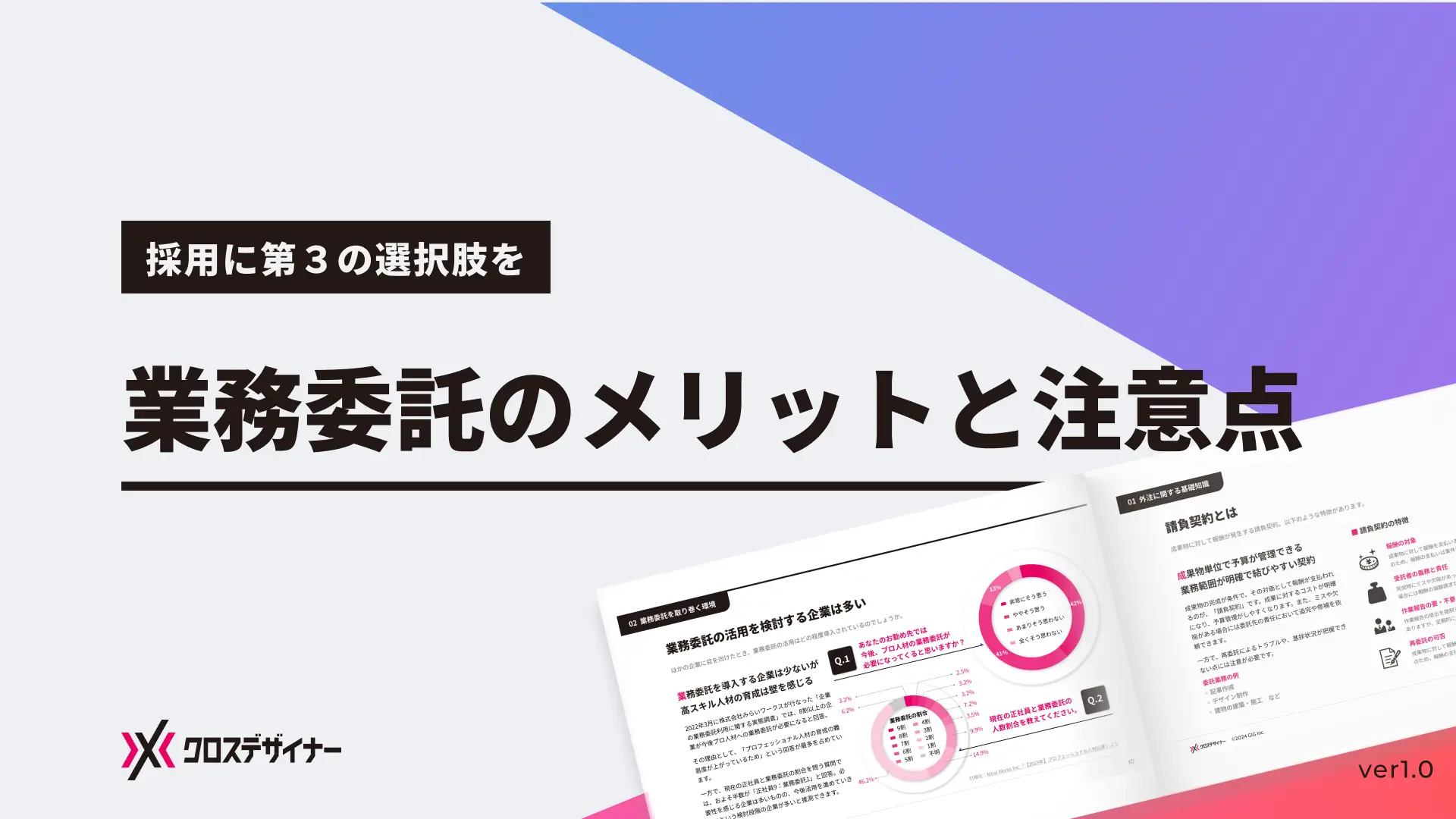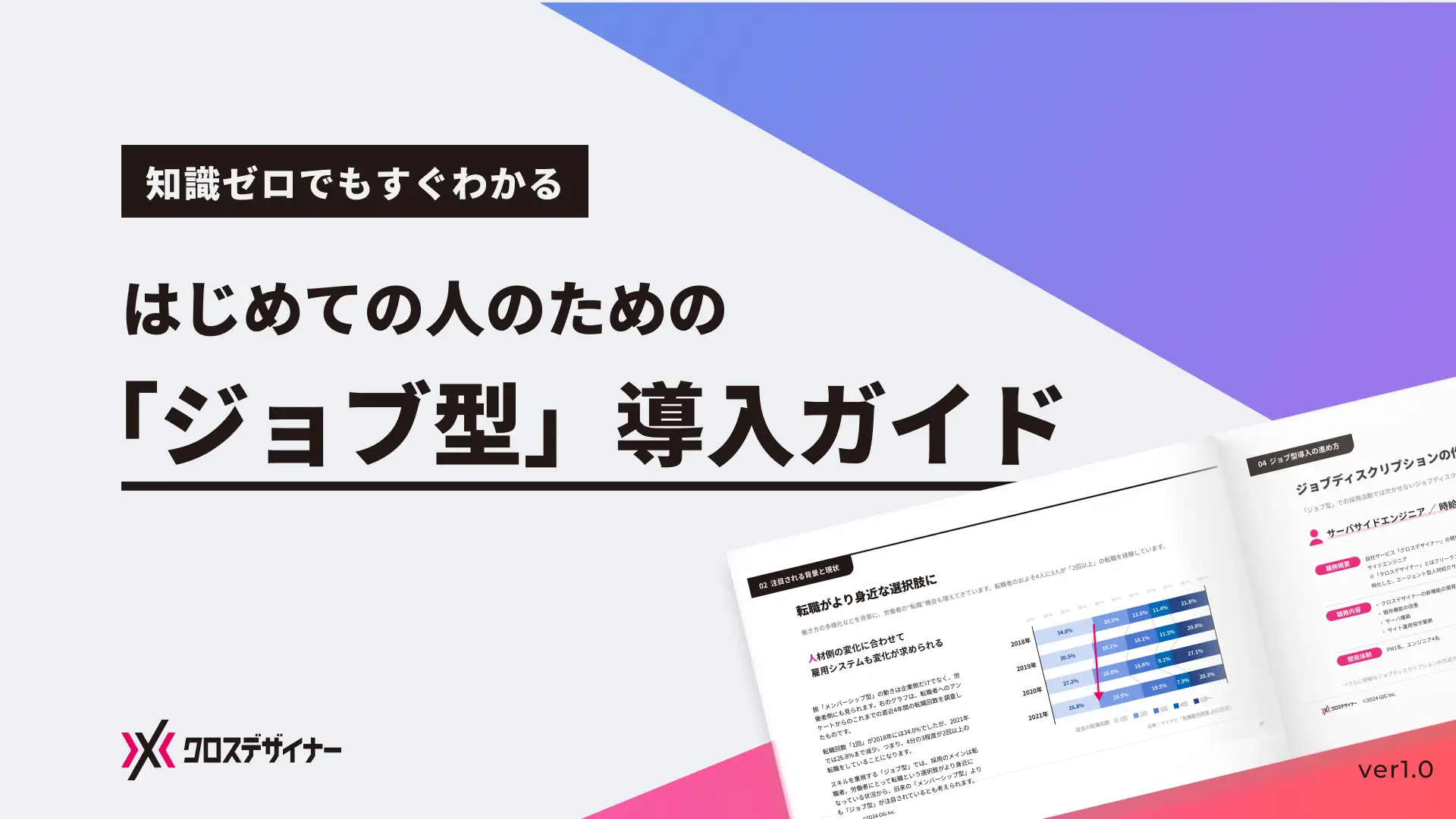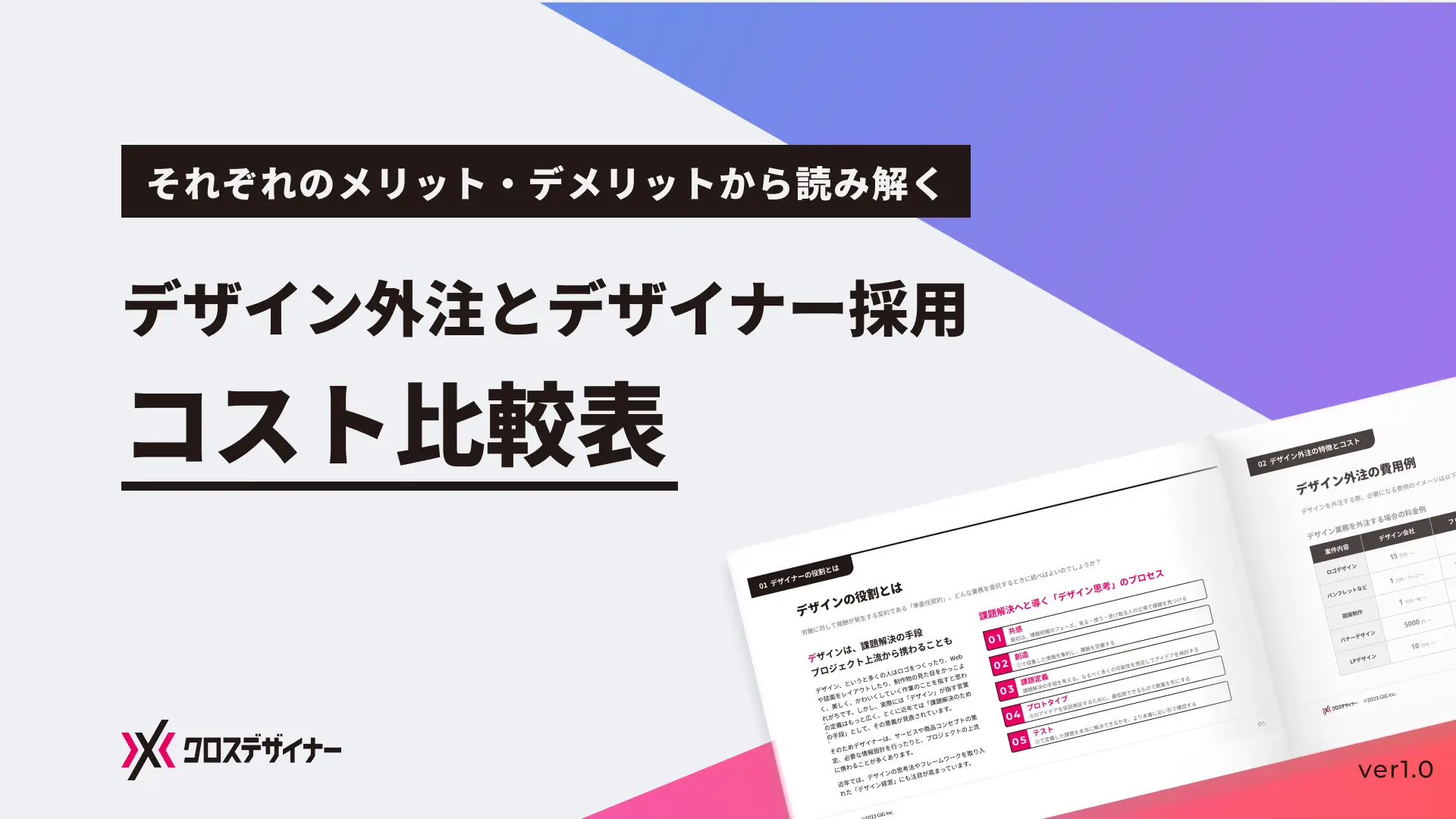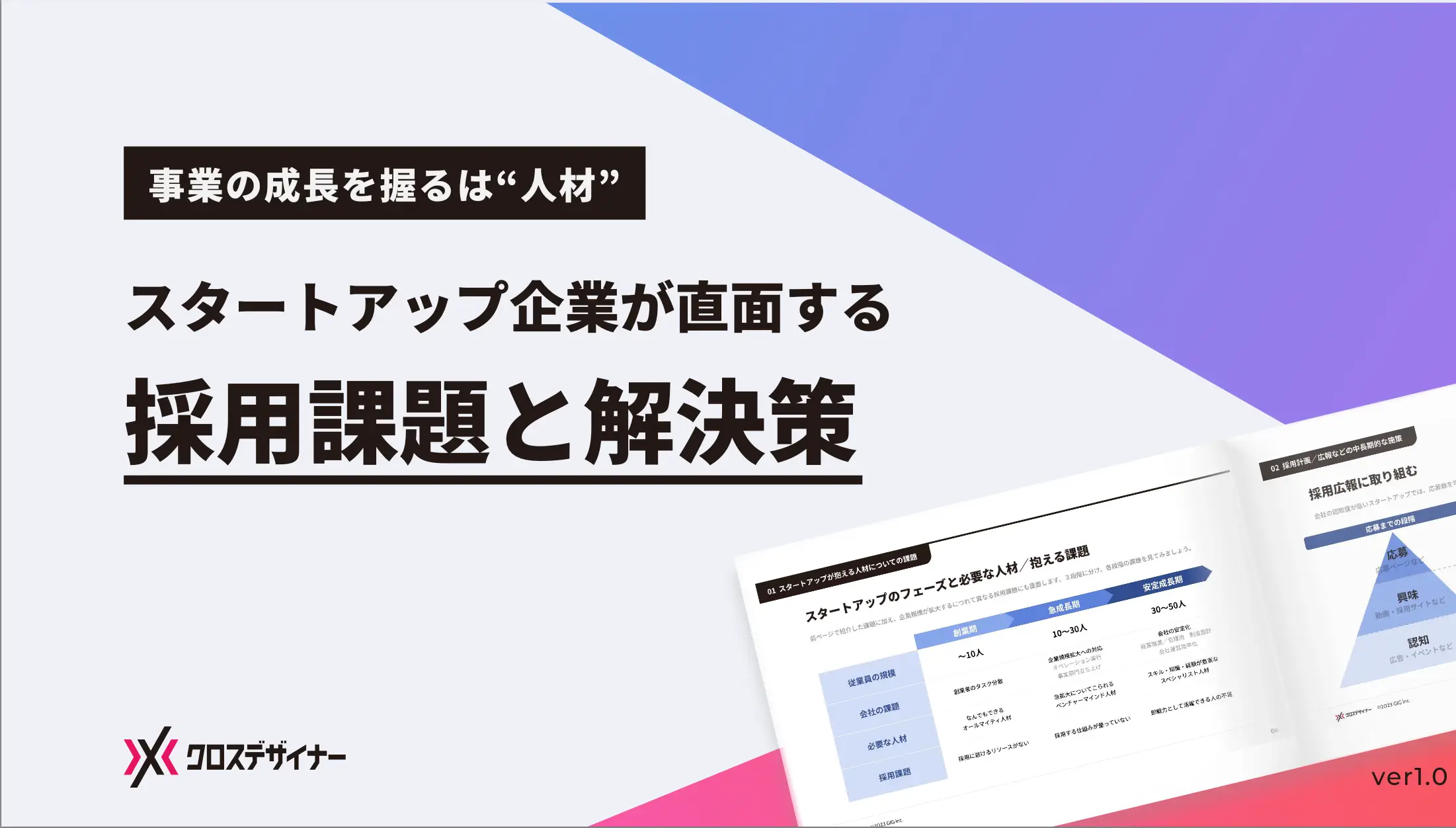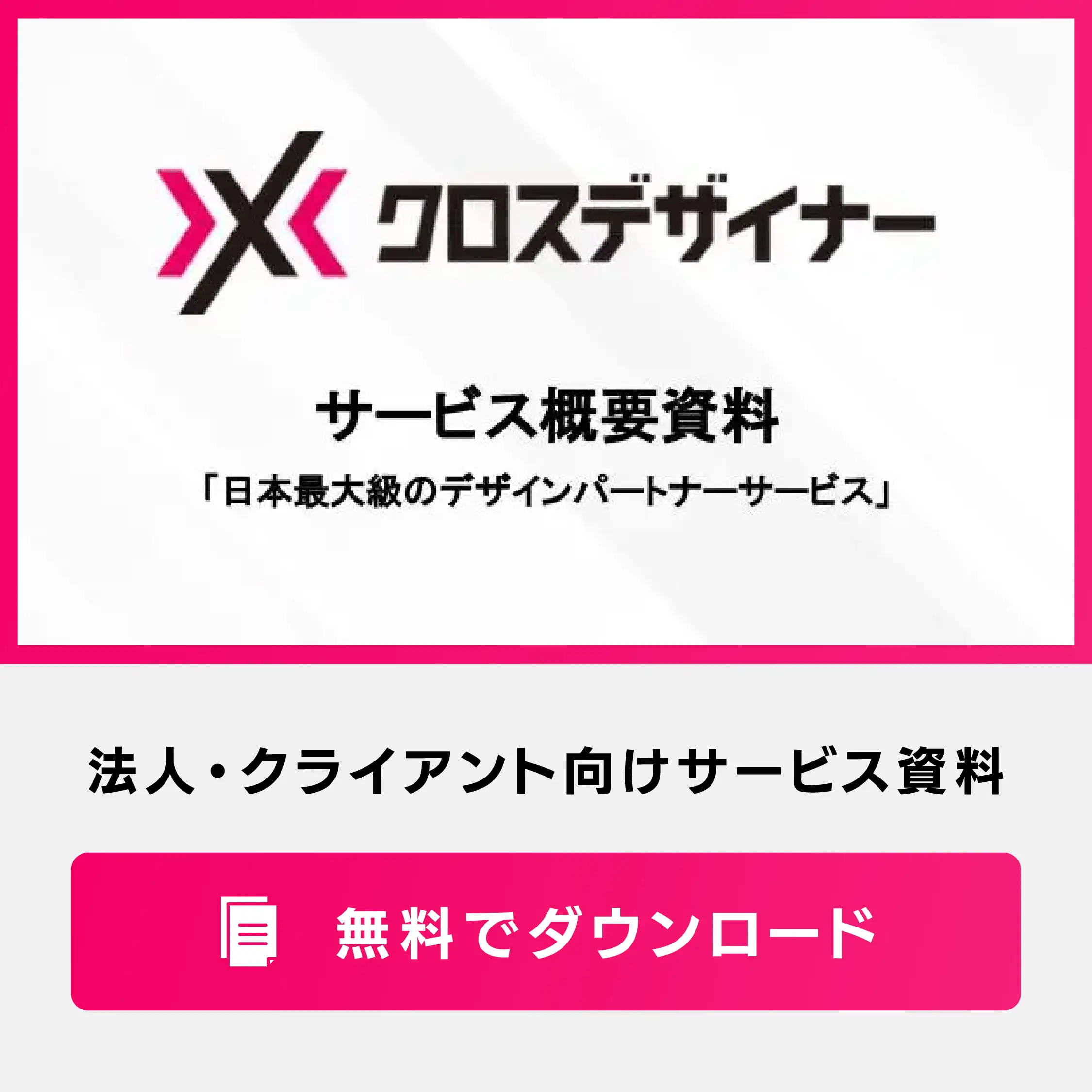社内に必要な人材が足りない、あるいはコストを抑えて人材確保をしたいときに外注を検討する方は多いでしょう。
しかし、「外注と似た言葉の業務委託って何が違うの?」「それぞれのできることや特徴って?」といった疑問にぶつかるのではないでしょうか。
そこで本記事では、初めて外注しようとしている方に向けて、外注や業務委託の違いから、外注先や外注の注意点まで解説します。外部リソースを効果的に取り入れたい方はぜひお役立てください。
外注と業務委託の違いとは?
外注と業務委託は、どちらも外部に業務を依頼する方法です。同じ意味合いで使われることが多いですが、正式には異なる意味をもっています。まずは外注と業務委託の違いについて解説します。
外注の意味
外注とは「外部へ仕事を発注する」ことを指す言葉です。「外部発注」と呼ばれることもあります。発注先は個人・法人など事業規模や契約形態は問いません。
企業が自社で対応が難しい業務や、専門性が高い作業が対象です。基本的に成果物が重視されますが、正式な契約形態を指す言葉ではありません。そのため、契約書などで「外注」などの文言を使用するのは避けたほうが良いでしょう。
関連記事:外注する際の流れとは? 必要な期間や短縮のポイントまで紹介
業務委託の意味
業務委託は、外注と同じように外部に業務を委託することを指しています。外注との違いは「人に頼んでやってもらう」ことを指しており、委託する業務によって「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態があります。
「請負契約」は成果物の納品によって報酬が支払われる契約です。「委任契約」は法律行為を依頼するもので弁護士など士業が対象となります。準委任契約は法律行為以外の仕事を依頼するときに使われる契約形態となり、労働力に対して報酬が支払われます。

関連記事:業務委託とは?簡単に、ほかの契約との違いやメリット・デメリットを解説
関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説
外注費と業務委託費の違い
外注と業務委託は、同じ依頼内容でも経費として認められる範囲が異なります。経費処理にも影響が出てくるため、正しく理解しておくことが大切です。
外注費の特徴
外注費は、外注にかかった費用すべてが対象です。依頼内容に応じた報酬だけではなく、発注のための準備にかかった費用や外部人材の管理費用などを「外注費」として計上することができます。
さまざまな費用をまとめて計上できるため、外部へ委託するときは外注費として計上できるかどうかを重視することでコストダウンが期待できます。
関連記事:外注費の勘定科目は?源泉徴収や消費税などの仕訳例も解説
業務委託費の特徴
業務委託費は「請負契約」と「準委任契約」のそれぞれの契約形態で定めた報酬が対象です。外注費のように、発注のためにかかったあらゆる費用は一切含まれません。計上できる費用の範囲は狭くなります。
さらに業務委託は契約の性質上、成果物の完成条件をこまかく決めておく必要があります。事前に詳細な条件のすり合わせと契約書の作成といった負担も考慮しなければなりません。
関連記事:【企業向け】業務委託に源泉徴収は必要?対象となるケースや税額の計算方法を解説
外注で業務委託の活用をおすすめするシーン
外部に業務を委託する場合、どのようなシーンで外注の活用が適しているのか解説します。
1. 社内人材の活用や育成に集中したい
外注するのに適した業務として、普段の業務で時間を割いている単純な業務や繁忙期など一時的に増える業務などが該当します。こうした社員が本来注力すべき業務に専念したい場合に、外注の活用が適しています。
業務を外注することで、社員が本来やるべき業務への注力や人材育成など、会社の成長に向けた施策に集中して取り組むことが可能です。
売上向上につながる施策を立てるなど、クリエイティブな業務に取り組んでもらうことができます。また、業務にゆとりが生まれることで、社内人材の育成に向けた体制を整えるなど、外注から内製化に向けた育成環境の構築にも集中して取り組むことが可能です。
求める人材像を明確に描いておくと確保しやすくなります。以下の資料では、採用ペルソナの作成方法をまとめていますので、ぜひご覧ください。ダウンロードは無料です。

2. 社内のリソース不足をカバーしたい
プロジェクトや業務遂行に必要な専門スキルが社内で確保できない場合にも外注の活用がおすすめです。
社内で人材を育成するのは、時間や手間がかかるものです。業務委託なら専門的なノウハウをもつ即戦力人材へ依頼できます。雇用関係はないため、社会保険料などの負担や労務管理の手間もかかりません。双方が契約内容に合意できれば、すぐに仕事を進めてもらうことが可能です。
関連記事:採用コストの平均相場と費用の内訳|新卒や中途採用単価や削減方法も解説
3. 短い期間だけ採用したい
一時的な業務量の増加や、特定のプロジェクトに参画してもらいたい場合も外注の活用がおすすめです。
長期雇用を見据えた正社員採用とは違い、人件費を抑えられます。さらにスポット契約や短期間の契約など、業務にあわせて契約期間を決めることが可能です。
人件費は売上の増減を問わず発生する固定費ですが、外注することで変動費として扱うことができます。
外注を活用する前に、一度自社の採用コストを見直してみませんか。以下の資料では、採用コストを削減するための方法を提案しています。無料でダウンロードが可能です。

外注先の選び方
業務委託契約を結ぶ外注先には、企業とフリーランスがあります。それぞれに外注するメリットとデメリットについて解説します。
企業へ外注するメリット
企業へ外注するメリットは以下の通りです。
- 中規模以上の案件を依頼できる
- 一定の品質を確保できる
- 納期遅延のリスクが低い
企業は制作体制が整っているため、大量発注にも対応してもらえます。また品質と納期も担保されるため、確実に成果物が手に入るという点では安心感があるでしょう。
フリーランスへ外注するメリット
フリーランスへ外注するメリットは以下の通りです。
- 費用を抑えて外注できることが多い
- 必要なときだけ外注できる
- コミュニケーションがとりやすい
- 特定の分野に特化している
フリーランスは個人で活動しているため、1人分の人件費しかかかりません。そのため、外注費は企業と比べて費用を抑えられることが多いです。さらに単発依頼など、柔軟な依頼にも対応してもらえるメリットがあります。
コミュニケーションについても、フリーランス自身が窓口となり実務に取り組むため、企業に比べて伝達がスムーズです。専門スキルを効果的に活用したい場合は、フリーランスへの外注がおすすめです。
フリーランスとの業務委託契約の流れ
フリーランスへ外注するには、以下の業務委託契約の流れを理解しておくことが大切です。
1. 契約条件を事前に決めておく
業務委託契約を結ぶ前に、業務内容や納期、成果物の品質基準など具体的な条件を決めておきましょう。成果物を手に入れるには、定めた条件をクリアするフリーランスへ依頼する必要があります。
業務内容に必要なスキルや経歴などをまとめた「ジョブディスクリプション」を作成しておくと、人材の選定時に役立てることが可能です。以下の資料ではジョブディスクリプションの作成方法を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。

2. 報酬の支払い方を明確にする
業務委託は契約形態で報酬の対価が異なります。請負契約なら成果報酬、準委任契約なら時間単価などを設定することが可能です。支払いタイミングなどの具体的な条件を明確にしておくことで、金銭面でのトラブルを防ぐことができます。
3. 業務委託契約書を作成する
事前に定めた契約条件や報酬条件を、契約書にまとめます。作成した契約書は、必ず双方で確認をして署名をしましょう。これにより法的な根拠として使用することができ、トラブル防止にも役立ちます。
業務委託契約書はどちらが作成しても構いませんが、どちらか一方が不利になるような条項は避けるべきです。以下の資料では、フリーランスへの外注時に役立つ業務委託契約書の作成方法を解説しています。無料でダウンロードが可能です。

4. 秘密保持契約を別途締結する
業務内容によっては、社外秘情報を渡すケースもあるかもしれません。機密情報を扱う業務を委託するときは、「秘密保持契約書(NDA)」を別途締結しましょう。「秘密保持契約書」には以下の内容を記載します。
- 秘密情報の内容
- 開示範囲
- 使用目的
- 期間
- 情報漏えい時の措置
- 損害賠償
- 管轄裁判所
何が秘密事項に含まれるのかをきちんと明記することが大切です。期間は、秘密情報を取り交わす期間または受領した情報の秘密を保持する期間を記載します。また、業務委託契約書内に再委託を禁止する条項を入れておくことで、情報漏洩のリスクを減らすことが可能です。
関連記事:再委託とは?禁止される契約形態と発注前にできるリスク対策
5.納品までこまめにコミュニケーションをとる
契約締結後は、納品までまかせっぱなしにせず、コミュニケーションをとる機会を設けておくと進捗を確認できます。
プロジェクトの進捗や課題、変更点について定期的に情報を共有しましょう。こまめなコミュニケーションは大きなミスやトラブル防止に役立ちます。
業務委託契約は雇用契約とは異なり、従業員と同じように管理すると厳罰の対象となるケースもあります。以下の資料では、安心してフリーランスへ外注するために、押さえてほしい業務委託の労務管理についてまとめています。無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

フリーランスと業務委託を結ぶときの注意点
フリーランスと業務委託契約を結ぶときは、以下の3つに注意しましょう。
- 「偽装請負」にならないよう注意する
- 下請法に注意する
- 業務内容にあわせた契約を結ぶ
それぞれ簡単に解説します。
1. 「偽装請負」に注意する
「偽装請負」とは、業務委託契約を結んだフリーランスに対し、委託元となる企業が直接指示を出して働かせる行為を指します。業務委託契約では企業に指揮命令権はないため、従業員と同じように指示をすることはできません。以下のようなケースでは「偽装請負」と判断される可能性があるため、注意が必要です。
- 勤務時間や勤務場所を指定する
- 企業が直接業務指示を出す
- 再委託により責任の所在が不明
フリーランスは雇用関係がないため、トラブル時の労働や安全衛生面の保護が不十分です。不利な立場に置かれやすいフリーランスを守るために「偽装請負」は禁止されています。もし「偽装請負」と判断されると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(労働者派遣法59条2項)
優秀な人材に長く働いてもらいたい場合は、本人の合意を得たうえで正社員雇用を検討しましょう。
関連記事:偽装請負とは?禁止事項や判断基準、問題点や罰則などを事例とともに解説
関連記事:どこまでの指示が偽装請負になる?業務委託契約との関係性まで解説
2. 下請法に注意する
フリーランスへ外注するときは「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」を理解することが大切です。下請法は、親事業者が下請事業者を不当な立場に置かないように定めた法律です。以下の取引に適用されます。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
下請法が適用されない場合、独禁法(独占禁止法)が適用されることがあります。また「偽装請負」と判断されると、労働基準法や労働組合法が適用される可能性もあります。どちらにしても契約内容を逸脱した働き方をさせると、何かしらの法律違反に問われるリスクがあることを覚えておきましょう。
違反した企業は、社名や違反内容が公表されるため、取引先からの信頼を失うおそれがあります。フリーランスへ外注するときは、こうした関係法令も理解して、お互いに対等な立場で仕事を進められるように努めることが大切です。
関連記事:業務委託で直接契約する際の禁止行為とエージェント活用のメリットを解説
3. 業務内容にあわせた契約を結ぶ
フリーランスと業務委託契約を結ぶときは、業務内容に適した契約形態を選ぶことが大切です。この選択は企業が勝手に決められるものではありません。
たとえば、請負契約を結んでいるのに企業が指示・管理を行っている場合、雇用契約とみなされる可能性があります。この状態は「偽装請負」に該当するため、労働基準法違反となるのです。
- 業務の目的
- 指揮命令の有無
- 勤務時間の指定
- 報酬の支払い方
これらを確認のうえ、適切な契約を結びましょう。
関連記事:業務委託契約を締結する際に起こりがちなトラブル事例6つと対処法を解説
フリーランスに外注するならエージェントサービスがおすすめ
フリーランスへ外注するために、業務委託の性質や関連法令について理解するのはたいへんです。フリーランス専門のエージェントサービスを利用することで、採用コストを抑えて求める人材を確保できます。
要望に沿った人材を提案してくれる
エージェントサービスは、企業のニーズにあわせた人材を提案してくれます。登録人材は独自の基準で審査していることもあり、採用難易度が高い職種でも要望に沿った人材を提案することが可能です。
デザイン業務の外注をお考えなら、フリーランスデザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』がおすすめです。以下ではクロスデザイナーに登録しているフリーランスデザイナーを一部ご紹介しています。ダウンロードは無料です。
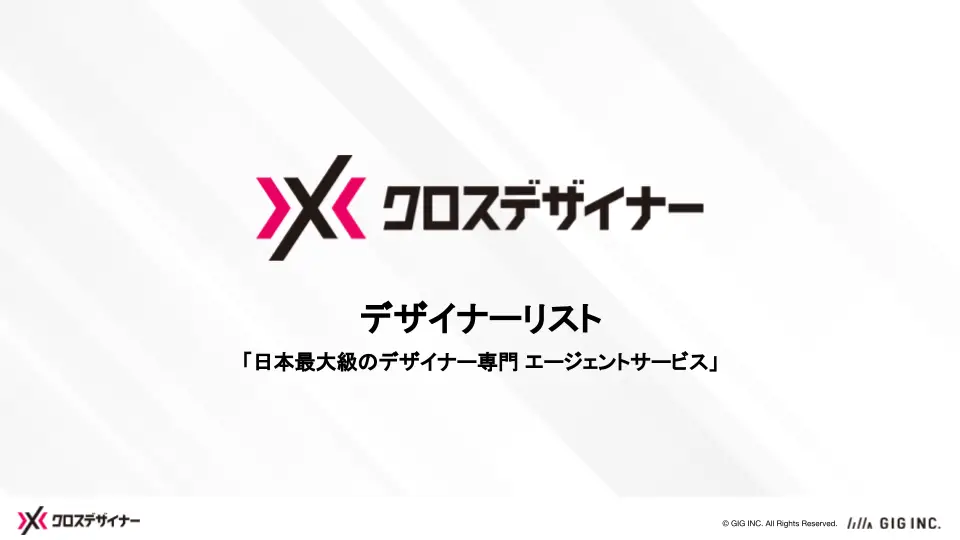
全額「外注費」で計上できる
エージェントサービスを利用することで、支払う費用はすべて「外注費」として計上が可能です。報酬以外に支払う費用もすべて外注費として一括の計上が可能になります。こまかく分ける必要もないため、経理業務の効率化にもつながります。
案件にあわせて柔軟に契約を結べる
エージェントサービスと結ぶ契約は、業務委託契約のため案件規模やプロジェクトにあわせて柔軟な契約を結ぶことが可能です。多くが自由度の高い準委任契約を採用しています。
クリエイティブやWeb案件の場合、成果物の仕様が変更するケースもあるため、準委任契約が適しているのです。エージェントサービスはこうした契約まわりもサポートしてくれるため、初めての外注でもスムーズに依頼することが可能です。
以下の資料では、準委任契約の特徴についてまとめています。有効な活用方法も紹介していますので、フリーランスへ外注を検討されている方は、ぜひお役立てください。

デザイナーへの外注ならクロスデザイナーがおすすめ!
本記事では、フリーランスへ外注する方法や注意点について解説をしました。外注するメリットやデメリットをふまえて、自社にあった外注先を見つけることが大切です。外注時に締結する業務委託契約は下請法をはじめ、労働に課する法律なども理解する必要があります。
なお、デザイナーの外注は『クロスデザイナー』がおすすめです。

クロスデザイナーは約7,000人のデザイナーから要望に応じて厳選したデザイナーを紹介するデザイナー専門のエージェントサービスです。実績豊富なデザイナーと準委任契約を結ぶまでサポートいたします。
業務拡大やコンテンツ制作の強化などで優秀なデザイナーをお探しならぜひクロスデザイナーの利用を検討してください。登録費無料です。気になる方は無料のサービス資料を下記よりダウンロードしてください。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents