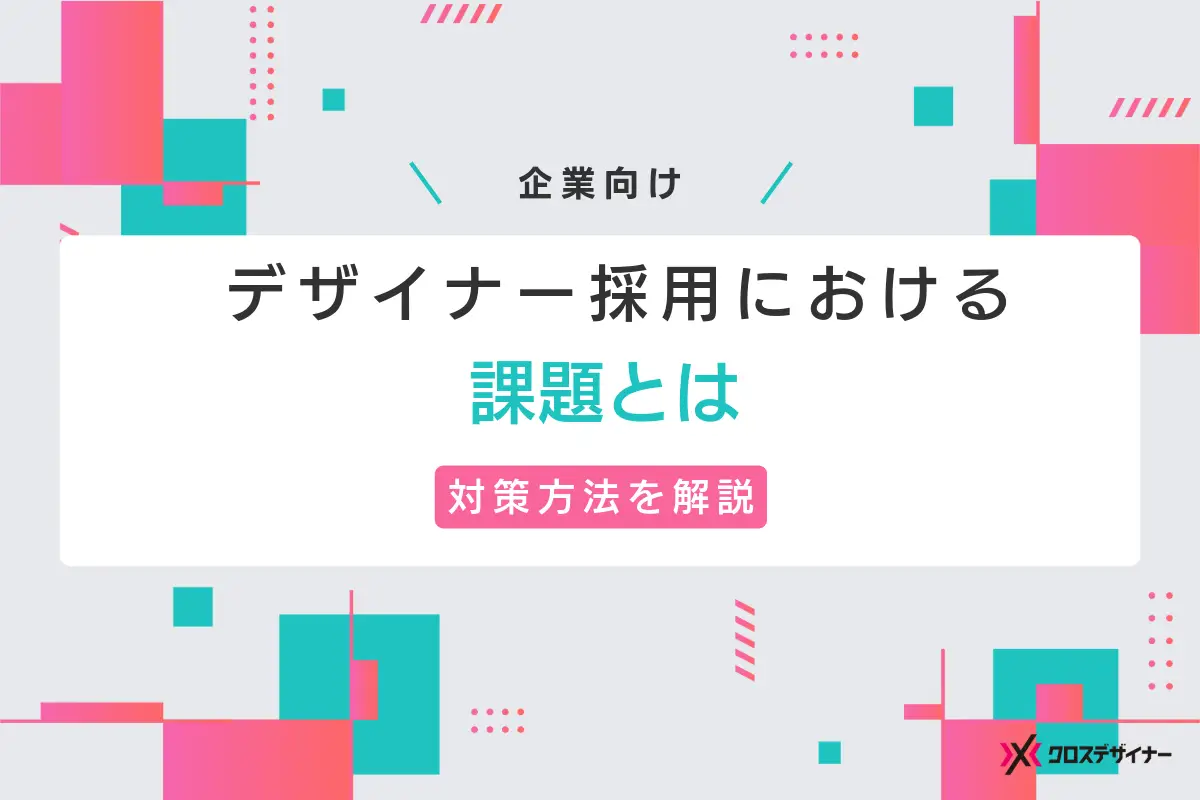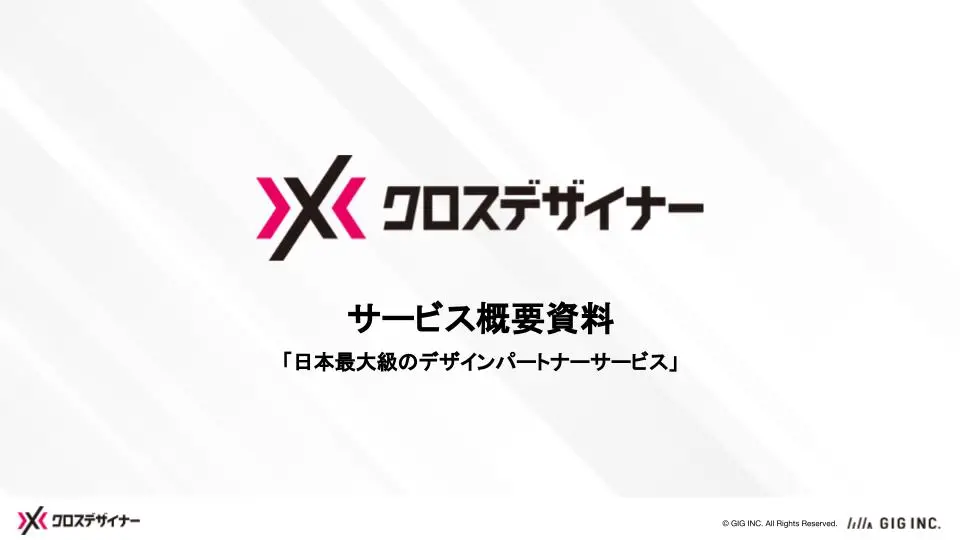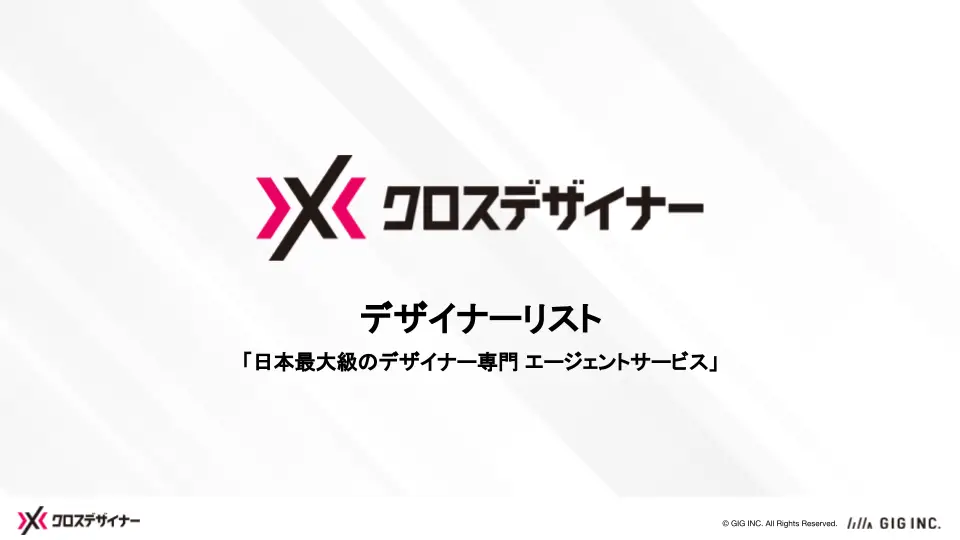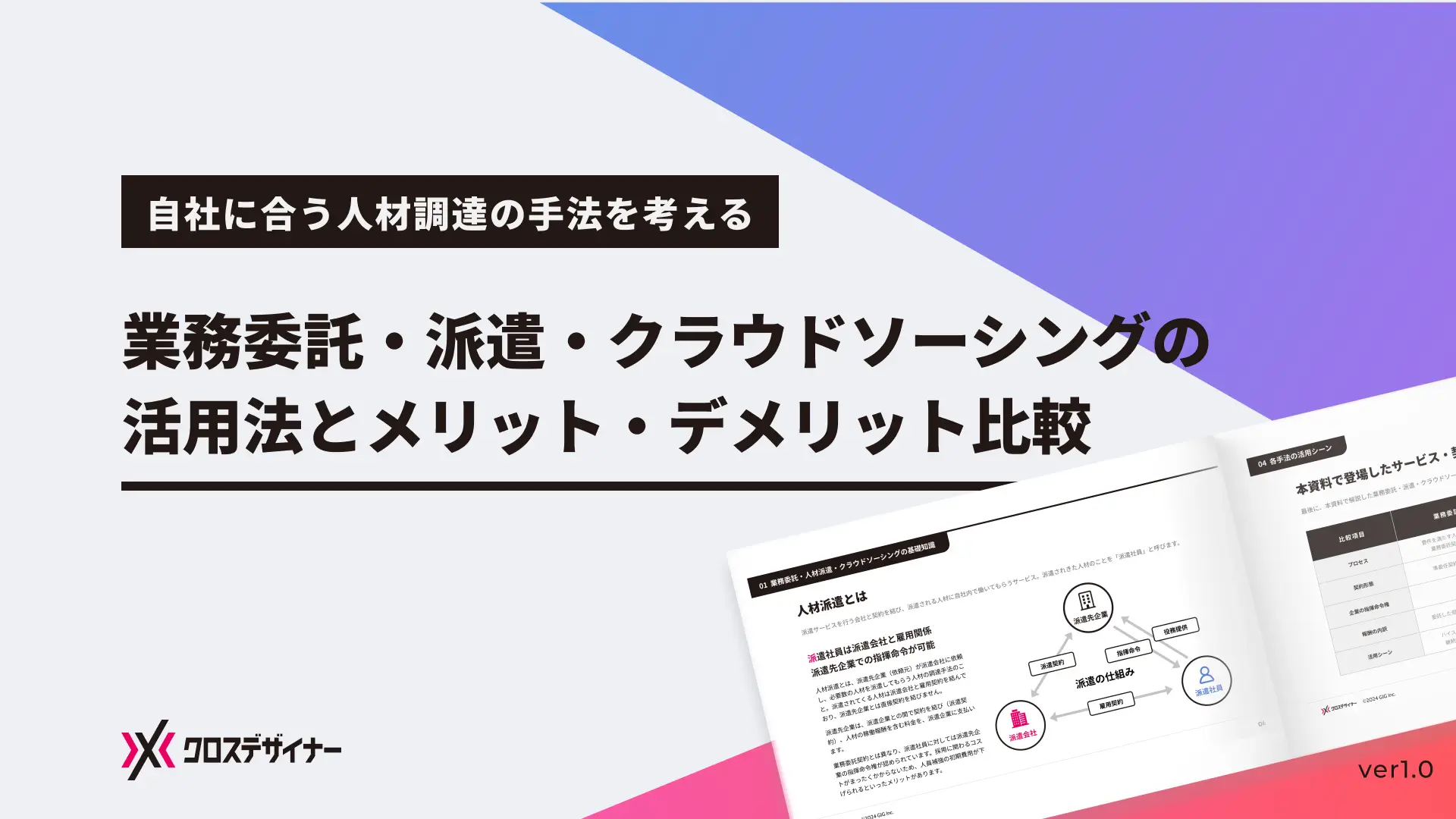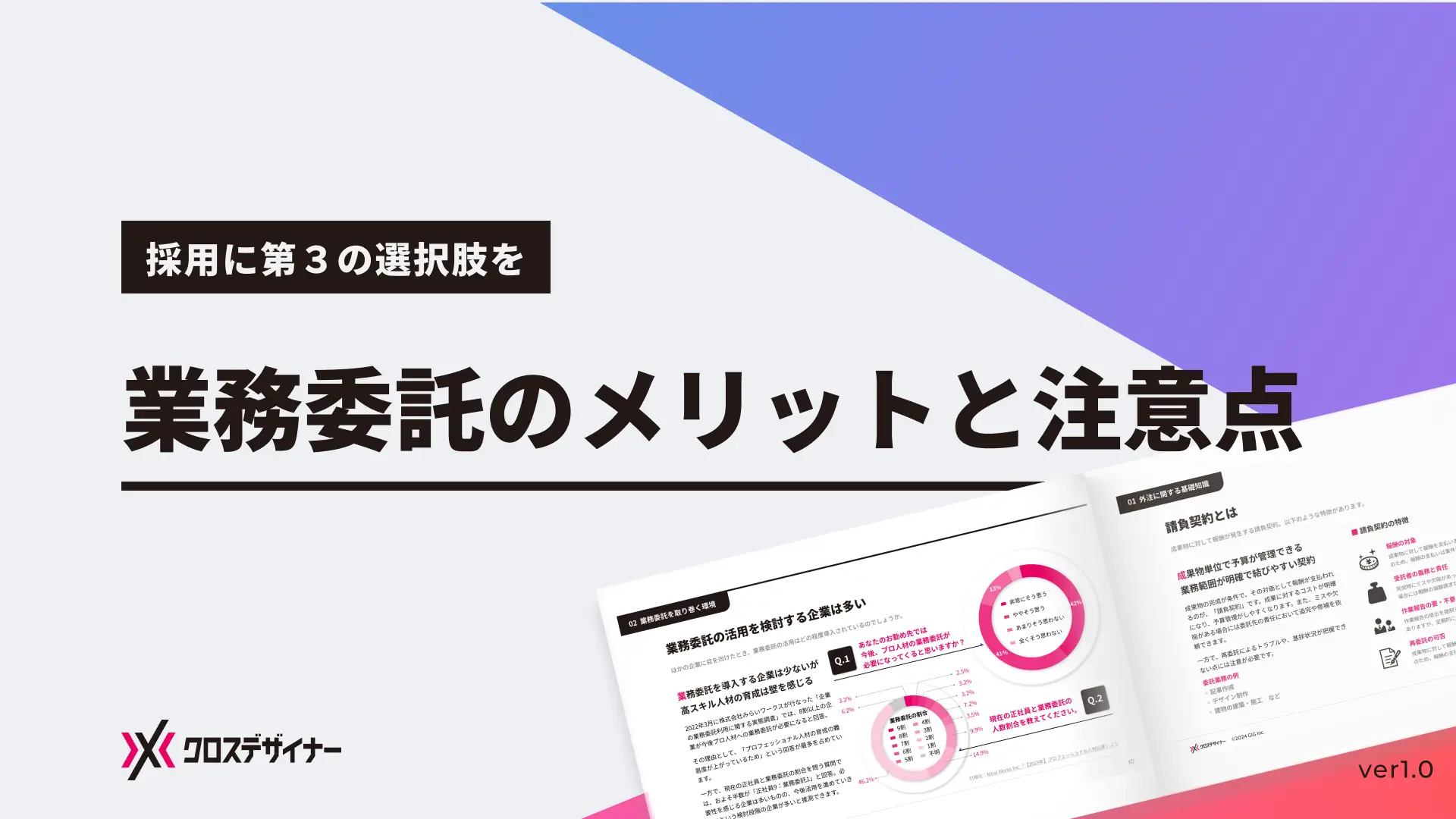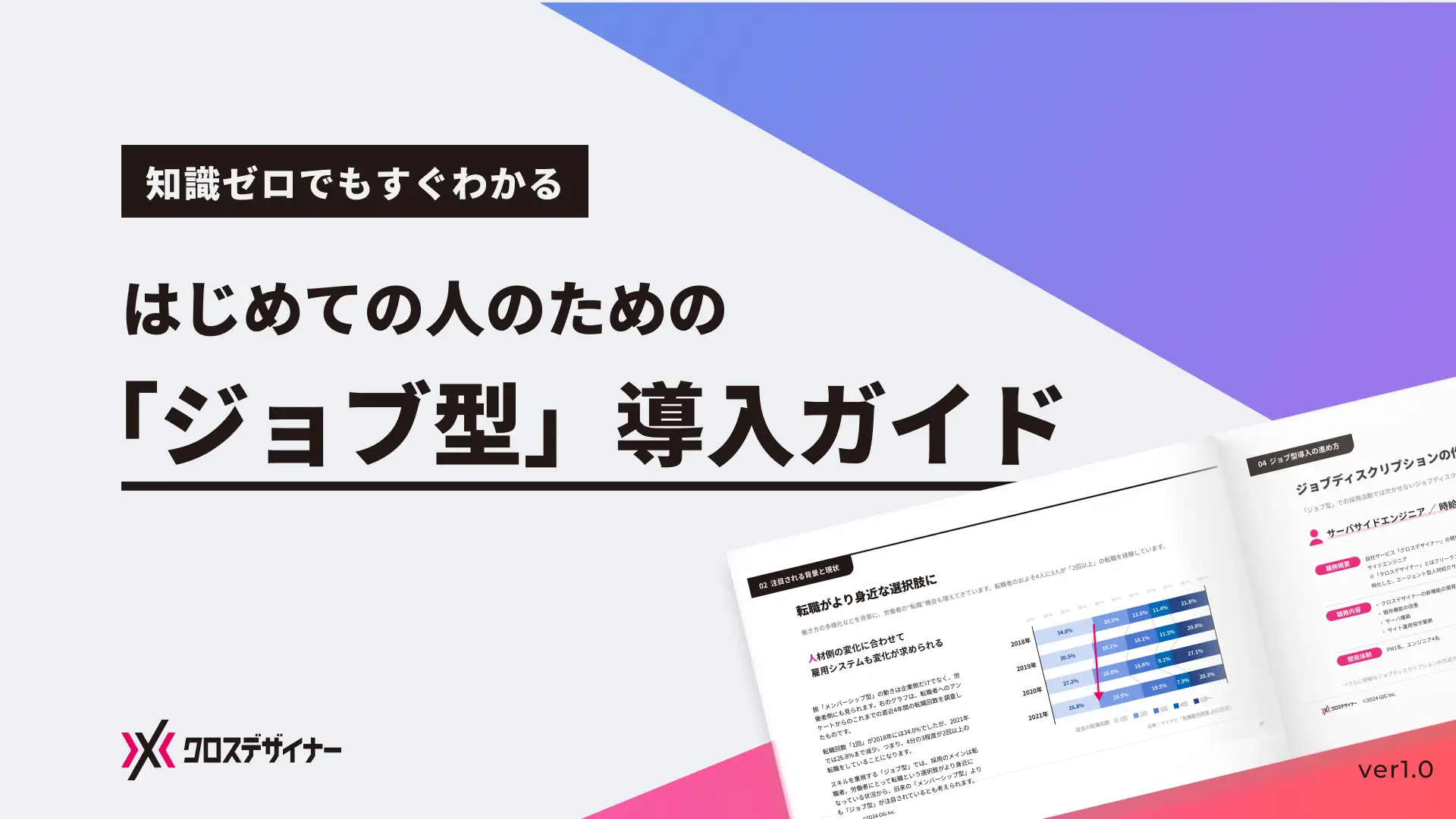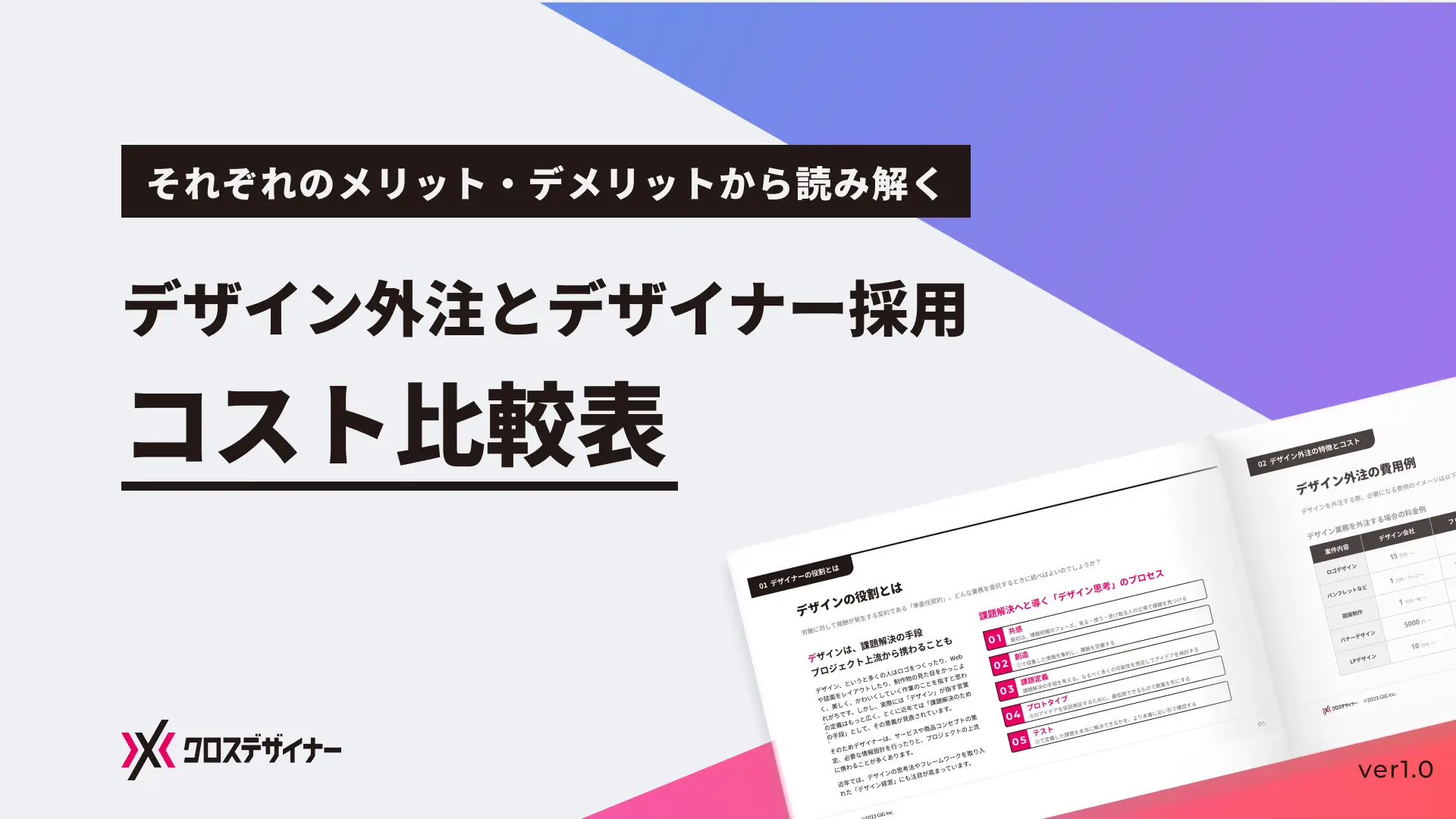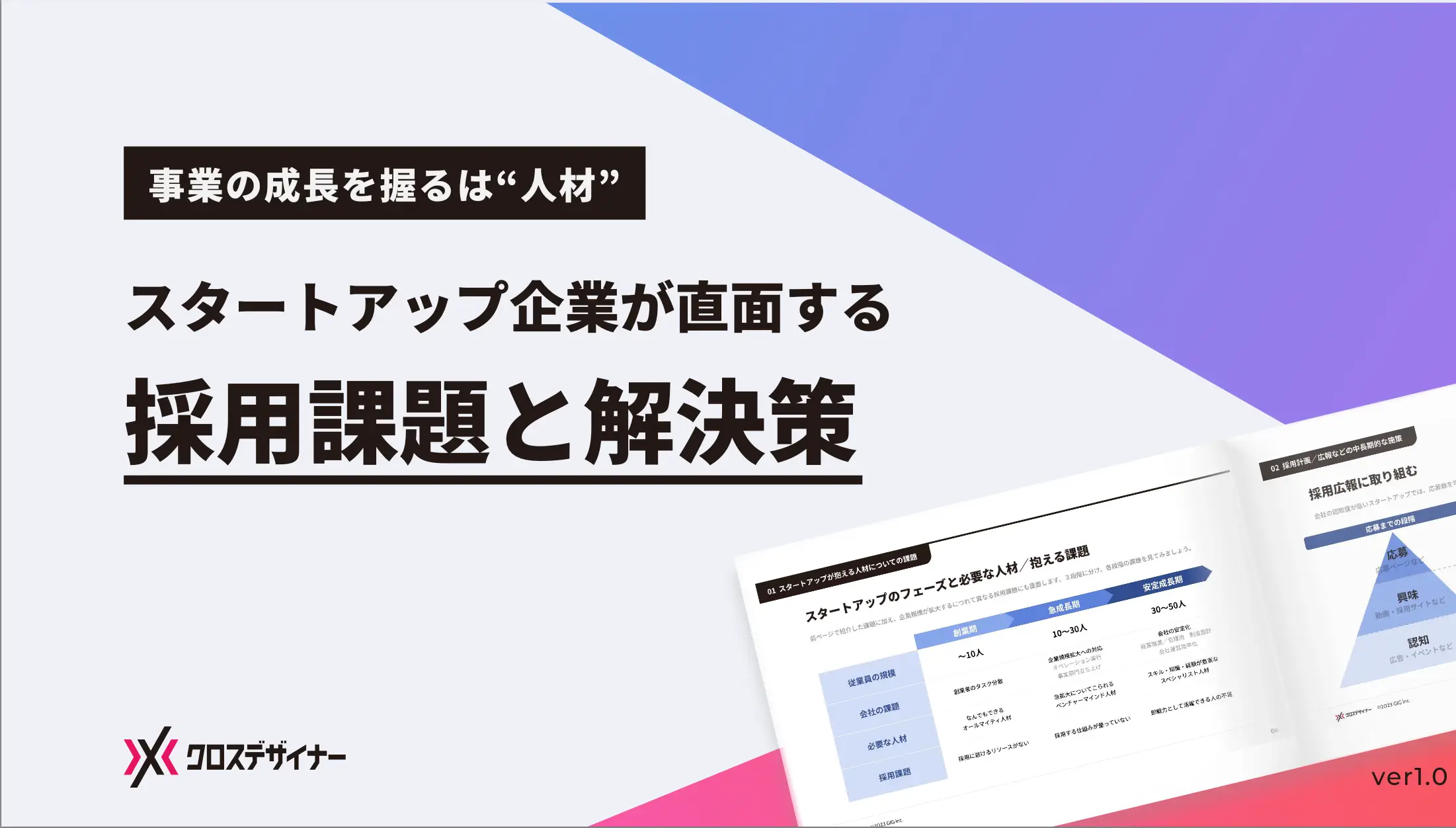外部のリソースを効果的に活用する手段として、「業務委託」が一般的になってきました。
上手く活用することで、専門家に手伝ってもらえたり、人件費を抑えることができたり、メリットが多いのが業務委託です。
「業務委託」とは契約形態の一つです。契約である以上、「知らずになんとなくやってみる」では、後になって大きな損失やトラブルにつながるおそれもあります。
そこで本記事では、業務委託を考えている方に向けて、契約の種類やメリット・デメリット、契約書で必ず明記すべき事項を解説します。
業務委託を網羅的に理解できるようになるため、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも業務委託とは? 簡単に解説
そもそも業務委託とは外注方法の1つで、自社の業務を外部の企業や個人事業主(フリーランス)などに委託する方法です。
ちなみに「業務委託契約」という契約方法は法律上は存在せず、法律上で示された「(準)委任契約」と「請負契約」をあわせて「業務委託契約」と言われています。
業務委託の特徴として、依頼側と受託側が対等な関係である点が挙げられます。正社員やアルバイトの場合、雇用主と社員は主従関係にあり、雇用主は社員に指揮命令が可能です。
一方で業務委託の場合は対等な関係なため、勤務時間や勤務場所を指示するような指揮命令はできません。
▼下記の資料では、業務委託人材の労務管理の注意点やポイントを、正社員とも比較しながら解説します。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

業務委託契約と雇用契約、派遣契約の違いは?
業務を依頼したいとき、契約方法としては業務委託契約以外にも、雇用契約や派遣契約もあります。それぞれの違いについて理解をしたうえで、業務委託契約を活用すべきか検討しましょう。
企業視点で見たとき、業務委託と雇用契約、派遣契約の違いは下記の表のとおりです。
| 業務委託契約 | 雇用契約 | 派遣契約 | |
| 雇用主 | なし | 就業企業 | 派遣会社 |
| 勤務時間の制約 | なし | あり | あり |
| 指揮命令 | 不可能 | 可能 | 可能 |
| 提供されるもの | ・業務の遂行(準委任/委任契約) | 労働力 | 労働力 |
| 社会保険料の支払い | なし | あり | なし(派遣元が支払う) |
| 3年ルール | なし | なし | あり |
詳しく解説します。
業務委託契約と雇用契約との違い
| 業務委託契約 | 雇用契約 | |
| 雇用主 | なし | 採用企業 |
| 勤務時間の制約 | なし | あり |
| 指揮命令 | 不可能 | 可能 |
| 提供されるもの | ・業務の遂行(準委任/委任契約) | 納品物 |
| 社会保険料の支払い | なし | あり(就業先) |
雇用契約とは、会社が正社員やアルバイトを雇用する契約方法です。雇用主と社員は主従関係にあります。
業務委託と雇用契約の違いは、大きく2つです。
1つ目は、指揮命令権の有無です。業務委託契約の場合は、あくまで依頼主と受託側が対等な関係にあるため、依頼する業務に対して細かく指揮命令することができません。たとえば働く曜日や仕事方法などを細かく指定することは、規約違反となります。
一方雇用契約の場合は、主従関係にあることから指揮命令が可能です。働く場所や勤務時間、業務の進め方など、細かい指定ができ、よりこちらの提案に沿った働き方を実現させることができます。
2つ目は、社会保険の有無です。業務委託契約の場合は、企業が社会保険料を負担する必要がありません。健康保険や厚生年金、雇用保険など、各種保険料を支払う必要がない点は、大きなコスト削減になるでしょう。
一方、雇用契約の場合は、各種保険の加入義務があるため、企業側は上記の保険料の支払いが必須となります。
業務委託契約と派遣契約との違い
| 業務委託契約 | 派遣契約 | |
| 雇用主 | なし | 派遣会社 |
| 勤務時間の制約 | なし | あり |
| 指揮命令 | 不可能 | 可能 |
| 提供されるもの | ・業務の遂行(準委任/委任契約) | 労働力 |
| 社会保険料の支払い | なし | なし(派遣元が支払う) |
| 3年ルール | なし | あり |
派遣契約とは、派遣元と派遣先の企業が結ぶ契約のことです。
業務委託契約と派遣契約の違いは、大きく2つです。
1つ目は、指揮命令権の有無です。先述のとおり、業務委託契約は指揮命令が認められていません。一方で派遣契約の場合は、派遣社員と派遣先は直接雇用ではありませんが、指揮命令が認められています。
2つ目は、3年ルールの有無です。3年ルールとは、派遣法により「派遣社員が同一事業所や部署で働くことが3年まで」と定めたものです。
よって派遣社員は、3年ルールを考慮したうえで、マニュアル化された事務作業が依頼されることが多くなっています。
一方業務委託契約の場合は、法律上で委託期間の禁止事項はありません。スキルや報酬面において互いに問題がなければ、継続的な依頼が可能です。
▼下記の資料は、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

業務委託契約の種類3つ
業務委託契約と一口に言っても、契約方法は「請負契約」、「委任契約」、「準委任契約」の3種類あります。
それぞれの特徴は、下記のとおりです。
| 請負契約 | 委任契約 | 準委任契約 | |
| 作業内容 | 完成を約束した業務 | 法律行為 | 法律行為以外の業務 |
| 契約不適合責任(瑕疵担保責任) | あり | なし | なし |
| 善管注意義務 | なし | あり | あり |
| 再委託の可否 | 可能 | 不可能 | 不可能 |
| 報酬の基準 | 成果物 | 工数や作業時間 | 工数や作業時間 |
| 報酬発生のタイミング | 成果物の納品 | 依頼業務の完成したタイミング | 依頼業務の完成したタイミング |
| 中途解約の可否 | 完成するまでなら可能 | いつでも可能 | いつでも可能 |
詳しく解説していきます。
請負契約
| 請負契約 | |
| 作業内容 | 完成を約束した業務 |
| 契約不適合責任(瑕疵担保責任) | あり |
| 善管注意義務 | なし |
| 再委託の可否 | 可能 |
| 報酬の基準 | 成果物 |
| 報酬発生のタイミング | 成果物の納品 |
| 中途解約の可否 | 完成するまでなら可能 |
請負契約とは、成果物納品を約束した契約方法です。支払いは依頼したものが完成したタイミングで発生します。
成果物納品を目的とした契約のため、主にWebメディアの記事やデザイン、システム開発を依頼する際に活用されることが多いです。
請負契約の特徴的な点は、受注者に契約不適合責任が伴う点です。契約不適合責任とは成果物に対して欠陥があった場合、受注者が負う責任のことで、発注者は受注者に欠陥部分の修正や損害賠償請求を行えます。
また中途解約について、成果物が納品されるまでは可能となっていますが、受注者に不利益が発生するときは、発注者側が損害賠償する必要があります。
委任契約
| 委任契約 | |
| 作業内容 | 法律行為 |
| 契約不適合責任(瑕疵担保責任) | なし |
| 善管注意義務 | あり |
| 再委託の可否 | 不可能 |
| 報酬の基準 | 工数や作業時間 |
| 報酬発生のタイミング | 依頼業務の完成したタイミング |
| 中途解約の可否 | いつでも可能 |
委任契約とは、法律行為を委託するものです。弁護士に訴訟代理を依頼したり、税理士に確定申告を依頼したりする業務は、委任契約に該当します。
委任契約の場合は、報酬の基準が工数や作業時間で判断されます。
それに伴い、成果物に対して責任を負う契約不適合責任がない一方で、善管注意義務を負います。
善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」の略で、簡単に言うと「やるべきことをきちんとやらなければならない義務」です。
そのため成果物に対して責任が問われなくても、クオリティを担保しない行為は発注者側が損害賠償請求を行うことができます。
また中途解約については、双方の合意があればいつでも可能となっています。
準委任契約
| 準委任契約 | |
| 作業内容 | 法律行為以外の業務 |
| 契約不適合責任(瑕疵担保責任) | なし |
| 善管注意義務 | あり |
| 再委託の可否 | 不可能 |
| 報酬の基準 | 工数や作業時間 |
| 報酬発生のタイミング | 依頼業務の完成したタイミング |
| 中途解約の可否 | いつでも可能 |
準委任契約とは、法律行為の伴わない委任契約のことです。
企業が業務委託を行う場合は、委任契約よりも準委任契約を結ぶことが多いでしょう。
準委任契約は、アプリ開発やWebメディアの設計、Webサイト制作などにおいて、人手やノウハウが足りず、柔軟に依頼内容を変更したいときに活用されます。
契約内容は準委任契約とほぼ変わらず、報酬は依頼業務に伴って時給で支払われることが多いです。
関連記事:準委任契約とは? 請負契約との違いやメリット、デメリットを解説
▼以下の資料では、安心して業務委託を活用できるように、契約形態ごとの概要や特徴を一覧表で比較解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

企業が業務委託契約をするメリット3つ
企業が雇用契約や派遣契約ではなく、業務委託契約をするメリットは全部で3つあります。
・専門家のリソースを借りられる
・柔軟にリソースを借りられる
・人件費を抑えられる
順番に解説します。
1. 専門家のリソースを借りられる
WebデザインやUI/UXデザイン、プログラミングなど、企業が新しいサービスを設計したいときに、必ずしもそのノウハウが自社にあるとは限りません。
業務委託を活用すれば、たとえ自社にノウハウがなくても、専門家のリソースを借りることができます。また全体の業務のうち、一部だけを専門家のリソースを借りることも可能です。
たとえばWebサイト制作において、実装面は自社で対応できるのに対し、デザイン面のノウハウが欠けている場合、デザイナーのみ業務委託で依頼すれば業務を円滑に進められるでしょう。
2. 柔軟にリソースを借りられる
会社の方針、予算、業務は、流動的です。今必要なスキルや人材が、この先もずっと必要になるとは限りません。
その点業務委託であれば、請負契約や準委任契約を通じて、柔軟にリソースを借りられます。たとえばデザインの案件を複数受注して社内デザイナーのリソースではカバーしきれないときも、業務委託契約を通じて一時的にリソースを借りられるでしょう。
また業務委託で依頼するフリーランスは、普段から類似業務を受注していることから、高いスキルを保有していることが多いため、稼働開始日から即戦力を期待できます。
3. 人件費を抑えられる
社員を直接雇用する場合、健康保険や厚生年金、福利厚生費などの人件費が発生します。企業が負担する社会保険料は、月給20万円の場合で月30,000円程度、年360,000円程度となります。
社会保険料は月給に応じて企業側の負担額も増えるため、業務委託契約によってこれらの人件費を抑えて依頼できる点は大きなメリットと言えるでしょう。
企業が業務委託をするデメリット3つ
企業が業務委託を活用するのはメリットだけではありません。3つのデメリットもあるため、これらを理解したうえで、適切な活用を目指しましょう。
・依頼コストが高くなる場合もある
・ノウハウが蓄積しづらい
・成果物の質をコントロールしにくい
順番に解説します。
1. 依頼コストが高くなる場合もある
デザインやアプリ開発などの専門性の高い業務を依頼する場合は、需要もあり、コストが高くなるおそれもあります。
先述のとおり、業務委託では社会保険料の支払い義務がないことから、人件費の節約につながります。しかし一方で、依頼費用が高くなることがある点は理解しておきましょう。
コストを少しでも抑えたい場合は、自社でできる限り内製化することが重要です。Webサイト設計であれば、ワイヤーフレーム設計、デザイン、コーディングのなかで一部だけ依頼すれば、コストを抑えられるでしょう。
2. ノウハウが蓄積しづらい
業務委託では指揮命令権がなく、基本的に受注者側に業務を任せます。よって依頼業務の内製化を将来的に考えている場合、そのノウハウを蓄積しづらいのはデメリットとなり得ます。
業務委託した内容について、スキルやノウハウを自社に取り入れていきたいときは、定期的なコミュニケーションがおすすめです。
委託した内容について、進捗を聞くとともに、工夫点や使用したツールを定期的にヒアリングしていくことで、自社にノウハウを残していくことができます。
3. 成果物の質をコントロールしにくい
社員同士の場合は、出社やミーティングでコミュニケーションを取ることで、業務の進捗やクオリティを確認できるため、成果物のコントロールがしやすいです。
一方で業務委託の場合は、社員に比べてコミュニケーションが少ない傾向にあります。よって依頼業務について丸投げした場合、想定していた成果物と違っているケースもあるでしょう。
成果物の質については、スキルの高い人材に依頼する場合でも丸投げはせず、定期的なコミュニケーションを取ることで、コントロールしやすくなるでしょう。
業務委託契約の流れ4ステップ
業務委託契約を進めるときは、次の4ステップで契約しましょう。
【業務委託契約4ステップ】
1. 契約形態の決定
2. 契約内容のすり合わせ
3. 契約書の作成
4. 契約締結
まずは「請負契約」、「準委任契約」のどちらで依頼すべきか決めましょう。一度の成果物納品であれば「請負契約」のほうが相性が良く、ある業務について一定期間依頼していきたいならば「準委任契約」のほうが相性が良いです。
依頼したい人が決定したら、具体的な契約内容のすり合わせを行います。契約書を作成してから、「考えていたものと違った」となると余計な工数がかかるため、テキスト、口頭ベースで業務内容をすり合わせていきましょう。
依頼業務範囲や契約期間、金額、使用ツールなどを共有しておくと安心です。
すり合わせのうえ、双方問題なければ業務委託契約書を作成します。業務委託契約書は必須ではないですが、報酬やツール、依頼業務についてトラブルが発生したときに、適切に対処するためにも業務委託契約書は作ったほうが良いです。
契約書に記載すべき内容については、後述します。
業務委託契約書を作成したら、最後は契約の締結です。締結後は具体的な業務について、適宜共有していきましょう。
▼下記からは、業務委託に必要な4種類の契約書を、すぐに使えるテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

業務委託契約書に記載すべき13項目
先述のとおり、業務委託契約書は必須ではありませんが、作成することで契約後のトラブルを限りなく防ぐことができます。特に報酬面や知的財産権、秘密保持など、事前に契約書を結んでおかないと、責任の所在が不明瞭となってしまうため、下記の内容を参考に必ず明記しましょう。
| 内容 | |
| 業務内容 | 具体的な業務内容を記載。 |
| 報酬 | 業務委託の報酬を記載。請負契約の場合は対価をそのまま、(準)委任契約の場合は時給等を記載する。 |
| 支払条件 | 報酬の支払い方を記載。 |
| 成果物の権利(知的財産権) | 成果物について、知的財産権の所在を記載。 |
| 再委託 | 業務委託内容を第三者に再委託するのが可能かどうか記載。通常、請負契約は再委託が可能で、(準)委任契約は禁止されている。 |
| 秘密保持 | 業務委託に伴い、得た情報を第三者に開示しないことを記載。 |
| 契約解除 | 業務委託契約に関して違反や不利益を被った場合、契約解除できることを記載。 |
| 契約期間 | 契約期間を記載。 |
| 禁止事項 | 業務委託で禁止事項があれば記載。 |
| 反社会勢力の排除 | 依頼者、受注者が反社会勢力と関わりがあった場合、直ちに契約解除できることを記載。 |
| 損害賠償 | 業務委託契約において違反及び損害が発生した場合は、損害賠償することを記載。 |
| 契約不適合事項(瑕疵担保責任) | 請負契約で記載。成果物についてクオリティが担保されていない場合、修正や報酬の減額、損害賠償、契約解除ができることを記載。 |
| 管轄裁判所 | 業務委託でトラブルが発生した場合、どの裁判所で裁判を行うか記載。 |
作成した契約書については、必ず受注者に共有し、内容に問題がないか確認してもらいましょう。
▼下記の資料では、業務委託契約書を作成する際の重要なポイントを網羅的に解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

【リスクを抑える】業務委託契約の注意点4つ
業務委託は自社にないノウハウやスキルを生かして業務を効率化できる一方で、発注方法に注意を払わないと訴えられるリスクもあります。
そのようなリスクを抑えるためにも、次の4点には注意しましょう。
・偽装請負にならなにように注意する
・下請法に注意する
・秘密保持契約(NDA)を別途締結する
・請負契約は収入印紙が必要な場合がある
1. 偽装請負にならないよう注意する
偽装請負とは、業務委託契約において、発注者が受注者に指揮命令している状態を指します。業務委託契約では発注者と受注者は対等な関係であり、指揮命令することは禁じられています。
それにも関わらず、発注者が受注者に勤怠管理を指示していたり、働き方を指示したりすると、偽装請負となります。
偽装請負が認められた場合は、労働基準法に則り「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(労働基準法118条)が課せられるおそれもあります。
双方の合意がなく、逸脱した指示をしていないか、業務委託契約の際は念入りに確認しましょう。
2. 下請法に注意する
下請法とは「下請代金支払遅延等防止法」の略称で、発注者が立場を利用して受注者へ不当な扱いをすることを防ぐ法律です。
発注者側の資本が1000万円を超え、下記の4つの業務を依頼する場合に下請法の規制対象となります。
【依頼内容】
・製造委託(物品の製造や加工の委託)
・修理委託
・情報成果物作成委託(デザインやプログラム、映像コンテンツなど)
・役務提供委託(運送やビルメンテナンスなど)
これらの依頼内容に該当する場合、発注者側は支払い額や支払い期日を記した書面を受注側に交付しなければいけません。
不当な価格での依頼など、下請法への抵触が見られたときは、発注者側が50万円以下の罰金を科せられるおそれもあります(下請法10条1号)。
3. 秘密保持契約(NDA)を別途締結する
企業の秘密情報が漏洩した場合、会社独自のノウハウが他社で利用されてしまうなど、会社にとって大きな不利益が発生するおそれがあります。よって秘密保持契約書(NDA)を別途用意し、受注者側の情報の取り扱いの意識を高めるようにしましょう。
秘密保持契約書内では、何が秘密情報に該当するか詳細に記載します。また秘密情報のコピーでも同様の価値があることや、データ保管等の注意点も記載し、万が一漏洩があった場合も、責任の所在が明らかになるようにしましょう。
4. 請負契約は収入印紙が必要な場合がある
収入印紙とは、契約書で支払う必要がある税金について、支払いを証明するものです。請負契約について、書面で契約を結ぶ場合は、収入印紙の支払いが発生することがあります。
具体的には契約金額が1万円未満であれば支払いが不要、1万円以上であれば契約金額に応じて支払いが発生します。(参考:国税庁)
ただし請負契約であっても、紙の書面ではなく電子契約であれば支払いは必要ありません。
デザイナーへの業務委託ならクロスデザイナーがおすすめ!
本記事では、業務委託契約の特徴について簡単にまとめました。
業務委託契約では、
・専門家のリソースを借りられる
・欲しいタイミングで柔軟にリソースを借りられる
・人件費を抑えられる
などのメリットがあるため、会社の業務で一時的に人手が足りなかったり、専門家に業務を依頼したかったりする場合は、積極的に業務委託契約を活用しましょう。
なお、デザイン業務において、業務委託で依頼したいならクロスデザイナーがおすすめです。

クロスデザイナーは7000名以上のデザイナーが在籍する国内最大規模のデザイナー専門エージェントサービスです。
審査通過率5%を突破した優秀なフリーランスデザイナーを、業務内容にあわせて提案します。業務内容はWebデザイン、UI/UXデザイン、アプリデザイン、DTPなど、幅広く対応可能です。
週2~3日の柔軟な依頼もでき、最短3営業日でアサインもできます。採用難易度の高いデザイナーへ依頼し、他者と差別化したデザインを完成させたい場合は、ぜひクロスデザイナーをご活用ください。
無料のサービス資料もご用意しております。ぜひ下記より無料でダウンロードし貴社のデザイナー採用にお役立てください。
- クロスデザイナーの特徴
- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例
- 各サービスプラン概要
- 支援実績・お客様の声
Documents